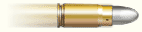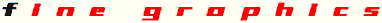Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
ロングテールズFILE;vol.8
映画 『カノン』 (1998年公開)
僕はサム・ライミの新作映画『スペル』を観て、びっくりしてしまった。
何がびっくりしたかというと、この映画に何かしら衝撃を受けた、という意味ではなくて、この映画はとにかく〝びっくり〟させる映画なのである。
僕らがサム・ライミに期待するのは、当然、『死霊のはらわた』シリーズや『XYZマーダーズ』、また『ダークマン』のような、初期の、グロテスクで悪趣味な〝失笑〟の世界である。
そういう意味では『スペル』は、ちょうど『スパイダーマン』を経た後のサム・ライミが、本格的な特殊効果を含めた大作趣味と、本来のチープなシニシズムとの折り合いをそれなりに上手くとった作品だと思う。
しかし、そういうことよりも何よりも、これ程こけおどしの〝おどかし〟に徹した映画はちょっとない。
それも心臓の悪い人なら本気で逝きかねない程のデンジャラス具合いである。
とにかく、ワッと出てびっくりさせる。
あっちからもこっちからもワッと出て、何でもかんでもびっくりさせるのだ。
しかも、仕掛けはおどろな婆さん、ほぼ、一体のみ!!
なにせ万事が瞬間ドキッ!オンリーで成立しているものだから、実際、後で思い返して、何が怖かったのか、さっぱりわからない程である。
更にどうでもいいことだが、実は僕は、これを観る前に松田優作の新しいドキュメンタリー映画を観ていて、ここで既にびっくりしていたから、この日はいろんな意味で、とんだびっくり記念日であった。
こちらの方は、松田優作死後何年だかいう名目以外、どこから観ても、作る必要も理由もない映画であった。
どうも僕は、俳優・松田優作の映画に影響を受け過ぎているせいか、素の彼にお世話になった人とか、遺族とかの話しを聞いてみたい気持ちが皆無である。
と、いうより、裏の実像など出なければ出ない程良い。
また、『ブラック・レイン』が、日本人俳優のハリウッド進出という意味で重要だったとかいうけれど、そんなバックステージの野望など関係無い観客にとって、松田優作、リドリー・スコット何れのフィルモグラフィーに於いても、あんなのは取るに足らない凡作である。
それが証拠に、果して日本以外のどこの国で、あの『ブラック・レイン』という作品を問題にする国があるだろう?
本音を言えば、世界にもっと知って欲しいのは、日本人俳優がハリウッドのオーディションにパスした希な記念碑、などという、超ローカルな話題なんかではなく、かつて日本に、『探偵物語』や『野獣死すべし』や『陽炎座』や『家族ゲーム』や『それから』といった、素晴らしくクールな映画があり、それらを体現した唯一無二の男がいた、という事実である。
今頃になってまでハリウッドをステータスとして仰ぎ見ることより、むしろ、それ以前の彼の仕事こそ、日本映画が世界に冠たる誇りだ、とか何とか言い切ればいいのではないか。
実際、僕は、『陽炎座』程の本物の作品を経験しながら、どうしたら『ブラック・レイン』云々などという話になるのか、当時から皆目、不可解な気持ちではあった。
まあ、何れにしろ、僕らにとって「松田優作」は、彼が遺した映画の中にしか存在しないし、それこそ彼が望んだ映画人としての魂である。
また、その魂の結実する点が『ブラック・レイン』だ、などと見なされるなら、彼の映画人生は、皆が思うより浮かばれないとも思っている。
ま、というようなことはほんとはどうでもいいのだが、実は僕がここで考えたいのは、〝こけおどし〟ではない、真の〝映画の怖さ〟とはどんなものか、ということだった。
〝怖い映画〟ではなく、〝映画の怖さ〟である。
補足すると、〝怖い映画〟とは、まあ、ホラー映画のような、元々、怖い題材をテーマとした映画のことである。
例えば、『悪魔のいけにえ』しかり
『エクソシスト』しかり『死霊のはらわた』しかり…。
これらは元々、〝怖さ〟という契約条件の元に取り引きされているから、単純にビジュアル自体が360度怖気なものを創作することになる。ただし、現実に謂われなき恐怖の産物などまず存在しないから、結果、荒唐無稽なモンスターやオカルティズム、または、殆ど超人化された犯罪者などをフィーチャーするのが大勢である。
まあ、概して即物的なものだ。
これに対して、僕の言う〝映画の怖さ〟を持つ映画とは、映画の中の表面的な身振りや出来事という以上に、この世界の緻密なニュアンスや、社会性というフィクションに隠蔽された心の真相を、淡々と、そして容赦なく暴き、その結果、得も言われぬ不安感や忌まわしさを残すような、そんな作品のことである。
もっとも、こうした、強烈な現実味の手応えから生まれる〝映画の怖さ〟とは、本来、〝不安や忌まわしさを残す〟ような作品にのみ与えられる言葉ではない。だから、これはあくまで、ある種の〝最も凶暴な〟そして〝最も悪質な〟真実の苦味を伝えている映画、に限っての話だ。
さて、(僕の知る限り)最も恐ろしくて、掛け値なしに〝最悪の手応え〟を残す映画とは何だろう?
それは幾つかあるが、これだけははっきりしている。
間違っても人に勧めたりしてはいけない映画のことである。
例えば、ユルグ・ブットゲライト監督のドイツ映画『ネクロマンティック1、2』。また例えば、ブノワ・ポールヴールド、レミー・ベルヴォー、アンドレ・ボンゼル共同監督によるベルギー映画『ありふれた事件』。更には、ギャスパー・ノエ監督のフランス映画『カルネ』とその続編『カノン』、そして『アレックス』。はたまた、ハリウッドでセルフ・リメイクも果たされた、ミヒャエル・ハネケ監督のオーストリア映画『ファニー・ゲーム』など…。
これらはどれも、観客の神経を逆撫でし、凄まじい悪夢を描いた、ということだけはある意味一様なのだが、しかし無論、その意図するところや指向性(あるものは性癖?)に於いては実に様々である。
悪夢といっても、先述の通り、現実の手応えから遊離したところの悪夢を精製する映画ならそれこそ数えきれない程存在する。しかし、これらがそうした作品たちと決定的に違うのは、何より、その悪夢の本質が、フィクションとしての社会性や形骸化された良識という欺瞞の表皮を剥ぎ取り、人間本来の歪(いびつ)さ、狂暴性の在りかを告発するという機能、つまりは、圧倒的なリアリティーの前提の上に立ち上がる悪夢だ、という点であろう。
人間の歪(いびつ)で凶暴な本性を描くことが〝リアリティー〟と書いたが、しかし僕は特にペシミストではないし、これといって皮肉屋という自覚もない。ただ、良し悪しは別として、人間とは本来、暴力性や根拠のない衝動を持つものである。また、これらをコントロールするのが社会の役割りだが、昨今の、凶悪事件の例を待つまでもなく、コントロールできれば人間、コントロールできなければモンスターというような、単純で独善的な図式からは人間性の実態を掬いようがないばかりか、何ら対処の方策ともなり得ないだろう。
もし、あなたがこの世界に絶望せず、尚且つ、生き抜こうと覚悟を決めるなら、まず、ありのままの人間の奥行きを知らなければならない。
例えそれがどんなに居心地悪く、いびつに歪んでいたとしても…。
そう、紛れもなく、映画には、直視すべき〝本能の闇〟もあるのである。
「私の映画を嫌う人々は、なぜ嫌うのか自問しなければなりません。嫌うのは、痛いところを衝かれているからではないでしょうか。痛いところを衝かれたくない、面と向き合いたくないというのが理由ではないでしょうか。面と向き合いたくないものと向き合わされるのはいいことだと私は思います。結局のところ、いかに奈落に突き落とすような恐ろしい物語を作ってみても、我々に襲いかかる現実の恐怖そのものに比べたら、お笑い草にすぎないでしょう。」
(第23回 ぴあフィルムフェスティバル 「知られざる世界の巨匠 ミヒャエル・ハネケ」より)
さて、前掲の〝怖るべき〟映画たちはどれも、様々な点で、とびきりソリッドな問題を孕んだものである。
しかし、中でも、傑出した芸術性という点に於いて、僕は特に、ギャスパー・ノエ監督作を挙げたくなる。
ギャスパー・ノエは現時点で日本公開された作品が、既に述べた作品、『カルネ』、『カノン』、『アレックス』の三作きりである。
しかも、これら三作品は『カノン』が『カルネ』の完全な続編であり(『カルネ』は40分程の中編。したがって、『カノン』が長編第一作となる)、更に、『アレックス』の冒頭シーンに『カノン』のその後が語られることから、これらを統一時間軸の物語りと考えると、何と、これは凄まじい悪夢の抒事詩であった。
『カルネ』、『カノン』の主人公、「肉屋」を演じるフィリップ・ナオンが『アレックス』の導入部で語る「時は全てを破壊する」という献辞は、ギャスパー・ノエ作品に拘らず、まるで、前述の全ての凶悪な映画たちに与えられた〝結句〟のようだ。
「快楽や悦びを忘れちゃいけない
悪行なんてない
ただ行為があるだけ」
ところで、映画『アレックス』は前二作に増して、〝衝撃〟という意味では、突拍子もない作品であった。
極限のシンプルにして、究極の破壊力!
映画の後半、『2001年宇宙の旅』のポスターがパンするシーンがあったけれど、この映画は正しく、映画表現の飛躍点、漆黒のモノリスなのだ、と感じさせる。
ただし、僕には、こと映画というものの問題において、どうしてもあの第二作、『カノン』という作品が引っかかるのである。
というのも、僕はこの作品こそ、全三部作の中で最も映画的アプローチがなされたものだ、と思っているからだ。
そのアプローチとは、つまり、〝映画の中では人は絶望の淵にさえ立つ権利がある〟という最も基本的な〝機能〟であり、映画としての快楽である。
この映画では、主人公が、救いようのない、どん底の淵を彷徨い続ける。ところが、観客がそれを醒めて見つめることで、何か言いしれぬ、魂のカタルシス、または、自由本能の安息感に至る節がある。
勿論、最後まで、社会性に収束するような、安易な希望や解決策が用意されるわけではない。
事実、そんなまやかしの類は一切登場しない。
例えばこの映画の結末部分、男が、実の娘に「ついに生きてく意味を見つけた 俺が女にしてやる」などと〝愛〟の言葉をのたまうが、それ自体は成就するものでも、持続するものでもないのである。
つまり、この映画とは、愛や協調によって解放される魂を描くのではなく、むしろ絶望そのものの中に、純粋な〝個〟としての闘争が浮き上がり、そのことが、他でもなく、社会性を演じる我々の側にこそ、感覚の深層部分で奇妙な解放感とシンパシーを呼び覚ますしくみなのである(言うまでもなく、それはアンビバレントな眩惑を誘うものではあるが)。
そう、これは余りに純粋な〝個〟にまつわる物語りなのだ。
僕は「時は全てを破壊する」という『アレックス』の冒頭のセリフが〝怖るべき映画たち〟の結句のようだ、と書いたけれど、例えば、三島由紀夫の『金閣寺』の、文字通り〝結句〟はこうだった。
「ポケットをさぐると、小刀と手巾に包んだカルモチンの瓶とが出て来た。それを谷底めがけて投げ捨てた。別のポケットの煙草が手に触れた。私は煙草を喫んだ。一卜仕事を終えて一服している人がよくそう思うように、生きようと私は思った。」
周知のように、実際の金閣寺放火事件の犯人は、ここで自殺を試みている。しかし、三島由紀夫は敢えて、その真逆の意志を結末に据えているのである。
実にこの、「生きようと私は思った」というくだりこそ、社会的闘争は終わった。そしてこれから〝個〟の闘争が始まる、という純粋無垢な生の本能を示しているのである。
無論、それは、一切の遮蔽物の無い、生身の闘争であり、社会性を負った観念的存在から、ただ一個の肉体へと変貌したことを意味する。
ここに、『カノン』と同質の、社会倫理さえ超えた〝野性〟とも言える、人間本来の〝牙〟を見出し、何がしか喚起させられるのである。
更にそのことが、諸々の事情のために、常に、個の魂を押し込める、我々の社会を逆照射する。
「生まれ 食べ チンポをおったて 子を作り 死ぬ… 人生は空っぽだ 昔も今も 未来も ずっと 俺がいなくても 空っぽのまま続いていく」
「人も動物と同じ 愛玩し 死んだら埋める」
もう少し考えてみよう。〝個〟のための映画とは何だろう?
それは決して嘘をつかない男の物語りだ。
無論、嘘をつかなければ、我々の社会に生きる場所は無い。
嘘をつかないということはまた、希望という〝幻想〟を持たないことでもある。
嘘をつかないことも幻想を持たないことも、曲がりなりにも良識ある人間には不可能なことだから、観客は映画の中で、もう一つの類い希な人生を生きることになる。
それこそ、〝個〟の闘争という弾丸のような人生だ。
そう、薬室から吐き出される一個のブレット(弾丸)こそ、主人公の〝個〟の象徴であり、社会性という〝融和〟の取りつく島のない最たるものである。
肉屋は、前作の肉切り包丁で、社会から自己を庇護する繭を切り裂き、ついに一個の弾丸となった。
「よし つまらん人生に もう1章つけ加えよう 〝毒蜘蛛の巣からどうやって逃げ出したか〟」
言うまでもなく、〝個〟の論理を貫き通すことは、この世界の秩序に背くことである。
だからこそ、映画の冒頭に「この映画はすべてのモラルに戦いを挑んだ」という物騒な文句が踊ることになる。
つまり、この映画の真の闘争、〝モラルへの挑戦〟とは、決して、悪辣なフィクションを構築することではなく、一切の嘘や約束事を排し、ただ、〝個〟のリアリティーに肉薄することなのであった。
「他人でなく 自分の欲望が叶えられたなら」
ところで、先にも引用したミヒャエル・ハネケ監督の発言の中で、自作のドラマツルギーに触れた、こんな興味深い言葉があった。
「心理的リアリズムに拘泥すると、いかに極端な状況を設定し、いかに難問を提出してみても、たちまち矛先が鈍ってしまいます。そこに生じる出来事は登場人物の性格に起因する、したがって自分自身とは関係ないと観客は考え、逃げ出すことができてしまうからです。逃げ出すのが不可能になる形式を見つけ出そうと、私は試みているのです。状況をラディカルに尖鋭化させて、心理的個人的な鋳型を避けることで、観客自身を不安と攻撃の真っ只中に投げ込むことのできる形式を探し求めているのです。観客は空白を自分で埋めなくてはなりません。自分で責任を引き受けなければならないのです。」
(第23回 ぴあフィルムフェスティバル 「知られざる世界の巨匠 ミヒャエル・ハネケ」より)
確かにこの発言は、徹底的にヒロイズムを排し、主観性を解体する、ミヒャエル・ハネケのスタイルを言い得ている。
そういう意味では、ギャスパー・ノエの『カノン』は、全編モノローグの〝心理的リアリズムに拘泥〟している点、この対極にあるわけだが、しかしむしろ、『カノン』の凶暴さとは、この一見、無気味な内面に共感させてしまう力技にあるわけで、またそれは、人間の暗部としての〝個〟の真相を全く巧妙に暴露している所以でもある。
ハネケの指摘のように、『カノン』という物語りは、〝主人公の性格に起因する点〟が大いにあり得る。しかし、真に無気味なのは、このグロテスクな内省が、実は誰しもの深層部分で、決して遠くのものではないと感じさせる点ではないか。
さて、最後になるが、少し『カノン』の、映画としての風合いについても触れておこう。
『カルネ』、『カノン』の連作について、最も特徴的なのは、何といっても、あの、ゴダールに対するオマージュとも言える映画手法である。
文字タイトルのインサートの仕方、ドキュメンタリー調の編集、自然光を基調とした16ミリの粒子っぽい撮影。あの、赤被りの画面の、すえたような空虚感こそ、何より劇中に流れる忌々しい時の淀みを語り切っている。
ベッド上の肉屋の視点、垢じみた天井が映る。彩度を失った人気のない街の実景。金の無心を断る人々の、抜きの構図の素晴らしさ。
基より見るべきものの無い風景が、何より見るべきものへと変質する時、「映画」は、始めて〝記憶〟へと昇華するのである。
ギャスパー・ノエの作品を通じて、僕は改めて、ありのままの光を映画史に取り込んだヌーベルバーグの威光を見た思いである。
そういう意味では、ギャスパー・ノエとは、数少ない、本家の聖杯を授かる者、と考えて良いのではないだろうか。
因みに、ギャスパー・ノエ以外で言えば、僕はかつて『ありふれた事件』を観た時、これは僕らの時代の『勝手にしやがれ』だ!と思ったものだが、だとするならば、さながら『カノン』は、ルイ・マルの『鬼火』といったところか…。
「ついに生きてく意味を見つけた お前を守る そして誰よりも幸せにしてやる お前は俺の娘だ 俺が女にしてやる 」
それにしても『カノン』という映画。これは生きることの欺瞞と誠実さをめぐる、余りに儚く狂おしいレクイエム(鎮魂歌)であった。
人生に、希望という夢を灯すことにうんざりしたら、迷わずこれを観ればいいのである。