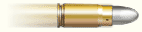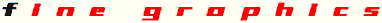Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
ロングテールズFILE;vol.7
映画 『DEAD MAN』 (1995年公開)
〝幸せ〟なんかに憧れるより、ロマンチックな人生のほうを選んでみたい。
〝楽しい仲間達〟と孤独を揉み消し合うより、エレガントな哀しみに身を浸していたい。
根底にそんな願望がなければ、もとより、誰も映画など見る筈もあるまい。
言わずもがな、劇場の暗闇の中では、誰しもが独りなのである。
〈絶対安全な場所〉から眺める、身を切られるような絶望。不安。慟哭。浄化。
「映画は人生だ」という言葉があるけれど、勿論、映画は人生そのものではない。ただ、人生の原典となり得る何ものか、であり、泡沫(うたかた)のメタファーなのであった。
「死人とは旅をせぬほうがよい
アンリ・ミショー」
そんな献辞と共に導入される映画『DEAD MAN』は、実に「映画」という他ない、映画そのものといった風合いの映画である。
アメリカの西部開拓時代、〝終点の町〟「マシーン」に、ただ、職を求めてやって来た平凡な男が、小さな現実の酷薄さや、思わぬ手違い、何よりその朴訥なまでの不運さから、死の荒野をさすらう〝デッド・マン〟(死を運ぶ者)へと仕立て上げられる、という物語りである。
この映画を考える時、実はとても重要なのが、この〝仕立て上げられた〟という点であろう。
何故なら、彼はどのような岐路に於いても「デッド・マン」という人生を〝選択〟などしていない。
選択したのは彼ではなく、〝人生〟の方である。
人生が彼を選び、彼を「デッド・マン」へと仕立てたのだ。
このことは作品全編に、印象的に映し出される彼の眼差しが最も物語っている。
『地獄の黙示録』に於いて、ウイラード大尉が、「恐怖だ.地獄の恐怖だ」と呻くあの眼差しにも似て、主人公〝ウイリアム・ブレイク〟は何ものも「選択」することなく、ただ、自らの〝血で詩を描き出す旅〟を見つめ続けたのである。
めまぐるしい程に流れる「旅」の風景に反して、この定点を守り続ける〝眼差し〟の不思議さは、冒頭、「終点の町」までの先導役である機関士によって「(列車の)窓の風景は舟に乗っているようだ.不思議だと思わないか?水は流れ続けるのに、舟は静止している」という言葉で言及されている。
勿論、この台詞が直接、掛かっているのは、ラストシーン、主人公が〝空と海の接する場所〟に流され、静かに見上げるあの空のことであり、あたかも流れ続けながら、実は決して免れることのない自らの〝視線〟(私という箱もの)というメタファーもまた、その大きな我々を取り巻く〝宿命〟(空)によって逆照射される。
さて、この映画の中で主人公を、あの、からからに乾いた死の彼岸から、真の死地へと橋渡しする役割を、例の奇妙なインディアンが担うことになる。
これについて以前、僕はある知人と雑談した時、彼はすぐに映画の問題からインディアンの民族文化へと話題をそらしていったけれど、しかし僕はこの物語りに限っては、あのインディアン出身の男の背後に殊更、民族性を強調するのは、むしろ作品独特のパラドックスであって(その証拠に、彼は自ら「ノーボディ(誰でもない人)」と名乗っている通り)、〝誰でもない〟という、そのことこそが、実はこの作品の性格を最も顕著に著していると考えている。
つまり、この映画の中では、誰もが「ノーボディ(誰でもない人)」なのであり、シンボライズされた表象そのものなのである。
『DEAD MAN』のこうした世界観の在り方は、ジム・ジャームッシュの作品群の中にあっても特筆すべき点だと思う。
勿論、この作品においても、例えば〝ペリシテ人や異教徒〟のくだりのように、アメリカ社会が抱える多民族間のドタバタ、いわばジャームッシュお得意の風刺的アイロニーは健在であり、加えて、銃社会やアメリカン・バイオレンスの成り立ちを活写するという意味でも意義は大きい(いや、このリアリティは映画史の中でも傑出していて、もはやこれは「西部劇」の系統というより、実際の西部開拓史の忠実な再現を目指したもののようにさえ見える)。
『DEAD MAN』はこの意味でも全く素晴らしいのだが、しかし、こうしたこと以上に、僕がこの作品の一番のポイントと考えるのは、やはり、物語りの大半の舞台が、この世の辺境の地、正しく死の彼岸、〝何処でもない場所〟に於いて展開されるという点だと思う。
だからここでは、いつものような人種間のいざこざさえ、どこか〝遠い現世の記憶〟にまつわるもののような風合いがあるし、そもそも、インディアンの「ノーボディ」にしても、部族間の混血であったことから人間社会をドロップ・アウトし、土地を離れ、放浪しているという設定である。
文字通り、彼等は皆、荒野を彷徨う亡霊なのであって、「誰でもない人」〝デッド・マン〟に他ならないわけだ。そしてそのことこそが、この映画に俗な肉感性を削ぎ落とし、極めてシンプルな魂の葛藤を浮き彫りにしているのである。
ところで、僕はこの映画を〝「映画」という他ない、映画そのもの〟と書いたけれど、おおよそ、ジム・ジャームッシュという、この世の最も信頼に足る映画監督の(勿論、一本たりとも不発のない)全ての作品に触れる時、使い古された言葉だが、やはり「映画的」なものの〝実在〟を確信してしまうのである。
結局、僕などの渇望は、これら〝「映画的」空間〟の至福に一刻も長く、深く、身を浸していたい、ということだけなのである。
勿論、映画はシノプシスにイメージの肉付けをしただけのものではない。シナリオに映像や効果音を加えただけのものではない。逆に何れかのエッセンスのみを抽出して映画本体を論じることも不可能である。
映画は「映画」そのものの中にしか無く、その極上のものは「映画的」な瞬間の中にしか存在しない。
どんな評論も、如何なる解説も、例えどんなに「映画的」なものの周囲を〝文化的視点〟に立って読み解こうとしたところで、決して「映画」そのものに肉薄したり、再現したり、語ったこと、にすらならないのである。
そうして考えてみると、結局、僕らに可能なことがあるとすればそれは、映画を通して自分自身を語ること、つまり、これだけなのであろう。
要するに、ジム・ジャームッシュの作品世界とはいつもそんな、「映画」というものの本質に至らせるべき、〝絶対不可侵〟の孤高性を獲得しているということなのだ。
ともあれ、僕にとってこの『DEAD MAN』もまた、掛け値なしに〝人生の原典となり得る何ものか、であり、泡沫(うたかた)のメタファー〟なのであった。