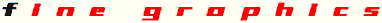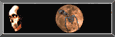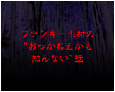Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
ロングテールズFILE;小休止
ぼくは怖い話が好き
ぼくは怖い話が好きだ。
ひと口に怖い話と言ってもいろいろとあって、その最たるものは借金と病気と大事なひとの死にまつわる話、ということになるだろう。
しかしぼくがここで言いたいのは、そういう類いのリアルな絶望に関する話題ではなく、もっと軽妙な、どうでもいい恐怖についての話だ。
そう、例のアレである。怪談。
今更、いい歳をして「怪談」でもなかろうとも思うのだが、しかし何と言うか、どうも好きである。ああいったフォーマットの小咄が。
しかもぼくはご多分に漏れず、幽霊話以外は怪談にあらず、と思い込んでいる節がある。
しかし妙なのは、ぼくが件の「心霊」なるものを理性では到底、信じることができない点である。
当然、「あの世」などは夢にも無いものと考えている。
例えばぼくはかつて父親が亡くなった時、親威の信心深い家庭に父親らしい幽霊が出た、と聞かされた時は、それならば他人の知らない父親に関する100の質問を用意するから本人に訊ねて一つ残らず正解してみろ、などと口走ったし、また他方では、テレビや新聞、出版業界の、金儲けのためなら如何なる作り事であれ、それこそ一抹の呵責も無く出し物にしてしまう、人間本来の商魂体質をいよいよ痛感させられる今日この頃である。
しかし、それでもぼくという奴は、良くできた「怖い話」には敬意をもって恐がり、できれば知人に吹聴したい衝動さえ持ち合わせている。
これはどうしたことだろう?
あるひとにとっては、これは、充二分に自己矛盾と感じるかもしれない。
いや、事実、疑うべくも無く、これはやっぱりすっとぼけた習性である。
まあ、とは言え、ぼくなりに弁明させてもらえれば、ぼくが求めて止まないのは、現象としての幽霊やオカルティズムそのものではなく、あくまで怖い「話」の方なのである。
霊の仕業かどうかは知らないが、ぼくがかつて体験した、断じて作り話ではない「怪談」風の出来事〝その1〟
ぼくは非日常的な不思議な体験をしたことも、したと思ったことも殆ど無いのだけれど、しかし人生に三度だけ、どうも理屈では解釈し難い出来事に出会ったことならある。
これからそのあらましを記していこうと思うが、但し、これらはことさら「怪談」というわけではない。
何故ならそれは「怪談」によく似たプロットを持ってはいるが、だからこそ奇妙に感じた出来事であり、実際にはぼくの小さな実体験に過ぎないと思っている。
しかし、面白いのは、人生に唯一、三度だけの体験が、ある時期、具体的には10年間程の間に度重なっている点である。
昔、あれはぼくがちょうど予備校生の頃だったと思う。
ぼくは東京郊外に両親と暮らしていたが、或る時、家を手放さなければならない事情が生まれて、さらに郊外、東京のはずれのH市に家族で引っ越すこととなった。
急な斜面を切り崩して造成された、幾重にも連なる住宅街の丁度てっぺんに位置するその新居は、棕櫚(シュロ)の木の有る、明るい二階屋であった。
できるだけ引越し費用を切り詰めるため、父親と二人、自家用車で荷物を運び込んでいたぼくは、その何度目かにひとりで新居に留守番することとなった。
夕暮れが迫る時間、ぼくはその解放的な造りの新居を楽しんでいた。
全ての荷物が運び込まれれば、またあの雑然とした無味乾燥な日常が始まるはずだ。
その新居は以前に人が暮らしていた中古物件ではあったが、売りに出される時点で見事にリフォームされ、生活臭らしいものはことごとく抹消されていた。
やがて日が暮れ、ことのほか居室数をたたえた新居は、ぼくのいる二階部屋にこうこうと灯りが燈る以外、しんと静まり返って、物音一つ立ててはいない。
当然といえば当然だけれど、初めて過ごす宵闇に沈む家は、日中のあのおおらかな佇まいとはまた別の、一種、威圧感にも似た湿った静けさを孕んで瞑目していた。
ぼくは雑誌か何か読んでいたのだと思う。
初めは微かな風の吹き込むような、音だと思った。
上の方から聴こえてくる。
上というのは、部屋を出た廊下の脇から登れるようになっている収納式の屋根裏部屋(納戸)のことだ。
何の音だろう?と聞き耳を立てたり、幻聴を疑ってみたりするような、何とも微妙な音だった。
隙間風の音か、紛れ込んだ鳥か何かの羽ばたきか、隣屋のテレビが反響する音か、いずれにしろ、不思議と特定し難い音に思われた。
もっともぼくはそれをさほど気にしていたわけではない。
言わずもがな、この家のことは何も知らないわけだから、例え構造上の欠陥か何かあったとしても不思議はないのである。
初めのうちはそんな風に、気味悪いというような感覚さえ憶えなかった。
しかし、さすがにこれはおかしいと思い始めたのは、〝音〟が徐々に変化しているようであり、しかも、人が唸されるような声に聴こえ始めた頃だった。
ここまで、おそらく、一時間以上は聴こえ続けていると思う。
当初は屋根裏部屋からと思えた音の発生源は、今度は、ぼくの部屋と一部屋挟んだ、ちょうど斜向いの一室から発しているように思われだした。
ここに至って、ぼくは初めて妙な気持ちになってきた。
人間心理かもしれないが、一度それを人の〝声〟に見立ててしまうと、どうもそれを元の〝物音〟まで降格させ辛くなってしまう。
ぼくの脳裏に一瞬、誰もいない部屋の暗闇がよぎった。
〝声〟のトーンは明らかに上がってきている。
当時、ぼくは既に幽霊など信じていなかったが、それにしてもこれほど明白に、説明の付かない現象に出会うと、実際には恐ろしさというより、狐につままれたような呆れた感情に囚われ、尚も、ことの真相を推理しようとしだすものである。
怖さより、解明できないことの気持ち悪さが後を引く。
しかし、そんなぼくでさえ、とうとう不気味さと同時に、現実問題、何とかしなければ、という気持ちにさせられる局面に至った。
声がはっきり隣の部屋から聞こえ始めたのである。
声音は遠くなり、かと思うと近くなり、得体の知れない脈動を繰り返している。
殊に、近い時はもうかなりのやかましさで、とても〝気のせい〟などというレベルのものではない。
それはもはや、病人(年配の男性?)がベッドで激しく唸される架空の状況をはっきり残像として焼き付けるまでになっていた。
わずか壁一枚挟んで…。
ぼくは、やれやれと立ち上がった。
この調子ではもう真剣に建物の欠陥か、最悪の場合い、誰かが侵入していることさえ疑わなければなるまい。
ぼくは密かな緊張の後、静かに自室のドアを開けた。
暗い廊下に出ると、隣室のドアノブに手を掛けた。
そして一息にそれを開けた。
音など影も形もなかった。
そこにはただ、重苦しい程の漆黒の闇が滞留しているだけであった。
瞬間、ぼくは小さな混乱に陥ったけれど、ともあれ、仕方なしに自室に引き返すと、もう詮索するのはやめて、それからはヘッドホンでできるだけ勇ましい曲を聴いて過ごした。
まさか家を離れて、不慣れな住宅街で時間を潰す場所も無かったのである。
それからどれ位の時間が経っただろう、車庫の方で聞き慣れた車の排気音が鳴り始めた。
同じ〝音〟でも人を不安にさせるものもあれば、この上なく安心させるものもある。
父親が部屋に入って来て、ぼくらは二、三言葉を交わした。
ぼくはそのほんの少しの会話だけで現実に引き戻された。
今迄の数時間に渡る奇妙な体験さえ、とても些細なことに思われ、少し話すのを躊躇した。
あまり幸先の良さそうな話しでもないのである。
ぼくはそしらぬ顔で、もう一度、聞き耳を立ててみた…と、その瞬間である。
この時こそ、ぼくは初めて、そして心底ゾっとしたのだった。
音が無い。そんなものはどんなに耳を凝らしてみても跡形も無かった。
これにはさすがに、理性も揺らぐ思いだった。
説明がつかない。
ぼくは確かに自家用車の排気音が聞こえる少し前にもその音、いや、〝声〟を聞いている。やはり気になったのと、物理的な現象だとしても、家族に報告しなければ、という思いから、時々、ヘッドホンを外して耳を凝らしていたのである。
家族が戻って来るのとほぼ同時に音が掻き消える、そんな反響音とは一体、どんな原理だろう?
では、可能性としてはやはり幻聴なのだろうか?
しかしそれならばぼく一人の不安心理による心の作用ということになる。少なくとも全く同じ音はぼくにしか聴こえないと考えた方が自然である。
しかし、実はこの音を聴いたのはこれ一度きりではない。
もう一度だけある。
しかも、その時は、両親も一緒に、はっきり聴いている。
実は二度目の時も、何と言うか、実にいわく言い難い〝タイミング〟であった。
この年の大晦日、夜の11時半頃、つまり、年明けまであと三、四十分という時刻だったと思う。
ぼくの部屋隣の、例の「声」が最終的に聞こえてきたと思しき部屋はその頃、両親が寝室兼事務室のように使っていた。
その時、ぼくらはこの部屋に集まって、その後の将来の、正直、あまりかんばしくない話題について話し合っていた。
するとかつてのあの「声」とそっくり同じものが聴こえてきたのである。
忘れもしない、誰かが低く身悶えるような、吹きすさぶようなあの声。
ぼくは無論、両親にかつての体験のことは話していたから、これがあの時のものだ、と話して聞かせた。
両親も名状し難い、という表情で聞き耳を立てていた。
特に、父はそれが何か良からぬ前兆にでも聞こえたのか、ベッドにふて寝しながら聴いていたが、「関係ない」とだけ言った。
この時もぼくが本当に肝を冷やしたのは、今度は年が明けた瞬間(!)何事も無かったかのように音が掻き消えた点である。
繰り返すようだが、年の瀬が迫る頃鳴り始め、年が明けた瞬間、掻き消える反響音とは果たしてどんな原理であろう?
しかも、今回ばかりは皆が聴いている。
幻聴ならば〝集団幻聴〟ということになるが、しかし以前、一人が聴いたものと同一(同種)のものを、後に複数が聴いた〝つもり〟になるというのは些か複雑である。
ならばもう一つだけ、一般的には最も可能性の高い仮説がある。
それは、何のことはない、この話がぼくの創作であるという可能性だ。
しかし、こればかりは証明のしようがないので、何とも言い難いが、しかしぼく自身は本当に体験した〝つもり〟になっていることだけは一応、訴えておこう。
因みに、この出来事にはあたかも紋切り型の怪談話しを彷彿とさせる後日談が存在する。
いよいよ作り話しのようだが、しかしぼくの中ではだからこそ呆れた、正真正銘の体験談なのである。
これはぼくが最初に「声」を聴いた後、母親から聞かされた話だが、両親が不動産業者に連れられてこの新居を初めて訪れた時、以前、住んでいた家族がいた。
ちょうど、業者に屋根裏の納戸を紹介された時、その家の子供が、「幽霊が出るよ」と言ったという。
その時は、小さな子供が狭い屋根裏部屋を恐れるのは当然だから、気にも止めなかったらしいが、その後、母親が近所の事情通の主婦たちに聞かされたところによると、この家は元々、先住者の親が愛着を持って建てたものだったが、家が完成して間もなく、まず老主人が亡くなり、また、その後を追うように奥さんも亡くなられたのだそうだ。
その後は少しの間、息子夫婦がこの家に住まったが、しかし幾らもせず、何故か、ぼくの両親に売ってしまったということだった。
だから主婦たちはしきりと先代の老夫婦を気の毒がっていたという。
また、この他にも、この家にまつわる「霊感」じみた話し、つまり、この家は〝マズイ〟ですね的な話しを二、三聞かされたことはあったが、しかしこういうのはあくまで個々の感性の問題だから、ことさら、ここに挙げるようなことでもないと思う。
結局、この家には10年間住んだが、ぼくにとっては予備校時代、大学時代、社会人になってからの数年間を過ごした家だけに、素晴らしいこともそれなりにあったが、ぼくの両親にとっては、特に、この家を手放す顛末は散々なものであった。
実は家を手放す時、ぼくらの前に住んでいたあの家族が、もう一度、家を取り戻したいと名乗りを上げたが、結局、思いの他、負債があったことから、用立てるべき融資を受けられず、断念したということだった。
上田秋成に泉鏡花にラフカディオ・ハーンにエドガー・アラン・ポーに阿刀田高に稲川淳二。
おどろな民間伝承を民俗学的に蒐集した柳田國男や〝本職〟ではないけれど遠藤周作が怪談集を上梓したり、太宰治が自作の小編中に怪談めいた逸話を披露していたり…。
それにしても、怪談とは何だろう?
高度に文学的なものから、むしろ文学というよりは話芸の一種まで、実に幅広く存在する。
しかし、各々の事情を棚上げすれば「怪談」とは少なくとも、<恐怖>というカタルシスを喚起する目的に絞った寓話のスタイルではある。
もっと具体的に言えば、聞き手の恐怖や不安のツボを探り合い、帰するところ、その<怖いシチュエーション>を競い合う、一種の遊びなのだ。
もっとも、考えてみればこれは、文学という「遊び」そのもののことでもある。
想像力と表現上の技巧を凝らして迫真の「場面」を想定し、且つ巧みに編み込まれた状況設定の罠が、受け手を<恐怖>というカタルシスへと誘う機能となる。
言ってみれば「怪談」とは「恐れ」という人間の、いや動物の、最も根源的な感情(防御本能!)に訴える箱庭文学なのであろう。
その証拠にぼくは上質な文学や表現ほど、どこか根源的な「怖さ」を内包しているものだと信じている。
ところで「怪談」というものを考える場合、どうしても物議の対象となるのは、その「恐怖」の質に対する各々の指向性の問題である。
そもそも何を最善の恐怖とするか?
こればかりは見事に千差万別であって、誰しも、知人と幽霊談義のひとつもやってみれば自明のこととなる。
それはあたかも「味覚 」を思わせる程の多様な個人差であるから、実際、どれがナンバー・ワンの怪談か?というのも実に決め辛いのが通例である。
だから逆に、一般論は避け、できるだけパーソナルに話を進めなければならないわけだが、例えばぼくにとっての「最も怖い物語の形式」というものもやはり存在する。
仮にその条件を整理してみると、次のような要素を満たしているもののようである。
1.デテールのリアリティ…
怪談においては肝心の恐怖描写のみならず、そこに至るまでの人生スケッチ(日常描写)がとても重要な〝奥行き〟のファクターとなる。
実は、この部分の巧妙さが物語りそのもののリアリティを約束し、全体を貫く一種の詩情となる点、本式の文学であっても同様である。
2.〝見せ場〟の斬新さ(意外性)、合理的発想からの飛躍…
怪談とは本来、超現実的な展開を宿命付けられる物語りなだけに、やはり見せ場の斬新さ、意表を突いた恐怖のアイデアが何より絶対命題となるところは言うまでもないが、ぼくが意識的に見分けたいのは、このアイデアの発生源が如何に合理的な意味の範疇を脱しているか?いわば作者の<狂気>を内包しているか、という点である。
やはりこれもあらゆる表現において同等に言えることだが、骨の随まで意味と理性に全うされた虚構には、決して我々の日常というものの嘘と詭弁の表皮を暴く力など持ち得ないし、したがって新しく自由な視点を獲得することも無いからである。
別の観点から言えば、もし本当に超現実的な出来事が起こったとすれば、それはきっと、人々の人智を超えた方法でやって来る、と考えた方が生々しさがある。
無論、〝人智を超える〟のだから、書き手がこれに対応する方法としては、自ずと<狂気>しかないのである。
3「落ち」や辻褄合わせを含めて、できるだけ説明的でないこと…
ある頃から頻繁に使われ始めた典型的なパターンに、例の「…後で調べて見たら…」というのがある。
これは説明のつかない怪異な現象の後に、大抵、紋切り型の因果律を用いて、物語りの「落ち」とする手法で、言い方を替えれば、理解を超えた不可解な出来事に、一見、合理的な根拠付けを与えることで、一つの教訓話(理性的な秩序)に仕立てようという趣向である。
実はぼくは昨今のこうした方法の濫用が非常に興醒めである。
いやしくも、怪談というものの導く先が恐怖や不安の手触りを楽しむためのエンターテイメントであるならば、〝最後まで解らないこと〟の方が受け手に漠とした不安を惹起させるのではないだろうか?
少なくとも怪談やオカルトや超現実的な逸話を楽しもうとする心理には、元々、意味や説明や根拠ばかりの合理的な世界から、一刻、解き放たれたいという大前提が秘められている。だから、行き過ぎた辻褄合わせや、説明的な「落ち」の類いは、とかく、あの凶々しさと恐怖に彩られた不可思議の世界を矮小化された、凡庸なものにするだけである。
だいいち、実話風に語られることが当世、怪談の真骨頂だとすれば、その真実味においても、「後で調べて見る…」ことなどまずできるわけもない。
実際には他愛のない個人的不思議体験の裏を、一体、どのような筋に、如何なる取材、聞き込みを行ったというのだろう?
4.忌まわしさ、悪意の潜在…
ぼくは怪談を、いわゆる「ホラー」というものの延長と考えたくはないのだけれど、ただ、どちらも共通するのは、ピリッとスパイシーな味付けであるということだ。
さながら怪談は、刺激的な香辛料を効かせた、一品料理といったところか。
スパイスの原料は勿論、「忌まわしさ」と「悪意」のブレンドである。
一口にスパイスと言っても、その効かせ方は料理人の腕の見せ処のようで、ぼくの好みは、例えば、一見、客をある筋書きの方へ導いておいて、一転して裏切るその刹那、黒い凶々しさのスパイスが光るような、そんな味わいである。
更にもうひとつ付け加えるならば、印象的な恐怖譚には「悪意」や「忌まわしさ」に加えて、これらの向こう側に第三の味覚、「卑屈さ」という辛酸なスパイスが一役買っていることがある。
「卑屈さ」とは魔性のものの不気味が極まって、ある種「滑稽」、つまり、笑いに転嫁される瀬戸際の状態のことだ。
例え魔界に迷った者という想定のもとであっても、人型のものの威厳や尊厳が著しく崩壊してゆく様は、受け手にとってショッキングなものである。
ところで、冒頭でも触れたが、ぼくは怪談というとどうしたって幽霊ものが王道だと思っている。
しかしながら近頃は、都市伝説風とか何だとかいう病的な犯罪者ものの「怪談」なども存在するのはご存知だろう。
正直、ぼくは、どうもああいった類いのものは得意ではない。
なぜなら、行動に異常をきたした生身の人間を題材にするなら、週刊誌の生臭い犯罪記事と本質的に変わらないからで、また、その種の出来事を、実際には真偽のわからぬ匿名性で語ることにも、いまいちモチベーションがない。
更に言えば、品格の問題。
本来、怪談の愉しみとは、誰はばかることなく興味本位で無邪気に楽しめる噂話の範疇であり、憩いの文学でなければならないのだ。
そういう意味では何処の誰ともつかぬ「幽霊」なる存在にご活躍願うのが一番ではないだろうか。
霊の仕業かどうかは知らないが、ぼくがかつて体験した、断じて作り話ではない「怪談」風の出来事〝その2〟
ぼくが通った大学は美大で、今は移転したけれど、当時は西東京の外れに位置した。
具体的に言うと、ちょうど高尾山の手前辺りである。
実はここには非常に有名な、いわゆる〝心霊スポット〟というのがあって、その名も「八王子城址」という。
つまり、ぼくの母校とは、実にふざけたことに、当時、この関東屈指(?)の霊場のすぐ脇に存在していた訳だ。
「八王子城址」というからには無論、そこに昔、「八王子城」というお城があったわけで、かつてこのお
城が攻め落とされる際、戦国の世にあってさえ比類無いほど凄惨な攻防が演じられたという。
事実、ここは歴史的に、北条氏が滅亡するきっかけになった地なのである。
「時は天正十八年六月二十三日申の刻(午後四時)、寄せ手が思いもよらぬ地獄の口を開けた八王子城は、今ここにようやく陥落を迎えた。
…中略…
終わった、ようやく終わった。総大将前田利家はそう思った。しかしそれは慶賀すべき大勝利と言えるような、そんな類いのものではなかった。あまりにも凄まじい犠牲と、これに関わったあらゆる人々の心に癒やし難く刻み込まれた地獄絵図の末に現出した壮大かつ荘厳な「時の終わり」、そして「永遠の停止」であった。とてももうこの城に再び人の営みが蘇えるとは思われなかった。」(川村掃部 著 『八王子城滅亡 天正十八年六月二十三日』より)
そんなわけでここが今でも、肝だめしフリークの間では、ちょっとした人気スポットになっているというのだ。
さて、確かあれはぼくが大学二年か三年の頃だったと思う。
ある日、ぼくは自宅でテレビを見ていた。
しょうもない内容の番組である。
その頃は、夏になると「心霊特番」みたいなものがしょっちゅう放送されていて、まだ、とても素朴なオカルト・ブームの只中であった。
この時、ぼくが見ていたものも、そんな種類の一本に違いない。
さほど真剣に見るともなく、ほとんど流しっぱなしにしていたぼくは、しかし番組のある箇所で思いがけなく、テレビに目を止めた。
あ、学校だ…。
鬱蒼とした木々を背景に、大学のすぐ脇を流れる小川が映っている。
そしてそこには小さな滝があり、そしてそして、つのだじろうが…。
つのだじろう??
「この滝はその昔、八王子城が落城した折、大奥など女子供が身を投げたと伝えられておるわけです。ではここでポラロイドなぞ撮ってみましょう.おおっ? 真っ黒で何も映らない!ではもう一枚.おやっ?今度は変な発光体がぁっ!!」
などというようなことをやっている。
正直、お前が変な発光体(←額)じゃあっ!!と突っ込みたいような番組ではあったが、しかし、ぼくは、へえ?、うちの大学近辺も結構、有名じゃん!と変な感心をしたものだった。
その次の日か、少なくとも二、三日後、大学で写真の授業があった。
確か撮影実習の初日か、二回目の授業だったことを憶えている。
その日は、大判のブローニーカメラを使って、大学の庭などで、お互いのポートレートを撮り合うという内容だった。
この日、使用するのはフイルムではなく、ポラロイドである。
そこで、ふと、ぼくはあのテレビ番組のことを思い出した。
ぼくは元来、悪戯好きである。
当然、写真科の親しい友人に、このポラであの滝へ行って、本当に心霊写真が撮れるかどうか確かめてみようぜ、と提案した。
つまり、それくらい、あの「心霊特番」がインチキ臭かったということでもある。
友人はただかったるいのか、ひょっとすると少しばかり気味が悪かったのか、とにかく何も答えなかった。
まあ、結局のところそんな物好きを働いている暇もなく、ぼくらは四人一組くらいのグループに別れて、各々気ままに実習を始めたのだった。
日差しの強い快晴の午後、ポラロイド付きブローニー・カメラを三脚にセットし、お互いのバストショットを撮影し合う。
光は充分だ。これなら思いっきり絞り込める。
ぼくは最初のシャッターを切った。
デジカメのお陰で、今はもう懐かしい歴史の遺物になってしまったが、撮影したてのポラロイド・フイルムを、現像液が万遍なく回り込むようによく振って、べりっと剥がす時のあの期待感は、中々良いものであった。
関係無いけど、ぼくはヘルムト・ニュートンの『ポラ・ウーマン』という写真集がお気に入りだったっけ。
ん?何だこれ…。
ポラロイドは元々、像を結ぶ迄に少しの時を要する。
しかしそれにしてもこれはおかしい。
もう出るべきものは出切ってしまった筈なのに、依然、真っ黒のままだ。
ぼくは仕方なしに二枚、三枚と撮影してみた。
やっぱり同じだ。真っ黒のままである。
カメラを調べてみてもさっぱりわからない。
どういうことだ?
結局、ぼくらは校内に散らばっている別のグループに助けを求めることにした。
ぼくらから大分離れたところで撮影していたチームに挨拶がてら、上手く撮れているかい?と尋ねたところ、素っ気なく、撮れない、という。
撮れない?
不思議なことに、彼等も状況は同じだった。
しかしぼくらは別々のブローニーカメラで、かなり離れた場所で撮影していたのである。操作上のミスなど無いかとそれぞれ確認もしている。
正直、ぼくはこの辺りのデテールははっきり憶えていないが、確か、更に別のグループにも尋ねてみたが、答えは同じだった気がする。
妙だな…。
もっとも、こんなことで学生達は真剣に悩んだりしない。
とは言え、全く原因が解らないというのも寝覚めが悪い。
ぼくはやむなく、写真科の友人に知恵を借りることにした。
ぼくは彼に、こう切り出した。
「おそらく大学が仕入れたフイルムが不良品なんじゃないかな?」
だが、意外なことに、彼はぼくのこの推測を真っ向から否定した。
絶対にそんなことはないという。出荷されたフイルムが何本も同時に不良だなどということはあり得ないというのだ。
しかし、あり得ないと言うけれど、じゃあ何故、映らないのか?と尋ねると、そんなことは知らないと言う。
ぼくらは軽い口論となった。
ならば、と友人は提案した。そんなことがあるかどうか、写真科の教授に聞いてくると言うのだ。
さて、教授の回答はこうだった。
まず、フイルムが出荷時から感光しない不良だなどということは前例が無く、考えられない。また、大学によるフイルムの保管方法に関しても、常に冷蔵庫の中で管理しているので、完璧な筈、と。
ふうん。やっぱり、友人の言った通りか…。
結局、何の手掛かりも得られず、撮影を続けている仲間のところへ戻ってみると、正直、拍子抜けした。
何のことはない、映り出したという。
〝映り出した〟?
しかし、これが更に奇妙なことに、撮影枚数を重ねるごとに、徐々に、薄っすら、像を結び始めたのである。
しかも友人の言ではないが、〝あり得ない〟ことに、別のグループでも全く同じように…。
無論、最後まで原因は解らなかった。
まったく、狐につままれたような出来事であった。
そして、帰り道、ぼくはバイクを走らせながら、フルフェイス・ヘルメットの中で、電気に打たれたように独りごちた。
…あっ…!…つ・の・だ・じ・ろ・う…。
ところで、先述した通り、ぼくは死後の世界や霊というものを基本的に信じてはいない。
実際、霊やその他のオカルティズムに対する懐疑的な根拠を挙げれば枚挙に暇がない。
しかし、そういうことの以前に、実は、ぼくには、信じるわけにはいかない、そもそもの前提が存在しているとも思っている。
その前提とは他でもなく、ぼくが無神論者であるということだ。
いや、その言い方は少々正確さに欠ける。
と、言うのも…。
今日のぼくのような人間に限らず、戦後、多くの日本人は信仰を失った。
逆に戦時下までの日本は、国家宗教としての日本神道を始め、仏教、儒教、キリスト教の影響入り乱れる巨大な宗教国家であった。
その頃、日本人はとても信仰心の篤い国民性で、いわゆる封建主義の頂点に神を頂く謙譲の精神が徹底されていた。
しかし敗戦を契機に、アメリカの占領政策のもと、それ迄の価値を大転換することを迫られたのである。
またその際、かつて未曾有の被害を出した日中戦争、太平洋戦争の精神的支柱が他でもなく、国家宗教である日本神道であったこと、このせいで日本国民自身、精神主義や唯心論的世界観の不毛を痛感させられることとなる。
ざっと概論すれば、これが今日、我々が宗教というものに本能的な懐疑心を差し挟むようになったそもそものルーツではなかっただろうか?
さて、だとするならば、戦後以降、日本人とは何一つ精神的よすがのないままやってきたのだろうか?
また、あらゆる意味での信仰心は失われてしまったのだろうか…?
ここからはぼくの持論を語らせて頂こう。
いや、決してそうではない。
何故なら、あらゆる民族には常に、神と崇める概念が存在するではないか。
では、今日の日本人が既存の宗教に代わって民族の中心に頂く絶対的価値とは果たして何だろう?
ぼくの思うに、それは〝科学〟である。
今日の日本人は「科学」の信奉者になったのだ。
YMOの曲に『シチズンズ・ オブ ・サイエンス』(科学の市民)というのがあったけど、当世の日本人は唯一絶対の価値尺度を「科学的かどうか」ということにおいているのである。
だから〝それは科学的に立証された!〟などと云われると、深く洞察することも無しに、盲目的に信用する傾向がある。
少し説明が長くなったが、これがおそらくぼくが霊の存在を信じられない本当の理由だと思う。
何のことはない。科学が霊というものの存在を否定しているからである。
つまり、ぼくが無神論者だから霊を信じられないというのではなく、〝科学の信者だから霊を信じるわけにはいかない〟というのが正確なところだろう。
科学の教義に於いては、霊を信じることは〝非科学的〟、つまり、異教徒とみなされるのである。
それにしても〝科学的〟とはどういうことであろう?
ぼくは最近、とある講演会の映像を見る機会を得たが、その話しの中で、映画 『マトリックス』の話題が出ていた。
「皆が現実だと思い込んでいるものは、実は、脳の中の電気信号がもたらす仮想の現象世界に過ぎない」というものだ。
同様のことは無論、仏教思想に於いても物ごとの核心として「色即是空」などと言及されている通りである。
人間にとって、この世は「死」という前提がある以上、全てが移ろいゆくまぼろしに過ぎず、確かなものなど何も無い、確かめる手だてなどどこにもない、ニューロン(電気信号を司る神経細胞)=心の作用がもたらすインナー・スペースに過ぎないというのである。
だとすれば、この現実(に見えるもの)自体、何も約束された共通の実体などであろう筈もなく、ましてや、「霊」や「彼岸」の存在などどうして確かめられよう?
現に科学は未だ「ココロ」というものの存在を規定することもできなければ、何ひとつ解明してもいない。
突き止めているのはその発生源が、実に〝電気信号!?〟であろうということだけである。
心が〝電気信号〟?
何のことやらさっぱりわからないのである。
つまり霊の正体とは感じたり見たりすればいるし、感じたり見たりしなければいない、単に各々の心のあり様によるもので、ではその肝心の「心」とは果たして何なのか?ということになると、我々の崇高な〝科学〟をもってしてもさっぱり解らないらしいのだ。
だから我々としても諦めなければならない。
実はぼくは元々とんでもなく不信心な人間で、少し前までは大晦日に神社にお参りすることすら無かった。
そういうことが〝合理的〟ではないと思っていたのである。
しかし昨今、歳を経る毎に、徹頭徹尾、合理的(科学的)であろうとすることが、果たして限られた人生の中でどれ程のことか、と感ずるようになってきた。
「不合理」なものに行動や思考をとらわれたく無い、と切実に願うなら、一方でまた、「合理性」にも人生の全てを規定されていいわけではない。
つまり、霊の問題にしろ、人生観にしろ、ぼくは自分が信じたいことぐらいは自分で決めたいし、自分の見識ぐらい自分の力で積み上げてみたいのである。
要は科学という、お仕着せのフィルターをかけて、万事、〝本当かどうか〟と悩むより、自分がどう思いたいか、生きたいか、ということである。
科学も合理性も手段であって、目的ではないのだ。科学は有益に利用したいものだが、科学の奴隷にはなりたくない。
というのも、このことはぼく個人の問題にとどまらず、現代社会の心の病巣のようにも思われるからだ。
科学は合理的、だから独善的に解釈してゆけば、小さな感情の機微には目をつむって最短で利益だけを追求するようになる。
最終的な利益の象徴は、今の社会の価値でいけば、勿論、金である。
すべからく目的だけがクローズアップされ、そこに至る人生の貴重な時間は、最も合理的な利益追求のプロセスでしかない。
その結果、価値は極端に一元化され、かつてあった広い意味での共同体意識や、他者への思い遣りや、誠実さや、忠義や、犠牲的精神や、弱者への慈悲や、とりとめのない小さな感情を愉しむことや、無益な奉仕といった、多元的で〝不合理〟なものは切り捨てられる一方だ。
しかし、これではまるで、偏狭なハイエナの群れを飼育しているに過ぎないではないか。
元々、人間とは何処へ行きたかったのだろう?
これらは科学(合理性)だけを信奉した社会のなれの果てである。
別の言い方をすれば、目に見えるもののために、目に見えないものを抹殺してきた成果である。
思えば、マザー・テレサが道端に行き倒れた浮浪者を助けたことに、どのような〝合理性〟があったのだろう?
例えば、社会にとって〝利益還元〟が難しいような貧しい高齢者や、治るあての無い病人を助けたからといって、どんな意味があるのだろう?
そんな問い掛けは身近にも枚挙に暇が無い。
しかし、結論から言えば、合理的であろうがなかろうが、我々は手を差し延べたいのである。
弱い者はどうしても救済しなければ気が済まないのである。
理由は有るといえば有るし、無いといえば無い。
とにかくそれが、合理性だけでは割り切れない、我々という「インナー・スペース」の住人であり、人間というものなのだ。
「人類は物を考える脳髄によって神を否定した。大自然に反逆して唯物文化を創造した。
自然の心理から生まれた人情、道徳を排斥して個人主義の唯物宗を迷信した。そうしてその唯物文化を日に日に虚無化し、無中心化し、動物化し、自涜化し、神経衰弱化し、発狂
化し、自殺化した。
これはことごとく「物を考える脳髄」のイタズラであった。「脳髄の幽霊」を迷信する唯物宗の害毒であった。
けれどもいまや、この迷信は清算されねばならぬ時が来た。神に対する迷信を否定した人類は、いまや「物を考える脳髄」を否定しなければならぬドタン場に追い詰められて来た。唯物科学の不自然から、唯心科学の自然に立ち返らなければならぬスバラシイ時節が到来したのだ。」(夢野久作 著 『ドグラ・マグラ』)
昔見たテレビ番組で埴谷雄高氏が、物理学(科学)は質量でしか世界を測ることができないが、文学は世界を〝質〟で測ることができる。科学など恐るるに足らない、という意味の発言をされていたと思うが、今ほどこの言葉を考えさせられる時代も無いのではないか。
さて、最後にもうひとつだけ付け加えるならば、科学という〝宗教〟が我々信者を導く涅槃の世界とはいつも光り輝く「未来」なのであった。
しかしそもそも、明日果てるとも知れない期限付きの命を抱えた人間に、どこまで行っても永久に辿り着けぬ「未来」なるものを指し示すとは、ちょうど、実体の無い「目的」のみを原理化する社会に似て不可解なことである。
実はぼくはこのテクノロジー社会が口を揃えて読経しがちな「未来」という言葉にどうも胡散臭さを感じている。
科学一神教社会のからくりを見るようである。
「未来社会を信じない奴こそが今日の仕事をするんだよ。現在ただいましかないという生活をしている奴が何人いるか。現在ただいましかないというのが〝文化〟の本当の形で、そこにしか〝文化〟の最終的な形はないと思う。
小説家にとっては今日書く一行が、テメエの全身的表現だ。明日の朝、自分は死ぬかもしれない。その覚悟なくして、どうして今日書く一行に力がこもるかね。その一行に、自分の中の集合的無意識に連綿と続いてきた〝文化〟が体を通してあらわれ、定着する。その一行に自分が〝成就〟する。それが〝創造〟というものの、本当の意味だよ。未来のための創造なんて、絶対に嘘だ。」(三島由紀夫 著 『東大を動物園にしろ』)
霊の仕業かどうかは知らないが、ぼくがかつて体験した、断じて作り話ではない「怪談」風の出来事〝その3〟
先に、テレビで「心霊特番」のような番組を見た後日、体験した、少し不思議な出来事を紹介したが、実はぼくはその他にも、これと似たパターンの信じられないような出来事に遭遇したことがある。
前の体験から数年後のことだ。
夏か秋かは忘れたが、何れにしろ、暖かい季節であった。
ぼくは父親と弟と三人で、岩手県遠野市の、今は空き家になっているお爺ちゃんの家に向かうことになっていた。
目的は、既に不要になった無人の家屋を掃除したり、整頓したりしに行くことで、父親が車を運転することになっていた。
さて、その前日か、少なくとも前々日のこと、ぼくはテレビを着けっ放しで、絵を描くか何かしていた。すると例によって、「心霊特番」系の番組が流れてきた。
それは「幽霊の姿が染み出した石」とかいう内容のもので、こういうのも「心霊写真」等と並んで、当時、有りがちな出し物のひとつであった。
因みにぼくは昔から心霊体験にまつわる怖ぁ~いお話し、つまり「怪談」の類いを愉しむのは大好きなのだが、「心霊写真」のような、こと、物理的、光学的な要素が加わる〝ネタ〟というのはどうも興覚めである。
オカルトというものを純粋に無邪気に面白がるためには、やはり心理的なものの危うさ、はかなさという要素が不可欠であって、また王道だと思っているからである。
そういう意味では「写真」ということになると幾らか即物的過ぎはしまいか?
なにしろ、この世でない、あの世の存在の筈が、生前の姿を思わせる細胞の集合体よろしく光りの粒子に反応したり、客観的、物理的フォルムを造形するという発想には少々、無理があると思う。
ぼくはそもそも、「怪談」と「心霊写真」との間には決定的な違いがあると思っている。
少し難しい話になるが、それは前者は、その文脈において、例えどんな突拍子もない出来事が起こったにしろ、それらはすべからく〝意味〟や〝象徴〟に収束されるのに対し、後者は怪しい〝実証主義〟に帰属する。
「怪談」とはいつも庶民の心の営みであり、その根底には他でもなく、〝ロマンティシズム〟が偏在する。
しかし、「心霊写真」となると、概して科学に対する劣等感以外の何者でもないからである。
脱線ついでに言及すると、ぼくは「怪談」とは「文学」の最も解り易い根源的な形式、とさえ考えている。
何故なら、本来、「文学」の領分である、人の心の内に巻き起こる様々な出来事とは、常に、奇妙で怪奇で不条理で幽玄なもの…、つまりは、おどろおどろしい「怪談」そのものではないか、と考えるからである。
さてさて、少し脱線が過ぎたようだが、ともかくその時、テレビには、何処とも知れぬ田舎らしい軒奥(普通の民家にも見えない)が映し出されていて、その仄暗い陰だまりの一隅に、大きな自然石から削り出されたと思しき置物が鎮座していた。その石に浮かび上がった無造作な黒い染みが、幽霊に見えるという話しである。
ふうん、だから?さすがに〝染み〟にまで意味を与えてもな。そりゃ、見ようとすれば何かには見えるだろう。第一、人の姿に見えるからって、何故それが幽霊なのか?人=幽霊か?まして何を根拠に怨念と結びつける?よしんばそれが霊界なるものの意思表示だったにせよ、何故、石に?どうしてそんな謎かけのような方法をとる?
ご想像のように、ぼくはこの「幽霊の姿が染み出した石」という代物を、何のテンションも無く、というより、正直、しょうもな~い気持ちで眺めていた…。
ぼくの記憶によればその翌日か翌々日、ぼくらは三人で東北自動車道を岩手に向かっていた。
ようやく花巻インターに近づいた頃、父親が珍しいことを言い出した。
たまには花巻より手前のインターで降りて、下から遠野へ向かおう。そろそろ用も足したいし、ついでに桃でも買って行くか。
ぼくは小さい頃から何度となく父親の田舎である遠野へ行っているが、父親がこんなことを言い出したのは初めてだし、こんなルートで遠野へ行ったこともなかった。
この降り口が果たして何というインターだったのか、今はもう、思い出すこともできないが、ともかく、ぼくらはその、街道が縦横に行き交う、辺ぴな田舎道を走っていた。
高速の降り口から幾らも行かないうちに、あそこで一休みするか、と父親が示したそれは、よく地方で見られる、果樹園農家が副業で営んでいる、おみやげ屋兼茶屋であった。
無論、飾り気なく、至って質素な佇まいである。
ぼくらはここに車を止めると、まず、奥の便所に入った。
ぼくが便所から出てくると、父親と弟の姿が無い。
どうやら桃を買いに、軒に入ったようだ。
ぼくもそこへ入っていった。
何らへんてつもない土間のスペースに、誰が買うのか、折り詰めの饅頭や粗末なベンチ。そんな鄙びた空間を何気なく更に進んだ時だ。
…ん…?
ぼくは何か得体の知れない、眩暈のような感覚に襲われた。
これはあながち大袈裟でなく、それまで感じたことの無い、夢の中を歩いているような、強烈な違和感。
その、僅かコンマ数秒の間に、ぼくはそれが破格に強いデジャヴュであることを理解した。
ここは知ってる…、ごく最近見たことがある…。何処で?
ぼくはほとんど朦朧としながら、更に答えと記憶の在処を求めて歩を進めた。
するとその奥に、何か不釣り合いな床の間のような場所があって、その上に鈍く、灰褐色の物体が…。
…あ…!
ぼくは瞬間、目を疑うと同時に、全身総毛立った。
そう、それはなんと、あの自然石の置物、「幽霊の姿が染み出した石」であった!
この時ばかりはさすがにぼくも戦慄した。
一瞬ではあったが、今まで信じてきたものが音を立てて崩れていくような、奇跡というものが突如、否定できない形で現出したかのような、そんな恐怖に近い感覚を味わった。
いや、それ程、驚いたのである。
このお陰で、その時の旅は、何か冥界に越境してしまったかのような、何とも冷えびえしたものとなった。
大体、岩手県遠野市とは柳田國男の『遠野物語』で名高い、「怪談」の聖地である(実はぼくが怪談好きなのも、元を正せばこの辺りの影響によるのである)。
それに、ぼくらが向かったお爺ちゃんの家というのは、長い間放置され、文字通り、お化け屋敷同然となった、古風な木造二階屋だった。
ぼくはこの…
ええ…、説論の途中ですが、今、通勤電車の中でこれを書いていて、生まれて初めて、乗っている電車が人身事故を起こしました。
通過電車におそらく、ホームから飛び込んだ模様。
しばらく電車に閉じ込められていましたが、車掌がうわずった声で「清掃が済んだ」と、発車を告げました。
隣の酔っ払いおやじ(何故か片手首に数珠)が吊り革にぶらぶらしながら、ヘラヘラ笑っています。
向かいの気持ち悪い女が窓の外をチラチラ見たり、ぼくが隣に座ると、ぼくのiPhoneを妙に覗き込もうとしてきます。
ヘッドホンからずっと、ルー・リード 『ワイルド・サイドを歩け』 が…。
2009.5.25 PM23:38 国領駅にて
いたこ28号さんのサイト
山口敏太郎さんのサイト
ファンキー中村さんのサイト