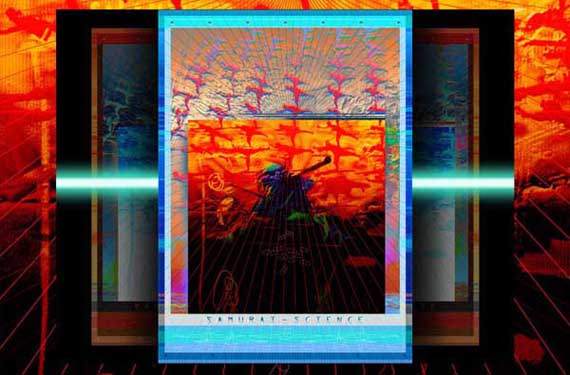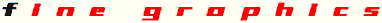Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
儘儞僌僥乕儖僘FILE;vol.5
媑揷枮 挊亀愴娡戝榓偺嵟婜亁
嬨巐幃巐屲岥宎巐仜僙儞僠庡朇(巐榋僙儞僠朇)搵嵹丄嶰擭幃60岥宎15.5僙儞僠暃朇搵嵹丄敧嬨幃巐仜岥宎堦僯.幍僙儞僠楢憰崅妏朇搵嵹丄嬨榋幃25儈儕3楢憰婡廵搵嵹丄嬨嶰幃堦嶰儈儕楢憰婡廵搵嵹丄15儊乕僩儖丄10儊乕僩儖應嫍媀搵嵹丄僯崋堦宆揹攇扵怣媀搵嵹丄楇幃悈忋娤應婡搵嵹丄僶儖僶僗丒僶僂(媴忬娡庱)丄僶儖僕丄杊悈嬫夋巤愝丄慡挿263儊乕僩儖丄慡暆38.9儊乕僩儖丄婎弨攔悈検64000僩儞丄廳桘枮嵹検6300僩儞丄嵟戝懍椡27僲僢僩乧丅
偐偭偙偄偄偲偄偆偙偲偼恖傪嶦偡傕偺偱偁傞丅
壗屘側傜丄偐偭偙偄偄傕偺偼愄偐傜晲婍傗暫婍偲寛傑偭偰偄傞丅
壛偊偰丄嫄戝側暔偼恖傃偲偵堌宧偺擮傪梌偊傞丅
偩偐傜傛傝懡偔偺恖娫傪嶦偡偙偲偵傕側傞丅
乽奜尳(偑偄偘傫)傪嬧敀堦怓偵揾憰偣傞乽戝榓乿丄幍枩嶰愮酔(僩儞)偺嫄懱偼夽執(偐偄偄)側傞娡庱偵媏偺屼栦復傪婸偐偣丄巐廃傪埑偟偰晄摦斦愇(偽傫偠傖偔)偺巔側傝乿(媑揷枮 挊亀愴娡戝榓偺嵟婜亁妏愳暥屔姧傛傝)
儅儖僙儖丒僨儏僔儍儞偑尵媦偡傞傛偆偵丄乽偄偮傕巰偸偺偼懠恖偽偐傝乧乿側偺偩偐傜丄恖娫偼塱媣偵乽巰乿傪懱姶偡傞偙偲偼偱偒側偄丅
柍榑丄乽巰乿偲偼堦屄偺娤擮偱偁傞丅
偦偆偄偆堄枴偱偼丄乽戝榓乿(摨媊岅偲偟偰偺崙壠)傕傑偨丄嫄戝側巰偺儊僞僼傽乕側偺偱偁傠偆丅
亀愴娡戝榓偺嵟婜亁傪庴偗偰丄擇丄嶰偺暥壔恖偼乽僥儖儌僺儗乕偺愴偄乿(柤梍偁傞嬍嵱愴)側偳偲尵偆丅
偟偐偟丄偙偺彫愢偺拞偱偼丄椺偊偽丄庡恖岞偑寖愴偺枛丄偄傛偄傛夡柵傪慜偵偟側偑傜丄堄奜偵傕扺乆偲壻巕傪杍挘傞條巕偑昤偐傟偰偄傞丅娡挿傕傑偨丄巰弌偺暿傟偵晹壓偐傜栣偭偨價僗働僢僩傪殫傞丅
乽偆傑偟丄尵傢傫曽側偔偆傑偟乿偲偄偆偺偱偁傞丅
偙偆偟偨昤幨偼寛偟偰丄暫巑偨偪偺崉婤傪昞偟偰偄傞偺偱偼側偄丅
巰偺嬍嵱愴偑丄扨偵乽巰偺嬍嵱愴乿偲偄偆柤偺偆偭偲偍偟偄擔忢偱偁傞偙偲傪朶偄偰偄傞偺偱偁傞丅
幚偼偙偆偟偨売強偵丄娤擮偲偟偰偺乽巰乿偐傜撍擛敳偗棊偪偨柍岰偺庤墳偊偑偁傞丅
偙偺嶌昳偵偼偙偺傛偆偵丄偳偙偐斲掕傗巀旤傪挻墇偟偨丄愴応偲偄偆傕偺傊偺惲傔偨娽嵎偟偑偁傞丅
偲偙傠偱偦傟偼丄偙偺暔岅傝偑丄廔愴捈屻偵彂偐傟偨惓恀惓柫偺庤婰偱偁傞偙偲偐傜丄杮暔偺愴応偺僼傿乕儕儞僌偑偍偍傛偦偙偆偟偨傕偺偱偁傠偆丄側偳偲偄偆堄枴偱偼側偄丅
帠幚丄偦傫側傕偺偼丄嫟捠擣幆偲偟偰偺噣杮暔偺愴応噥側偳偲偄偆傕偺偼丄偙偺悽偺偳偙偵傕偁傝偼偟側偄丅
偮傑傝丄偙傟偼暣傟傕側偔嶌幰撈摿偺姶惈偱偁傝丄嶌晽偲偄偆傕偺偱偁傞丅
偩偐傜堦曽偱丄偁傞恖偑偙傟傪乽僥儖儌僺儗乕乿(弮娤擮揑旤摽偲偟偰偺乽巰乿=乽嶶壺乿)偲尒棫偰傛偆偲傕丄偦傟傕傂偲偮偺愴憟(楌巎)偺夝庍偲偄偆偙偲偵側傞丅
偮傑傝丄弌惇偟偰備偔暫巑偑丄幚偼扤傂偲傝丄帺傜偑愴巰偡傞応柺傪憐憸偟側偄(偱偒側偄)傛偆偵丄奺乆偺乽愴憟乿偲偼(偲偄偆傛傝傕愴憟偙偦)幚懺偺柍偄丄柉懓偑怐傝側偡偲偙傠偺乽徾挜乿偵夁偓側偄偺偱偁傞丅
偩偐傜偙偦愴憟偼柍偔側傜側偄丅
乽巰乿偲偼変乆偵偲偭偰朤娤偟偨傝暥柆壔偡傞傕偺偱偁偭偰丄寛偟偰丄懱姶偡傞(偱偒傞)傕偺偱偼側偄偺偩偐傜丅
傕偲傛傝丄乽娤擮乿偑乽尵岅乿偵傛偭偰廃摓偵曇傒崬傑傟偨巚堃偲偄偆柤偺僼傿僋僔儑儞偱偁傞埲忋丄恖偼尵梩傪惗傒弌偟偨帪偐傜丄偄傢偽丄懳徾壔偱偒傞偁傜備傞傕偺傪乽旤摽乿偵曄偊偰偟傑偭偨偺偩丅
偩偐傜丄愴憟偝偊旤偟偄偺偼帺慠側偙偲偱偁傞丅
旤偟偄柉懓丄旤偟偄崙壠丄旤偟偄惛恄丄旤偟偄摦婡丄旤偟偄暫婍乧丅
偦偟偰抧崠偑岥傪奐偗偰偄傞丅
柍榑丄旤偟偄抧崠偑乧丅
乽傢傟堦弖偲偰巰偵捈柺偟偨傞偐
弌峘埲棃丄巰惗偺娭摢偵傆偝傢偟偔丄傒偢偐傜傪嬅帇偣偟偙偲偁傝傗
嵟屻偺崗乆偵丄嵄偐偺惗峛斻傪傕姶偠摼偨傞傗
傢傟偼巰傪抦傜偢 巰偵怗傟偢乿 (媑揷枮 挊 亀愴娡戝榓偺嵟婜亁妏愳暥屔姧傛傝)