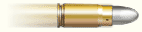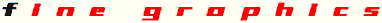Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
ロングテールズFILE;vol.4
映画 『死んでもいい』(1992年公開)
正しくて健康なことがあらゆる場面において美しいのならこんなに良いことはない。しかし、どうやら真実はそうではない。
石井隆監督の映画『死んでもいい』は一言で言ってしまえば、生臭い三面記事のような作品であった。
東京近郊の地方都市(大月)に目的も無いまま、ふらりとやって来た青年が、偶然、出会った人妻に一目惚れし、ずさん極まりない不倫劇を繰り広げた挙句、短絡的にも夫を殺害してしまう。
原作の『火の餓』(西村望 著)は実際の事件を題材にしたノンフィクション風の作品だが(実際の舞台は東大阪)、この事件自体、いかにも往年の〝低俗番組〟「ウイークエンダー」あたりで取り上げられそうな、何か、すえた焦げ臭さとでも呼ぶべき愚鈍な人間模様であった。
何故これ程俗悪にして凡庸を極めたようなモチーフを、渾身の映画人生を賭けて描こうとする監督がいるのか、まず、それが驚異であった。
ベースがそうだからか、とにかくこの映画は〝何だかダメ〟な記号に満ちている。
先に言っておくと、〝てんでダメ〟なのではない。〝何だかダメ〟なのである。
都心への窓口という以外、形容のしようもない地方都市、駅前の小さな不動産屋と歳の離れた夫婦、喘息持ちで住所不定の青年、地方商店会の慰安旅行、今時、時代がかった水辺の連れ込み宿、そして不倫の末のありふれた殺人劇。
あらゆる記号にどこか1960年代、70年代の残り香が染み付いていて、どうも落ち目で、乗り遅れた感じである。
物語の図式だけを言葉にしてみればそういうことになる。
しかし、にも関わらず、私はこの映画『死んでもいい』を今までも、また、これからも、熱烈に支持してゆきたい気持ちである。
これは奇妙な二律背反に聞こえるかもしれない。
しかし、それは例えば、古臭くて愚鈍なことの中に決して美が成立し得ないのならば、あるいは、そういうことになろう。
しかし事実はそうではない。
しかも圧倒的な美しさである。
石井隆監督といえば言うまでもなく、『天使のはらわた』シリーズに始まる〝名美、村木〟ものがつとに有名な日本映画の名匠である。
近年は『花と蛇』シリーズなど、オリジナル以外の企画でセールスをあげたと思いきや、最近作『人が人を愛することのどうしようもなさ』では、再び本来の持ち味にカムバックしている。
ところで、私にとって、石井隆の映画は非常に特別な意味を持っている。
というのも、私はある時期までの、幾つかの石井作品を、それこそ、宝石のように想っている。が、しかし一方では、それ以外の大半の作品をどうも諸手をあげて愛せないのである。
つまり私にとって、彼程、出来、不出来の振幅の激しい映画監督は他にいない。
では、どんな作品が私にとって賭け値なしに〝石井ワールドの至宝〟と呼べるのか?それは今回、取り挙げた『死んでもいい』を別にすれば、例えば、監督第一作にして〝名美、村木もの〟の真髄を感じさせた『天使のはらわた 赤い眩暈』、それに石井演出の精密さと亜流を許さない独特のリリシズムが結晶した『ヌードの夜』、また、バイオレンス・アクション・エンターテイメントを標榜しながら、実は圧倒的にリアルな内面を持つ、日本人による日本人のためのフイルム・ノワール『GONIN』、更に言えば、石井隆が原案、脚本で参加した相米慎二監督の傑作『ラブホテル』と、いったところだろう。
もっともこれは、多くの石井映画フリークが異口同音に唱える呪文ではないだろうか?
それにしても私としては、これら石井映画のエッセンス100%の作品群の中でも、実は一本だけ異端の作品『死んでもいい』を〝最高傑作〟に挙げなければならない
ことを、幾らか皮肉な気もしている。
因みに『死んでもいい』がここに挙げた他作品と幾分、趣きを異にする理由は、ひとつには、劇画家であり、脚本家でもある石井監督がめずらしく他の原作ものに材を取っていること、また、アクションの要素が皆無の、一見、文藝作品風会話劇であること、そしてまた、石井映画の十八番とも言える道具立てや、名美、村木の純愛そのものが必ずしもテーマの主眼となっていないこと(私はこの映画が、単なる恋愛劇という以上に、もっと根深い人間の業を描いたものだと思っている)などが挙げられよう。
さて、あたかも愚かしい人間の営みや野暮ったさが一瞬にしてシャープな狂気となり、美に転嫁される〝石井マジック〟については先にも少し述べた。
こうした切り返しの切れ味は、例えば、この映画における編集の、小気味よく〝割られた〟部分と徹底した〝長回し〟との対比にもよく表れている。
人妻、名美(大竹しのぶ)と信(永瀬正敏)の不動産屋での出会いのシーン(たたみかけるような切り返しのカット)や舟宿での密会シーン(極端な長回し)などがその典型である。
もっともこれらの方法論は、石井映画の常道ではあるけれど、私はこの映画に関する限り、こうした演出効果の冴えは一段、傑出していると思う。
長回しに関してはこの他にも、信が名美をモデルハウスで襲うシーン、名美の夫(室田日出男)が名美の浮気を車中でなじるシーン、そして何と言っても、クライマックスの、ホテルでの殺戮シーンなどに息詰まるような緊張感を与えている。
そういえば、日本映画において〝長回し〟と言うと、やはり相米慎二を思い出すけれど、しかし私は、あのアーティスティックな文脈における意図的な錯誤(割らないことの動機の部分にどことなく〝反体制〟のにおいがする)とも言うべき長回しなんかより、生粋の活動職人としての石井隆のそれの方が、ずっとしっくりくるのだが、如何だろうか?
さて、『死んでもいい』という映画にはその構成の部分に、こうした的確な方法論が存在するわけだが、それと共に見逃せないのは、この映画の隠喩(メタファー)の精緻である。この意味で、私は『死んでもいい』ほど濃密な、〝映画という以外の何者でもない〟映画は無いと思っている。
軸となるのは、石井映画の象徴、〝雨〟と火(煙草)の対比である。
「間が悪かったね.通り雨だっていうのに」
この言葉は物語りの冒頭、後に殺害される名美の夫から加害者の青年、信に対して、自ら吐かれることになる。
〝通り雨〟とは無論、信のことであり、それはまた、〝官能〟を表している。
これに対して名美が灯すライターの火は〝情熱〟だ。
喘息の信は危険と知っていても名美の唇からくゆらされる紫煙の間近に接近する。
そうして、名美が灯す煙草の火を中心に、二匹の〝蛾〟が寄り添っている。
いずれにせよ、〝官能〟と〝情熱〟の向かうところは〝死〟なのである。
それにしても「恋」とは何だろう?
何より映画『死んでもいい』の恐ろしさは、名美の夫を余りに魅力的に描いている点であり、故人、室田日出男の信じ難い程の素晴らしさである。
何故、彼は殺されなければならなかったのか?その一点を映画は問いかける。
人間とは何だろう?
男と女は何処へ行くのか?
こうしたテーマに加えて、とかく仕掛けや道具立てやモチーフのけれん味ばかりを追求しがちな映画づくりにあって、これ程、端的なテーマで、これだけ人間性をえぐる作品があり得るならば、映画とは果たして何であろう?
映画のクライマックス、三人のもつれ合いの胸苦しさ、殺される者のやり切れなさ、人間存在の根源的な哀しみが観る者の心を鷲掴みにする。
そしてラストシーン、名美の余りにも美しい涙が、絶望を超越した彼岸の〝水辺〟となって、私の胸を壮絶に撃つのである。