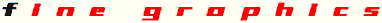Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
ロングテールズFILE;小休止
見ることはつくること
僕は、〈見る〉ことと〈つくる〉ことはそれほど距離のあることではないと思っている。
というか、もし、〈見る〉ことと〈つくる〉ことが同義であったなら、これほど独創的でエキサイティングなことはないだろう。
いやいや、〈見る〉ことと〈つくる〉ことを同義だと感じることだ。
〝つくる〟ように見たり、〝見る〟ようにつくることだ。
例えば、絵画や映画を観たり、文学や音楽を楽しむ時、〈私〉という微細で膨大な記憶の欠片が発動し、意識の底に何かがかたちづくられる。
これが〝つくる〟という状態だ。
例えば、真っさらな紙を前にして、果たしてこの白い余白にどんなプロセスで、如何なるビジョンが立ち現れるか?それを冷徹に見届ける〈私〉がいる。
それが〝見る〟という行為だ。
些細な日常の中でインプットとアウトプットが交錯し、能動と受動が裏返りながら無名の〝時〟に名前を与える。
するとそれが日記になったり、人生になったり、歴史になったりするものだ。
僕は〈過去〉と〈現在〉は明確に区別できるものではないと考えている。
人間は〈記憶〉の生き物だ。
〈記憶〉は時系列とその優先順位が重要なのであって、その整合性と配分がその人のアイデンティティということになる。
しかしそもそもあらゆる記憶の所在は地続きだから、例えば、見慣れた記憶の合間に、ひょっこり異質な記憶が滑り込んだとしても不思議ではないし、また、僕等がいつ、どこで、どんな記憶を呼び起こそうとも、お構いなしというわけだ。
このことは人類の記憶という意味の〈歴史〉であってもまったく同様なわけで、つまり人は〈思い出〉や〈歴史〉の素子を好きな場所から勝手に取り出したり、時には想像力を駆使してその過去へ適宜、往復したりすること、そのことで自由になれる。
僕等には必ずしも〈記憶〉を整然とさせておく謂れはないのである。
第一、共通の〈記憶〉や〈歴史〉など始めから存在しないのだから…。
僕はこうした考えが好きだし、方法論も好きだ。
僕は幾らか〝ダメ〟であっても面白いものが好きだ。
と、いうよりは〝つまらない正論〟のようなものが嫌いなのである。
何事も整理されていれば良いというものではない。
正しくても、賢くても、真面目でも、偉くても、イケてても、器用でも、要領が良くても、お金持ちでも、結局、面白くなければ始まらない。
このことは、映画や小説の世界を考えるとわかり易い。
主人公が卒なく時代を先取りしてて、合理的で、カッコいい有名人なんてまっぴらだ。
そういう映画もあるにはあるが、まず面白かったためしがない。
映画や小説の主人公は落ち目で、乗り遅れていて、不器用で、少々インチキ臭く、程よく不真面目な小市民が何よりだ。
そんな〝ダメ〟でもそこはかとなく〝面白い〟主人公が、何らかの〈幸福〉を勝ち取った時、決まって映画は終わる。
なぜ終わるのか?それは美意識という価値において〈幸福〉とは語るべき何ものでもないからである。
美もない、義もない、生き甲斐がないのである。
勿論、この話は三島由紀夫のことでもある。
しかしそれでも僕らは我身についての幸福を願わずにはいられない。
例えそれがぶくぶく肥太るための、ふやけたアイロニーの世界とわかっていても、切実に待ち焦がれるのだ。
それはほとんど喜劇のように…。
〈幸福〉を語るべき何ものでもないと見なすことが良いことなのか悪いことなのか、また、〝語れる〟ことが果たしてどんな足しになるものなのか、僕には解らない。
しかしともかく、このことは、美しいことを数えて生きる人々にとっては痛烈なジレンマなのである。
僕は東京生まれの東京育ちだから、故郷というようなものは無いのだけれど、それでもそこを訪れると今でもいわく言い難い気分にさせられる街ぐらいはある。
例えばその一つは調布であり、もう一つは三軒茶屋だ。
調布は子供の頃を過ごした街で、三軒茶屋は高校時代を過ごした街だが、殊に前者は、何時訪れても、例の奇妙な感覚に襲われる。
これを人は郷愁と呼ぶのだろうか?まるで〈記憶〉そのものの中をさすらっているような形容し難い哀切感にも似た感覚。
実際、ある頃まではこれらの場所が度々夢の中に出てきたから、なおのことそんな気分にさせられる。
実は、僕の過ごした調布の界隈はつげ義春の漫画の舞台として度々登場する。
あたかも、あそこはあの漫画の舞台で、この辺りが…、と言った具合に、僕だけが知っている秘密のつげ漫画探訪が組めそうだ。
もしかするとそんなことも、あの奇妙な感覚と何か関係しているのかもしれない。
因みに、僕の往時の住まいは旧日活撮影所と旧大映撮影所のちょうど中間地点に位置した。
幼少の頃から映画の撮影には慣れ親しんできたから、そのせいで映画好きに育った、と考えられなくもない。
さて、去年のことだが、僕はある休日、砧公園内にある世田谷美術館にひとり出かけた。
久しぶりに横尾忠則の絵なんぞ眺めた僕は、まだ日が残っているのをいいことに、世田谷線で経由して来た三軒茶屋にて道草を決め込んだ。
そういえばこの街を最後に訪れたのは何時のことだろう?
遥か記憶に封印された街で、僕は早い飯を喰った。
246の向こう岸とこちら岸に点在する下町風情の商店街をあてどなくぶらつき(やはりこういう町は胸に沁みるようなオレンジの夕暮れが似合うものだ)、気が付くと、何とはなしに母校の方へ足が向いていた。
夕闇に浸され始めた人気のない246号線沿いを全く無為に歩き始めた僕だったが、思えば、そんな気ままな散策は以前にはお手のものであった。
遠い見知らぬ町、遥か記憶に忘れ去られた場所を、何処までも何処までもあてどなく歩く。
ところで何故、僕はそうした〝あらかじめ過去に閉ざされた〟街や、或いは見ず知らずの土地をひとり歩くことを好むのか?
それは一言で言えば、時折、ふと、〝遭難〟してみたくなるからである。
今、自分がここにいるということを果たして誰が想像出来よう?という、実に心細いシチュエーションを僕は好む。
とはいえ、これはあくまで日常からひとしきり逸脱するためのささやかな遊戯に過ぎぬ。
何故なら、僕はこの時歩いた246号沿いの歩道を、それよりずっと以前、逆方向から辿ったことがあった。
つまり渋谷から三軒茶屋方面に歩いて来たことになるが、時刻は確か、深夜1時頃だったと思う。
何故そんな時刻にこんな処をひとりで歩いていたのか、というと、以前、僕は、一時的に帰るべき住みかを失ったことがあって、その時、渋谷の道玄坂上にあったカプセルホテルを仮宿としたのであるが、ある日、仕事を終えて、あの蜂の巣を思わせる棺桶の中で眠りにつこうとしたものの、時刻がやや早い。酒を飲みたくとも金も無いので、成り行き、夜の街をぶらつくことになったのだった。
そうして気がつくと、僕はかつて一時期を過ごした街を目指して、なんとなく歩いていたのである。
時折、猛スピードでヘッドライトとテールランプが行き交う他は人の気配すらもなく、あれ程慣れ親しんだはずの街は、かつて僕が知っていた街とはまるで別人の貌をしていた。
僕はとても深い闇の底に沈んだ気がした。
〝今、自分がここにいるということを果たして誰が想像出来よう?〟
昔観た『上海異人娼館』という映画の一説に、「私はまだ誰でもない…」というのがあったけれど、この時の僕はまさしく誰でもなかったのである。
人間には知らず知らずのうちに守られている命綱があるということや、あんなに眩しい夜の灯りのすぐ側で、これ程深い漆黒の闇が口を開けているということを僕はこの時知った。
僕は今、この底知れぬ冷たさを湛えたアスファルトの上に大の字にうつ伏せ、頬を触れさせてみたら、そこから感電するように瞬時に伝わる感覚、それこそが〈絶望〉だ!と思った。
もっとも、僕はその後、道端に大の字になることはせず、また、母校に辿り着くこともなく、ただ、蜂の巣に戻ると、そのまま何も考えず眠ってしまった。
さて、深夜にではなく、夕暮れに246を歩いていた日の話を続けよう。
僕が久しぶりに母校である◯◯◯高校を眺めた時にはもうすっかり宵闇が街灯りを凌駕していた。
過去と現在が微妙にぶれながらオーバーラップし、心地良い湿度を帯びた宵の大気は、僕に、またあの感覚を蘇らせる。
〈記憶〉そのものの中をさすらっているような感覚…のことである。
現実感の希薄さ。眩暈のような哀切感。優しく忍び寄る不安。
それは思考ではなく、嗅覚で感じる孤独だ。
僕はそのまま学校をやり過ごすと、記憶の回廊、ゆるやかな坂道を下っていった。
考えてみればこのわずか数100メートル足らずの距離は、僕の中ではまるで異次元スポットのようだ。
体育会だけは特別低料金で散髪してくれた、東條英機そっくりの老人の店があったことや、学祭の日、同級生が一方通行をバイクで逆走し、激突死したのもこの場所だった。
僕の脳裏に、かつて存在したことすら忘れ去られ、今の今まで封印され続けた微細な過去の数々が突如、一斉蜂起し、あたかも幻覚のように甦る。
濃い紫の宵闇が、映画館の暗闇の役割を果たし、記憶のスクリーンを鮮明に滲ませる。
僕は歩いた。
引き返そうという気にはなれなかった。
思い出をフィードバックするのが嫌だったのである。
始めのうち、僕は、微かな記憶を頼りに井の頭線の方向を目指していた。ところが、ひとしきり行ったところで、とうとう方角をつかめなくなってしまった。
記憶の回廊を越え、見知らぬ土地に到達してしまったのである。
激しく車の行き交う街道沿いを、僕はどこまでも歩いた。
すれ違う人も無い、夜の並木道の小さなショーウインドーを見つけると、決して出会うことの無い存在の不思議を感じながら僕は歩き続けた。
スティービー・ワンダーが"I GO SAILING"と唄った気がした。
さすがに心細くなってきた頃、ようやく世田谷線の駅舎に燈る灯りが見え始めた。
まるで〈遭難〉しようとして、本当に〈遭難〉しかかった人のように、僕はそれを認めた。
そしてその時ふと、もしかすると僕はもうとっくの昔から〈遭難〉しているのかもしれない、という考えが頭をよぎった。
しかしともあれ、一時的にせよ、灯りに身を浸せる場所があるということがその時の僕には暖かく感じられて、僕は迷わずその光の中へ身を滑り込ませた。
2009.3.15