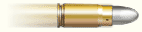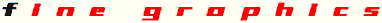Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
�����O�e�[���YFILE;vol.2
�c��-�|�b�v�E�A�[�g���߂�����
����̂���́w�|�b�v�E�A�[�g�x�Ƃ������ƂŁA����ɂ��Ă܂����l���Ă��������̂�����ǁA���������́w�|�b�v�E�A�[�g�x�Ƃ������̖̂{��ǐ^�����ꂩ�炨���炢����̂͂������ɋC���ł͂Ȃ��B
�����l���Ă����炩�ėy���L���̔ޕ��ɂ���炵�����̂�Ԃ������Ƃ��v���o�����I
�Ƃ����̂͊w������Ɉ�x�A�����������̂������K�v�ɔ����ĊT�ς��Ă݂����Ƃ������������B
���Ắw�|�b�v�E�A�[�g�x�ł���B
���������킯�ō���͂܂��A���Âٕ̐����g���Ă���������Ă������B�������炸�B
�ǓƂ̕\�w �`60�N��i�V�b�N�X�e�B�[�Y�j�|�b�v�ƌ���A�����J�A�o���̊�`
�n�[�V�[�̔`���R������Ƃ������C��������������
�w�l�͎q���̍��A���C�h���ق��Ȃ�Ė��͈�x���v���`���Ȃ�����.�l���������̂̓L�����f�B�̂��Ƃ�.�傫���Ȃ�ɂ�āA���̖��́u�L�����f�B���邾���̂�����ׂ���v���ɂȂ��Ă�����.�����Đ�������������l�Ԃ͌����I�ɂȂ������ˁx
1987�N2���A���ԒB����u�h�����v�Ƃ������̂ŌĂꂽ�A�����J���E�|�b�v�̋M���q�A�A���f�B�E�E�H�[�z�������E�����B
�u�h�����v�Ƃ̓h���L�����ƃV���f������g�ݍ��킹������ŁA�ނ̍H�[�A�ʏ́u�t�@�N�g���[�v�ɏW�܂������s�C���������������ԒB�ɂ���Ė������ꂽ�B
�`�F�R�l�̕�������A�F���łǂ������ł������Ȕނ̕��e�ƌ|�p�ƂƂ��Ă̈���ˋC�����������`�e�ł���B
����ɔނ͑�����B
�w�l���O�x�ڂ̐_�o�a�ɂȂ������́A�܂��]���ȃL�����f�B�Ȃ����Ȃ�����.���̌�A�l�̎d�����������n�߂āA�����Ղ�L�����f�B����ɓ���悤�ɂȂ���.�����Ⴀ�V���b�s���O�E�o�b�O�ɓ������L�����f�B�����������ς��ɒu���Ă���.�����獡�A�L�����f�B�̂��Ƃ��v���ɁA�l�������������ʁA���C�h�̕�������Ȃ��ăL�����f�B�̕�������ɓ��ꂽ���Ă��ƂȂ�.�O�ɂ��������悤�ɁA���ׂĂ͎q���̍��ǂ�Ȗ��������Ă������A�܂胁�C�h���~�����������L�����f�B���~�����������ɂ������Ă���̂�.���̍����������̂������ŁA�l�͍��A�n�[�V�[�̔`���R������Ƃ������C�������������x
�|�p�E�ɂ�����60�N��͂܂��Ƀ|�b�v�̎��ゾ�����B����́A����������Ȃ�A�����J���^�Ɂu���E�v�Ɠ��`��ɂȂ�u�Ԃ������B
�j���[���[�N����A���f�B�E�E�H�[�z�����W���X�p�[�E�W���[���Y(�ނ����o�[�g�E���E�V�F���o�[�O�̓|�b�v�E�A�[�g�O��A�l�I�E�_�_�C�X�g�Ƃ��Ċ��Ƀ|�b�v�̌�����Ă���)�A���C�E���L�e���V���^�C���A
�W���E�_�C������M���ɁA�g���E�E�G�b�Z���}���A�W�F�C���Y�E���[�[���N�C�X�g�A�N���X�E�I���f���o�[�O�A�W���[�W�E�V�[�K���Ƃ�������ƒB���r�o���ꂽ�B
�\�ʂ����S��N�H���n�߂�
�A������ʎY�i�A�ɍʐF�̃R�}�[�V�����Y���A�I�����W�Ɠ��̂Ȃ����w�A�o���h���t����p�̃f�N�l�`�A���ɏ�������R�~�b�N�̒��̏����A���������|�b�v�E�A�[�g�̎�l���B�͂��̇��Â��ǂ����O�H�̃A�����J�̌��ƉA�����݂������V�j�J���ɁA�X�������e���Č������B
���������R�̂��Ƃ̂悤�ɐ��E�̒��S�̓p������m�x�Ɏ���đ������B
���_�������A�����ȕ����M�����E�𐧂����̂ł���B
�Ⴆ�E�H�[�z���́u�l�͋@�B�ɂȂ肽���v�Ƃ��u�������Ȃ������A���f�B�E�E�H�[�z���ɂ��Ă̑S�Ă�m�肽���Ǝv���̂Ȃ�A�l�̊G���f���\�ʂ����ė~����.�����ɖl������.���̔w��ɂ͉����Ȃ��v�ƌ���Ă���B
���̌��t�͑��ł��Ȃ��A���E�̕\�ʂ����S��N�H���n�߂����Ƃ������Ă���B
�Ƃ����̂��A�ނ�̍�i�͏�Ɏ����̎������A�܂��͓��I������h�邪���Ƃ����������Ő������邩��ł���A���������Ӑ}���ꂽ�����̊T�O���|�p�Ɏ������ނ��Ƃ����ނ�̍ł��d�v�Ȋ�݂������B
���̂��߁A�ނ�̃��`�[�t�Ƃ��ẮA�X�ɔ×����A��l��������R�}�[�V�����ȃC���[�W���x�X�I�ꂽ�B
���_�A���̒��ɂ͐��_���Ƃ��������͖̂����A�����A�����̃V���{�����A�₽���ȃ��J�j�Y���A�܂��͑����I�ŃI�[�g�}�e�B�b�N�ȃC���[�W�̘A�������邾���ł������B
�W���X�p�[�E�W���[���Y���܂��A�ނ̍�i�u���v�ɂ��āA�w�A�����J�����̃f�U�C�����g�����ƂŁA���́A�����̖��ʂ����Ȃ��ōς�.���̂Ȃ�A���͊����f�U�C������K�v���Ȃ��������炾�x�ƌ����Ă̂���B
�ǓƂɊo����������A�����J�́u�ߌ��v
���āA�����������Ƃɉ����āA�|�b�v�E�A�[�g�ɂ͂�����̏d�v�ȑ��ʂ�����B
����͉X�����J��Ԃ����n�������ƁA�����������i�Ƃ�������F���̗��ɉB���ꂽ������悤�ȌǓƂ̊炾�B
�����Ă��ꂱ�����܂��Ɍ���A�����J���g�̊�Ȃ̂ł���B
�|�b�v�A�[�g�ɂ����鉼�ʂ̗����Ƃ��Ắu�ǓƁv�́A���̕\�����̌��������߂ɁA�������Ă������蕂���яオ���Ă��邪�A����Ɠ����̋������┙�R�Ƃ����s���A�J�T�Ƃ��������̂͑��̃A�����J���E�A�[�g�ɂ����ʂ��Č�����B
���ꓙ�͂����炭�p���𒆐S�Ƃ������[���b�p�G��( �_�_���V���[���A�C�M���X�E�|�b�v����ٓ_�Ƃ��Ă� )�̏�Ō��ꂽ�u�ǓƁv�Ƃ͉����َ��̊�������B
�Ⴆ�ł��A�����J�I�ƕ]�����z�b�p�[�����C�G�X�ɂ����Ă�����͌����ł���B
�G�h���[�h�E�z�b�p�[�̍�i�A�u�i�C�g�E�z�[�N�X�v�Ő[��̃R�[�q�[�E�X�^���h���瓊��������ꂽ�j�̗J�T�Ȏ����́A�W���[�W�E�V�[�K���̐p���B�������ŕ������낤�Ƃ���A���̈ł̐[���Ɉ����p�����B
�[�I�Ɍ����Ă��܂��A���������A�����J�́u�ǓƁv�̍��{�́A���j���������Ȃ����������̏��݂̖�������h�����Ă���ƌ����Ă����B
�����Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�̊��͂܂��A�A�����J�̑��������ƂƂ������ʂ�����e�ՂɉM���m��邾�낤�B
�������ČǓƂɊo����������A�����J�́u�ߌ��v�Ƃ́A�����ɁA60�N��̂����̐l�X�ɂƂ��đ傢�Ɂu�쌀�v�������Ƃ����킯�ł���B
�����ł̓A�C�f���e�B�e�B�s�݂̔Y�߂�A�����J�́A�}�������E�������[�̃V���N�X�N���[���⎇����f���o������ȏ��̐O�Ƃ������n�������̕\�w�Ɋ��g���ꂽ�̂ł���B
���������A��������60�N�㗬�A�����J���u�쌀�v�̗����҂������E�H�[�z���ł������B
�ނ͌|�p�������|�b�v(���L�����f�B)�̂悤���r�߂Ă��܂����B
��������̔��ł���B�ނ̍�i�ɂ��r�߂�ɂ��傤�ǂ��������Ǝh�����[�����Ă���B
���̓G�l���M�[�ɂȂ邵�A�h���͑z���͂����N���邩��ł���B
���āA�l�͂ǂ��炩�Ƃ����Ɓu����v�Ƃ������̂����܂�ǂ܂Ȃ��B
���R�͊�������āA���������u����v�Ƃ������f�B�A�ɂǂ����v���Ƃ��낪����̂ł���B
����A�ނ���Ŏ��͋�������������Ȃ��B���鍠�܂ł͖l������Ȃ�ɖ��拶�ł������B
�ܘ_�A�u����v�ƌ����Ă��\�H�ЂƂ��炰�ɂ������͖����B�X�̍�i���͎̂�y�Ɋy���߂���̂̔��ɑ������f�B�A���Ǝv���B
�ł��A���̇���y�Ɋy���߂釁�Ƃ������Ƃ��ނ���Ȏ҂ŁA�������\�����Ƃ������̂Ɏ�y���Ƃ�����Ղ���������߂�C�ɂȂ�Ȃ��l�ɂƂ��āA���̓��e�́A���X�����I�A�}���I�ɉ߂���Ɗ����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
�܂��A�T���āA���̇��t�@���^�W�[�̂��߂̃t�@���^�W�[���Ƃ����悤�Ȗϑz���E�̉i�v�֊ɂ͍���J�����ł͂Ȃ��A�o���̂Ȃ��NJ��������邱�Ƃ̕��������̂ł���B
����Ӗ��ł͖l�́A����������������ꂽ�ꏊ�ɇ��t�@���^�W�[���Ƃ������́q�J����r���\�z�������킯�ł͂Ȃ��A�������̂��̂������̇��t�@���^�W�[���Ɍ����ĂĂ����ɗV�т������Ȃ̂ł��낤�B
���������Ӗ��ł́u����v�Ƃ́A���������\���Ƃ��Ă̇������ʒu���������Ȃ̂�������Ȃ��B
�����Ō����������ʒu���Ƃ́A�������E����̋����̂��Ƃł���B
�u��������̋����v�Ƃ����Ӗ��ł́A����͉f������y���ɉ�������ǁA���w��G����͂����Ƌ߂��B
�܂�A���̋����̒P�ʂ�<�L����>�̓x�����ł���B
�ʂ̌�����������·��d�͊����̍Č����ƌ����Ă������B
�u�f��(����)�v�͂��Ƃ��Ə�x�̐�������ɂ߂Č����𐳊m�Ƀg���[�X���Ă���B�u���w�v�͒[����\���`�����L�����̂��̂ł���A�ł��ϔO�I�ȕ\���`�ԂȂ����ɁA�t�ɇ������Č����ւ̏Փ��������A�����`�ʂƓ��Ȑ��𗧑̓I�ɋ�g���邱�ƂŇ����A���e�B�[�����l�����Ă����B�u�G��v�̓��A���Ɍ������g���[�X���邱�Ƃ��ł���A���ۊG��̂悤�Ɂu�����Č��v�Ƃ͒��ڊւ��̂Ȃ��ӏ����W�J�\���B
�u����v�Ƃ����\���͂��̗����ʒu�̔��������猋�ʓI�ɇ������g���[�X�̈Ӌ`������O��āA�Ɠ��ȃ����g���A���I�t�@���^�W�[�̕����֗��Ƃ����܂ꂽ�̂ł���B
�Ƃ���ŁA�l�������Ŗ��ɂ������̂́A�Ⴆ�A�u����ł��A����̒��ɂ�����������������i������v�Ƃ����悤�Ȍʂ̋c�_�ł͂Ȃ��B
�ܘ_�A�ꕔ�ɂ̓e�[�}���ɂ���A�f�e�[���ɂ���A�L���ȏd�͊�(�����̏d��)���l��������i�͑��݂���B
�������A���|�I�����̍�i�́A���ꂪ����Ȃ�ɇ����A���e�B�[�������������̂̂悤�Ɍ����Ă��A�Ⴆ���̃G�b�Z���X�����̂܂��l���Ƀt�B�[�h�o�b�N���悤�ȂǂƂ���A�ǂ��ɂ���a���͔ۂ߂܂��B
���ɂ�������s���悤�Ƃ�����A�u�A�L�o�����v�����������ɏo���ʂ܂ł��A����͖��ɃL�b�`���Ȑl���ɂȂ邾�낤�B
�����A�l���l���釀�\�����̉��l�ړx�Ƃ́A�ǂ����Ă��A�����̎��l���Ƀt�B�[�h�o�b�N�����邩�ۂ��A�Ƃ������Ƃ��d�v�Ȃ̂ł���B
���������A���݂̌`���̖���͂��̐��藧���ɂ����ĉf��̕��@�_��Ǐ]���邱�Ƃ��甭�W�𐋂��Ă���B
�L���m����悤�ɁA��O�͊G��������̂悤�Ȃ��̂ł���������ɁA���A��ˎ������f��̍\�}��J�������[�N��������A�Տꊴ�̂�����̂Ƃ����B
���̌�A�������g���[�X���̕������Ƃ��ẮA�u����v�̓o����o�āA���Ȃ��Ƃ����ȓI�e�[�}���ɂ����āu���`�t�v���A�����`�ʐ��ɂ����āu��F���m�v���A���ꂼ��ɖk�̇��d�͊������l�����Ă���B
�������l�́A�Ђ���Ƃ���Ƃ��̕ӂ肪�A���Ė��悪���w��f��ɐ^��������ߐڂ����Ō�ł͂Ȃ��������A�Ǝv���Ă���B
�Ƃ���������͂��̌�A�܂������Ǝ��̌`����ςݏd�˂邱�ƂŁA�f��Ƃ��Ⴄ�A���w�Ƃ��Ⴄ�A�Ɨ��ƕ��̕s�v�c�ȃ����g���A���E���[���h���J�Ԃ������̂������B
�܂肻�������킯�Ŗ��悪���������f��̕��@�_��Ǐ]���邱�Ƃ��甭�W�������̂ł���ȏ�A�l������N���ɂȂ�ƁA���F�A�u����v�Ȃǁu�f��v�̊ȈՏk���łɉ߂��ʁA�Ƒ��v�ɒf�����̂���������ʂ��Ƃł͂������B
�X�ɂ��̍��̖l�̎v�l�o�H�ɂ����ẮA������\�������v�v�f���u���́v�Ɓu�摜�v�ɑ�ʂ��A�͂����Ė���ɂ�����l�[���╶�͕\�����͏㎿�ȁu���w�v�ɔ�r�����邾�낤��?�܂��A����ɂ�����u�摜�v�̎��Ƃ͖{���́u�G��|�p�v�ɑ����ł��ł�����̂��낤��?�ȂǂƁA�v�����点�Ă����B
���_�A�����͎����������B
�l���Ă݂�A�l�̂��̔��z�͉��̂��Ƃ͂Ȃ��A(���₻��ȑΗ����̑��݂���^��ꂻ������)�u���C���J���`���[�v�Ɓu�T�u�J���`���[�v�̃K�`���R�����ł������B
�������Ėl�́u����v�����܂�ǂ܂Ȃ��Ȃ����B
�����Ɂu�f��v��u�G��v��u�����v�ɂ̂߂荞�ނ悤�ɂȂ����̂ł���B
�Ƃ���ł��̎��A�u����v���}�����u���C���J���`���[�v���̑叫�i���A���͖l�ɂƂ��Ắu�|�b�v�E�A�[�g�v�ł������B
�v���A���̓q���l�Ȃ��Ɍ|�p�̃��C���X�g���[���ł���Ȃ���A�j�㏉�߂āu�T�u�J���`���[�v�Ƃ������̂�Ώۉ����A���A�o���M�����h���蓾���u�|�b�v�E�A�[�g�v���A�T�u�J���`���[�̂ЂƂ̏ے��ł���Ƃ���́u����v���쒀����Ƃ�(���Ƀ|�b�v�E�A�[�g�͊��x�ƂȂ��R�~�b�N�����̃e�[�}�ɑI��ł���ł͂Ȃ���)�A�����ɑ����Ȃ��ЂƂ�̏��N�̎v�f�̒��Ƃ͂����A����Ȃ��Ƃł������B
��������L��̂Ɍ����A�N���ɂȂ����l�́u����v�����u�|�b�v�E�A�[�g�v�̂ق����J�b�R�����Ǝv���悤�ɂȂ����̂ł���B
�����ɂ��̂��Ƃ͂���ȊO�̔��p�j�̕��������n���Ă݂Ă����l�ł������B
�Z�U���k�ł��Ȃ��A���l�ł��Ȃ��A�S�b�z�ł��Ȃ��A�S�[�M�����ł��Ȃ��}�`�X�ł��Ȃ��s�J�\�ł��Ȃ��B�B��u�J�b�R�����v�̂́u�|�b�v�E�A�[�g�v�ł������B
�����������́u�J�b�R�����v�Ƃ������l�ړx���u���C���X�g���[���v�͂��܂藝�����Ȃ��B
����A�����͂��Ă��邪����͈Öق̗����ł����āA���Ƃ���Ώۉ����Ȃ��̂ł���B
���鎞��܂ł͎�ɂ����������B�������u�|�b�v�E�A�[�g�v���������́u�J�b�R�����v�Ƃ����v�z�����l��̍����ɒu���Ă���悤�Ɍ������B
���������Ɂu�|�b�v�E�A�[�g�v�̉ߌ����ł���A�����ʂ�A�J�b�R�悳�ł������B
�ł́A�|�b�v�E�A�[�g�́u�J�b�R�悳�v�Ƃ͉����낤?����͌y�����A�ŁX�����A���X�����A�ӎU�L���A�v����Ɂu�y���Ɣ����炳�v�ł���B
�y���Ĕ����炢���̂����������̈Ӗ��𐬂��A�Ƃ������o�͖���̂悤�ȁu�T�u�J���v�ɉ����Ă͓���݂̂��̂ł������B�������A�ЂƂ��сA���̔��M�����u���C���X�g���[���v�Ƃ������ƂɂȂ�ΖႤ�B
���������Ӗ��Ń|�b�v�E�A�[�g�͖{���ł������B
�����Ƃ��A���{�̍������͌����A�E�G�b�g�Ńi�C�[�u������A�|�b�v�E�A�[�g�̂��̊������ǓƂƃX�s�[�h���͖{���̈Ӗ��́u�|�b�v(���ʊ��o)�v�Ƃ����ɂ͗]��ɇ��ٕ����ł��������B
�d�����傩��y���Z���ցB�I���W�i���̃|�b�v�E�A�[�g����͎�����u�ĂāA�l�����߂ă|�b�v�E�A�[�g�̐�������͓̂��{�̕����l����������ȕW���ɂ̂��܂��Ă���^���Œ��������B
�l�͗�����̎v�z�ɂ͂܂�Ȃ������̂ł悭�͒m��Ȃ��B�������A�E�G�b�g�ȍ��������łɇ��y�����ȂǕW�Ԃ���Ƃǂ��������ƂɂȂ邩�c�A���ꂾ���͉������C�������B
�Ƃ肠�����A���f�B�[�E�E�I�[�z��������I�Z�b�N�X�E�s�X�g���Y������I( �w���������҂̌Ǔ��x��ǂ߁I)���ꂪ���y�����Ƃ������̂ł���A���s���A�����Ƃ������̂ł���A���C�����Ƃ������̂��A�Ɩl�͎v���B
����ɂ��Ă��A�|�b�v�E�A�[�g�������̕\�������ɗ^�����e���́A���ꂱ�����Ȃ��̂������B
���͗����90�N��A�l�I�E�|�b�v(�V�~�����[�V���j�Y��)�ƌĂ��|�p�^�����u�����A���̕����������㗲���o�ꂵ���B
�u�A�j���v�敶���̈��̔h�����ƍl����A���x�͑��オ�|�b�v�̕����ɃA�j�����������ꂽ���ƂɂȂ�B
����ɂ��Ă��A�����炭�A���f�B�[�E�E�I�[�z����L�e���V���^�C����������ނɎ��グ�Ă������g���ɋ����͖��������ł��낤���Ƃɑ��āA����̓A�j�����������R�ƃ��X�y�N�g����B
�ƁA�������Ƃ͂܂�A�V��������̃|�b�v�Ƃ́A�p�������C���Ȃ��Ώۂ������ʉ������Ă䂭���̂Ȃ̂��낤��?
������ɂ���A<���C���X�g���[��>��<�T�u�X�g���[��>�̌��E��j��������N���܂����㗲�̎d���A�Ƃ������Ƃ͌����邾�낤�B