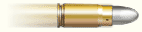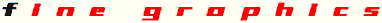Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
ロングテールズFILE;vol.1
映画 『狂い咲きサンダーロード』(1980年公開)
伝説のバイオレンス・ムービー登場!
1980年、あれは私が中学一年の頃だ。友達と新宿伊勢丹近くの東映に劇場版、宇宙戦艦ヤマトの第三作、『ヤマトよ永遠(とわ)に』を見に行った時のことだ。
本編前の予告編が始まり、スクリーンを見詰める私の前に、果たして得体の知れない光景が展開されることとなった。
それは思春期に入りかけの初心(うぶ)な少年にとってそれこそ体感したことの無い鈍い衝撃だった。
凄まじい数の凶暴そうな若者たちが火花を散らすような乱闘をしている。どう見ても役者などとは思われない、暴走族とおぼしき男が台詞とは考えられない言葉をがなり立てている。ブレまくるカメラワーク、つんざくようなギターフレーズ。どうやら肉体的な暴力を描いているようでいて、随所に生々しく血生臭い銃撃戦のシーンがカットバックする。
これは一体何だろう? このとてつもなく〝怖い〟感じは何から来るんだろう? そもそもこれはホウリツを守って作られた劇映画のようなものなんだろうか?
当時の私は何かいけないものを見てしまった気がした。
13歳といってもやや早熟であった私は当時既に劇場通いを初めていて、『マッド マックス』も見ていた。確か『地獄の黙示録』も見ていた。『戦国自衛隊』は大好きだった。つまり、大人の見る激しい暴力描写を含む映画なら一応の免疫を持っていたのである。しかしこの時見たあの日本映画の予告編はそんなものとはまったく違っていた。そんな(幼心にも)冷静に傍観できるような形式化された暴力劇とは…。
その映画、その問題の映画の名前は『狂い咲きサンダーロード』。
少なくとも私はこの映画を堺にはっきり大人の世界に足を踏み入れてしまった。つまり、『宇宙戦艦ヤマト』とは言わず、『スター・ウォーズ』が代表するようなエンターテイメントとしての勧善懲悪ファンタジーにしばらくの間、未練すら失ってしまったのだった。
因みにリアルな"大人の世界"を垣間見た、と言うのはあながち冗談では無い。現にこの映画の本編を(いたいけな胸踊らせながら)観に行った坊やの私はその客層に度肝を抜かれた。大半の観衆が一見してホンマもののお兄さん達だったのだ!! (まあ、とは言えイジメられるようなことはなかったわけですが…当然か。中学生がこんなの見にきて、意味わかるんかなぁ?なんてニッコリされていたのかもしれません)
Biography ― 映画 『狂い咲きサンダーロード』とは何か?
「そこは幻の街サンダーロード。フル・スロットルのバイオレンスで狂い咲いてもイリュージョン…」
「熱とスピードを受けとめろ。ブッ飛ぶぞ…ついてこれるか?」
私に限らず一部の映画フリークの間では半ば伝説化された感のあるこの映画『狂い咲きサンダーロード』は現在も着実に活躍中の石井聰亙監督が、日大芸術学部在学中に撮った(実に!)卒業制作であり、自主製作作品である。
なぜそのような自主製作の映画が一般劇場公開されたのかというと、ご存じの方も多いと思うが、石井聰亙監督はこの作品以前に何本かの8ミリ作品を撮っており、中でも処女作『高校大パニック』は一部の注目を集め、日活で一般映画としてリメイク(名目上は石井聰亙と日活側との共同監督)された。
つまり、そうしたことから『狂い咲きサンダーロード』は当時の東映セントラルの目に止まり、もともと16ミリ作品であったオリジナル バージョンを劇場版35ミリにブローアップして公開されたものである。
因みにこの映画は超低予算ながら1980年度キネマ旬報ベストテンでは9位にランクインしている。
物語は、幻の街サンダーロードを舞台に、主人公、仁(ジン)率いる鉄人暴走族「魔墓呂死(まぼろし)特攻隊」と新道交法施行を契機に「愛される暴走族になろう」と談合する「エルボー連合」、それに魔墓呂死の創始者でありOBである岩見剛(タケシ)擁する政治団体(?)「スーパー右翼 国防挺身隊」らの三つ巴の闘いを描いた(当時、銘打っていたところの)〝ロックンロール・ウルトラバイオレンス・ダイナマイト・ヘビーメタル・スーパームービー〟であった。
まあ、要するに、最凶、最悪を自認する街の吹き溜まりのようなアウトロー達がまさに血で血を洗う抗争を繰り広げるというだけのストーリーである。
スタッフは監督に先述の石井聰亙( 『シャッフル』『爆裂都市』『逆噴射家族』『ユメノ銀河』『五条霊戦記 GOJOE』『ELECTRIC DRAGON 80000V』 )。助監督に、現在はフリーディレクター、また映画監督として『独立少年合唱団』、『いつか読書する日』で海外でも高評価の緒方明。美術監督には撮影現場の「鬼軍曹」的立場として、また挿入曲やメインテーマ等の音楽も務める泉谷しげる。撮影は石井作品の常連、笠松則道(『どついたるねん』)。製作は(後述するが)この映画に出資した、当時の名画座「上板東映」の元支配人 小林紘と、もともと自主映画制作集団「狂映舎」のメンバーとして石井の盟友であり、共同脚本も担当する秋田光彦(現在はお坊様になっておられました)。また、「狂映舎」とは良きライバル関係にあり、この時期の自主製作映画史において『特攻任侠自衛隊』、『戦争の犬たち』という二大金字塔(!)を打ち立てた「騒動社」から飯島洋一と土方鉄人監督が火薬等エフェクト関連のアドバイザーとして、また「スーパー右翼 国防挺身隊」隊員役として参加している。
更に付け加えておきたいのは、やはり「狂映舎」の立ち上げメンバーで、あの自主製作映画のもうひとつの雄『追悼のざわめき』を撮った松井良彦監督が編集助手として参加されているという点だ。
続いてキャストには主演に、当時、劇団『GAYA』の座長を務めていた山田辰夫( この映画の演技により報知映画賞等の新人賞を複数受賞 )。共演に(本作中、唯一、役者らしい役者)小林稔侍。また、この作品に続く石井監督の映画『シャッフル』では主演を射止める中島陽典。この他、主にテレビドラマで活動する役者、南条弘ニやその他『GAYA』のメンバーが脇を固めている。
また、面白いのはスタッフの緒方明や松井良彦が人手不足のため度々エキストラ出演していたり、更に群集シーンでは本物の暴走族が参加したりしていて、当時、話題になったものだ。
私はかつて『狂い咲きサンダーロード』を初公開当時(確か)2、3回、その後各所の特集上映や後に発売されるVHS版等で数え切れない程見る機会を得たが、近年、『石井聰亙作品集 DVD-BOX ~PUNK YEARS 1976-1983~』が発売され、この中に同作品も収録されていることから、実に29年の時を経て、デジタルリマスター版としてチューンナップされたあの『狂い咲き…』を見直す機会に預かった。
月並みな言い方だが、やはり『狂い咲き…』は少しも古びてはいなかった。
いや、それどころか、現在に至って、更に新しい意義とその異様な輝きをいや増しているようにさえ感じられた。
それは決して懐かしさというだけでは済まされない、喚起力と破壊力に満ちていた。
30年目の作品論 ― ウルトラ・バイオレンス・ムービーに寄せて
ではそもそも何が、この伝説的作品の最も特筆すべき点と言えるのだろうか?今日に至るまでこの『狂い咲き…』という作品がこれ程の支持を受け続けている要因とは果たして何なのか?
ここからはその辺りを私なりに考察してみたいと思う。つまり今一度、この作品の魂を雪ぐという意味でも…。
さて、そのことを考えるにあたっては、まず何より、この映画が当時の商業映画界に突きつけた圧倒的な革新性、または特異性を指摘しておかなければならないだろう。なにしろこの作品は多くの点で、それまでの日本映画というもののセオリーから逸脱、いや〝飛翔〟しているのである。
ここではこの映画の欠くべからざる三つの要素を引き合いに出しながら、少しこの〝飛翔〟について考えてみたい。
私が考える、映画『狂い咲きサンダーロード』の特筆点とは…
例えばその一つは、常にこの映画の根幹に付きまとう〈街〉という概念。
そしてもう一つは、音楽的グルーブを基調にした編集センス。
さらにもう一つを挙げるとするならば、そもそもこの映画の〝在り方〟と言おうか、成り立ち自体の中に、当時の形骸化した映画的文脈から飛翔していると思われる要があるのである。
それではまず始めに、この映画における〈街〉ということの意味について考えていこう。
地鳴りする都市 ― シンボライズされた〈街〉
この映画の設定について考える時、まず何より重要と思われるものがある。それは、あながち舞台背景という意味に寄らない、ひとつの〝象徴〟としての〈街〉という概念である。
例えば映画のラストシーンで強烈なカタルシスと共に奏でられる『翼なき野郎ども』。その中で「風にならない都市よ」というフレーズがリフレインされるが、唄っているのは勿論、我らが泉谷しげるである。彼はこの映画において美術監督も務めるが、実はこの映画の〈街〉(都市)という発想は元々彼の持っていたイメージに拠るところが大きい。
石井聰亙はこの映画の監督であると共に、周知のように原案者でもあるわけだが、そもそも彼の発想の原点には泉谷しげる描くところのコミックやイラストのイメージが色濃かったという。
今となっては意外と知られていないかもしれないが、泉谷しげるはフォーク ソングでブレイクする前、漫画家志望だった時期があり、そうしたことから、ちょうど70年代後半当時、『ガロ』や『野生時代』などに作品を寄稿していたことがあるのだ。
これらの作品群は後にいうところのサイバーパンクのテイストが強く、こうしたイメージに触発されて『狂い咲きサンダーロード』のキー・コンセプト・イメージは固まっていった。
例えば当時出版された泉谷の作品集『生き娯楽主義』の中に『Eストリィートのならず者』という短編コミックが掲載されている。これは彼独特のコラージュを駆使した作品であるが、これなどは『狂い咲きサンダーロード』の世界観そのもののように見える。
タイトルの『Eストリィート』というのはブルース・スプリングスティーンの曲『Eストリート・シャッフル』から来ているらしく、石井自身もこの頃のスプリングスティーンに影響を受けたことから、映画のタイトル自体『涙のサンダーロード』という彼のアルバム タイトルにあやかったのだという。
因みにこの『Eストリィートのならず者』というネタは、後の石井作品『爆裂都市』の原案となった。
さて、少し横道に逸れたが、実際の本編において〈街〉は産業用パイプがあたかも魔物の神経器官のように張り巡らすメカニカルな工業地帯の威容であったり、凶気溢れる中にもポップセンス光るグラフィティー(泉谷の手に拠る)や廃棄物の山積する廃墟といったかたちで姿を現す。
なるほど、『狂い咲き…』の世界観を〈象徴〉するビジョンとしては確かに存在感を勝ち取っている。
私は当初からこの映画の本当の主人公は実はあの殺伐とした埃っぽい〈街〉そのものであり、最も純粋な邪悪の意思として確かに生きている〈街〉自体の怨念が主人公に憑依し、やがて「街中の奴ら全員ぶっ殺してやる…」とつぶやかせる、という構図を夢見たものだ。
事実、「地鳴りする都市よ」( 『翼なき野郎ども』 )と唄われることと呼応するように、劇中でもあの暗黒の〈意思〉は、(自らの「生」を表明するかのように)随所に低く呻くバイブレーションとして胎動し続けている。
また、こうした、それそのものが〝生命体〟を思わせる〈街〉のイメージは、同時にこの映画におけるメカニカルなものの象徴としての〈バイク〉のイメージにも換喩される。
この事は例えば『キネマ旬報』1980年9月上旬号寄稿の山根貞夫氏の評が言い得ている。
「ズズズズと響く地鳴り、火山の噴煙、赤茶けた山肌に転がっているオートバイ ― 石井聰亙の『狂い咲きサンダーロード』は、そんなタイトル前のシーンからはじまる. 転がっているオートバイと書いたが、正確ではない. 画面からの印象にそくせば、そいつは転がっているのでなく、横たわっているという感じなのだ. なにか奇怪な一匹の生きものの、死んで横たわっている姿….ことにその半身がアップになったときのエロチシズムが、そう思わせる. 草も木もない、赤茶けた岩と石ばかりの山肌なので、大写しになるマシーンの構造の入り組んだ形とにぶい輝きが、生命の残映を感じさせるのにちがいない. ふつうの意味の動物ではなく、たとえば近未来のメカニカルな生きものの、死んで横たわっている姿….この映画のすべては、ここに象徴されていよう. ざらざらに荒廃した世界のなか、メカニカルな無機質化を強いられた生命体の狂おしい疾走ぶり、そしてその果ての死が、この映画の描くものだからである」
もっともこの映画に於いて〈街〉という概念こそ主題の中核を成す、という提案は実は自明である。
なぜなら、この映画のタイトル自体に他でもない、『サンダーロード』という〈街〉の名が冠されているではないか。
『サンダーロード』とは言うに及ばずクライマックスの大殺戮が繰り広げられる都市の名である。
そう言えば、この『狂い咲きサンダーロード』という作品は「日本に於けるサイバーパンク ブームの先駆けの一つである」という評を以前見かけたことがあるが、この所見はまさしくあのメカニカルであり、かつ荒廃した工業地帯を背景に使ったことと、設定を実際、〈近未来〉に置いたことが大きいと思われる(因みに〈近未来〉を具体的に表すために単にスプレー缶で1986とか1987と書き殴っているあたり、こうした稚拙な荒っぽさはこの映画に於いてのみ絶対に正しいのである…何故か…)。
アンビバレンスな葛藤 ―〈リアル〉と〈ファンタジー〉そして飛翔!
さて、この物語の背景としての〈街〉がこの世界観の紛れもなく〈象徴〉であることは解った。しかし、ここで我々は奇妙なことに突き当たる。と、言うのも、その最も重要な設定の根幹を成す筈の〈街〉のデテールが、本作劇中に於いて殆ど語られないのである。殊にこの街の成り立ちやシステム、運営の在り方など一切説明されることはない。
例えば当時の泉谷しげるのインタビューに次のようなものがある。
「よくあんだろ、暴走族の映画に. 社会が悪くて、親がダメで、学校教育がコーハイしてて、屈折の果てに一気に発散てパターンが. 石井の映画の場合、架空の都市ン中で暴走族がちゃんと市民権得ててね. だいたい革ジャン暴走族しか出てこねえんだから. きちんとしたカッコしてるヤツらは景色としてチラッと出てくるだけ. 片スミの青春って描き方してないもん. 着眼点、オモシロイだろ」
この言説にしろ既にこの〈街〉を巡る世界観の奇妙さを指摘したものである。
なぜ「革ジャンを着た連中」が市民権を得ているのか?
こうした謎は他にも例にいとまがない。
例えばなぜ主人公達は廃墟に暮らしているのか? なぜ『幸男』が殺された時、自分達で焼いたのか? なぜ『マッド ボンバーのおっさん』に「金持ってんのかよ」と聞かれ、あれ程の武器を買えるだけの金を『仁』は持っていたのか? 第一、『仁』達は仕事をしているようには見えないけれど普段どうやって暮らしていけたのだろうか? などなどである。
さて、実は私には、ここまで読んで頂いた読者の方の声が聞こえるような気がする。
つまりこうである。「それはこの映画が目指すところがファンタジーに過ぎないからだ」と。
しかし私はこう答えたいのである。
「問題なのはこの映画がファンタジーに見えないことだ」と。
そう、この映画に限っては如何に通俗的なファンタジーの文脈を読み取ろうとしたところで、肝心のその風貌がどうしてもファンタジーに見えないのである。
この映画の手触りとは決して凡百の「空想世界」が生み出すひ弱なものではない。
リアルと言おうか、生々し過ぎるのである。
暴走族も右翼も売春宿の女の子達に至るまで、全てが本物に見える。役者が演じていると思えない程にである。しかも何とアンビバレントなことに、背後にあるもの、舞台設定としてのバックボーン〈街〉、がこれ程までに、ご都合主義的ベール(ファンタジー?)に包まれているのにである。
一言で言えばこれは〈コンセプト〉と〈表象〉の分裂状態と評してもいいだろう。
更にこのことは、舞台設定(=空間)という問題に留まらず、この映画の歴史観念(=時間)というものを考えた場合い、より明白となる。
主演の山田辰夫は石井聰亙に初めて会った時「石井さんは道路交通法改悪のことで物凄く怒っていた」と語っている。「走れなくなった奴は一体どうすればいいんだ」と。
言うまでも無く、この時代(1970年代後半)のそうした現実がそのまま着想として『狂い咲き…』に取り入れられて行った。
無論、物語のセオリーとして同時代の問題意識を一見、遠くの何者かに託すという、いわば説話法とでも呼ぶべき機能があるにしろ、ここで石井監督以下若いスタッフ達が選んだ問題とは、余りに卑俗に過ぎる「今」であった。
この感性、呆れるほど刹那的で即物的な認識世界。老いさらばえた者が「若さ」と表現するところの突出した感受性がたまたま異様な情熱で捉えた1970年代末の「今」は、信じがたい程の〝生の空気〟をフイルムに刻印してしまった。つまりそれがこの作品の本物っぽさ(リアリティー)である。
しかし一方で、彼等は強烈にファンタジー(センス・オブ・ワンダー)をも希求している。
例えば、観客にとって仁たちの物語は一体、いつの時代の出来事と解すればいいのだろう?
一見、70年代末の空気が息苦しい程に凝結しているかに見えるこの世界は(スプレー缶一本の魔法によって)実はパラレルな構造を持つ、我々の世界と異なる次元の物語なのであろうか?
一方で過剰なまでのリアリティーを獲得しながら、奇妙にも強固な匿名性を前提に持つ世界。
仁たちのアジトで、健と典子の屋根裏部屋で、仁が忠の見舞いを受けた病院の部屋で、岩見剛と茂のベッドで、正にこの、全ての時代から閉ざされ、隔絶されながらも、すべからく70年代そっくりの世界。
これが『狂い咲きサンダーロード』が我々を幻惑する秘密である。
そう、概してこの『狂い咲きサンダーロード』という映画の魅力とは、このアンビバレンス!このアンバランス!不可解さ!
1970年代末の〈道交法〉なのに〈近未来〉だというパラノイア的状況、これこそが『狂い咲きサンダーロード』の〈怖さ〉の本質であり、くしくも
、日本映画に於ける特異点、あるいは定形からの〈飛翔〉なのである。
もっとも、言い方を変えれば、本質的に自由なのに、本物の外観を持つ世界?それこそ映画の醍醐味と言わずして何であろう。
定形からの脱出!〈アクション〉ではなく〈暴力〉のために…
さて、ここまで物語の受け皿としての〈設定〉を考えてきたところで、今度はそこにおさまるべきもの、つまり直接的にスクリーンに描き出される表象としての肉体がどんな身振りを見せたか…、この点について少し検証してみたい。
ここで再度、泉谷しげるの発言を引用することになるが、実は彼は当時、『狂い咲きサンダーロード』のスポークスマン的な役割りを担っていて、かくいう私も、主にラジオなどから流れてくる彼の言葉に耳をそばだてたものだ。
はっきりとは憶えていないが確か『林美雄のパックインミュージック』か何かでの発言だったような気がする(更に蛇足になるが、当時、私はオールナイトニッポンよりもパック イン ミュージック派で、今は故人となられた林美雄氏の放送では、『ユア ヒットしない パレード』というコーナーで、『狂い咲き…』 の挿入曲を提供している『パンタ&HAL』に声援を送ったり、また『狂い咲き…』本編の紹介などもされていたことを記憶している. 更にこの番組内であったか、『狂い咲き…』の予告CMというものを私は聴いている.ナレーションは何とあの広川太一郎!! 『電光石火に銀の靴』をバックに、「幻の街、サンダーロード街に鉄人暴走族がやって来た!」というものだった)。
泉谷氏曰く…、
「普通、撮影で車を走らせる場合、かなりスローな速度でスピード感を表現するものなんだが、この映画では100キロ以上のスピードを平気で出していた…」と、そんな意味の発言である。
また、こんな発言もあった。
「学生のやることは恐ろしいよ.例えばバイクでアクリル板に突っ込ませて、破片が足に突き刺さっても気にしないんだ. 俺らは一応、大人だから安全だけはっていうのあるけど、彼等は全然考えていないからね」
更に主演の山田辰夫の発言でこんなのもある。
「バカだと思いましたね. 死ぬよって思いましたもんね」
どうやらここで多くを語る必要はなさそうだ。要するにそれ迄の日本映画に較べてマシンのスピードが違う。アクション シーンの危険度が違う。いわば〈被写体の物理的身振り〉そのものが違うのである。
私はスクリーン上の体験の中で〈型〉としてのアクションではなく、本物の〈暴力〉に近いものをここで初めて観た気がした。
実際に役者は捨て身で演じている。
特に圧巻なのはやはり冒頭の仁達が『ストリートファイアー』に殴り込んで来るシーンと幸男を取り戻すために『デスマッチ工場跡』で大乱闘を演じるシーンであろうか。群集劇でありながら凄まじいばかりの疾走感である。
殊にこれらのシーンにおいては後述する〈編集思想〉と合間って、劇中の事物が疾走するというに留まらず、映画そのものが疾走していく感を強くさせる。
無論、この「疾走」、「躍動」によって何が生み落とされるかというと、それこそ石井監督の術中、〈ビート〉である。
『オレは、スタッフに言った. 「ロックしているかい? ロックしているかい?」 』(公開当時のパンフレット掲載の石井監督の談話)
本来、ロックに〈型〉が存在しないように映画『狂い咲きサンダーロード』に合理的な殺陣(たて)は存在しない。なぜなら〝制御不能のエネルギー〟こそこの映画唯一のテーマであり、この危うさ、言い換えれば緊張感が、結果的にこの作品を日本映画の歴史に於いて唯一無二の存在にしているとも言えるのだから。
グルーブ発生装置としての〈編集〉―その先の「体験映画」
さて、そろそろこの辺りで話を〈音楽的グルーブを基調にした編集センス〉に移して行きたいと思う。
ところで何故、私はここで〈編集センス〉などという曖昧模糊とした言葉を使っているのかというと、私はこの『狂い咲きサンダーロード』という映画における〈編集〉の〝発想〟とは、それ迄の日本映画を考えた場合い、非常に特筆すべき点を含んでいる、と思っているからだ。
私が、今になってこそ改めて感嘆させられるのは、この映画が公開された当時はまだ『MTV』さえ存在していなかったという事実である(因みにMTVが開局したのは映画公開のちょうど翌年であるらしい)。
あらかじめ端的に言えば、私は『狂い咲きサンダーロード』の〈編集〉における要点、または最も特徴的なポイントとは、〈グルーヴに対する感性〉にあると思っている。
勿論、グルーヴとは音楽用語であり、本来映画のつくり手が、ストーリーやテーマを語ろうとする時に便宜上駆使するというようなものではない。
JAZZで言うところの〈スウィング〉。レゲエで言うところの〈バイブス〉。ロックで言うところの〈グルーブ〉。大括りにしてしまえば〈ノリ〉とでも訳してしまおうか。
つまり、この映画において〈編集〉とは、決して物語を整頓し、効率的に語るだけのものではない。いや、それ以上に重要視されているのはカットとカットの切返し(繋ぎ)が生み出すところのあの純粋なカタルシスである。
例えば優れた楽曲(演奏)が時を刻むことで、そのセンスとタイミングの妙技によってグルーヴ感(カタルシス)を生み出すように、ここでは本来「映画」が抱える〈編集〉というものの合理性は遥かに肉体〈ビート〉化されている。
もっとも、全ての映像の編集には最低限、一定のリズムを要する。展開を円滑に説明するために韻を踏む必要があるのである。
ところが、『狂い咲きサンダーロード』においてはこの「韻を踏む」という行為が単なる必要としてだけではなく、一つの快楽システムとして「目的化」されているのだ。
いわばこの映画のこうした〈編集〉の妙技が生み出すところのグルーブ感はまるで音楽そのもののようである。
「『狂い咲きサンダーロード』の試写の時も、俺の隣の学生なんて、最初の30分間、体を揺らして見てるんだよ. 押されちゃってるというか、体に訴えられてる. それを観て"あっ、これはいけるな"と思った」(泉谷)
繰り返しになるが、これは未だ『MTV』が生まれる前の、しかも日本映画界における出来事である。
逆に言えば今でこそ、ハリウッド映画をひとつの典型とし、良くも悪くも、こうした直接感覚に訴えるような刺激的な編集技法は研究され、また主流になっているとも言えよう。が、一方で、こうした今日的な映像文化を育む原点となったものこそ、かく言う、80年代に勃興するMTVカルチャーなのである。
当時、石井監督は、確か『地獄の黙示録』や『2001年宇宙の旅』を引き合いに出しながら「体験映画」ということを語っていた。
「体験映画」とは、つくり手が自らの体験に基づいてつくる映画のことではなく、観客に「体験」したかのように感じさせる映画のことだそうだ。そしてこれからは正にこの「体験映画」の時代に入って行くのだ、とも…。
少なくとも私はこの時期の日本映画陣営にあって、これ程的確に、その後の映画文化の向かうところを言い当てた発言はないと思っている。
もっとも、それもその筈である。当時、既に行き詰まりを見せていた大手配給会社系のイマジネーションなどからこれは決して生まれ得ない発想だったのだから。
つまりそれ程までに、この映画の立脚点とは、当時の日本映画的状況から極北であり、また前衛的だった、ということなのである。
衝撃の〈音楽映画〉!そして〝アンチ・ロック・オペラ〟
さて、奇しくもここまで『MTV』というものを例に出してきたのであるならば、やはりこの映画の音楽の使い方について触れないわけにはいかないだろう。
無論ここまで語ってきたように、ある種、この映画の〈編集思想〉には、既に音楽と似た構造を有する、という前提もあるのである。
殊にこの映画『狂い咲きサンダーロード』ほど、音楽というものの使い方において衝撃を与えた作品もなかったであろう。
つまり、これ程までに映像と音楽が〈同期〉した作品も他になかった。
この映画は挿入曲の殆んど全てがいわゆるボーカルもので、BGM扱いの曲というのはごく限られている。つまり体裁としては「音楽映画」のようなものだとも言える。例えば『ロッキー・ホラー・ショー』のような…。
しかしこう語り出したとき、私はいささか口ごもってしまう。
確かに映画史の類型を見渡した時、直ぐに連想される形式としては『ロッキー・ホラー・ショー』や『フラッシュ ダンス』や『フットルース』のような「音楽劇」、いわば〈ロック・オペラ〉のようなものを考えてしまう。しかし断じて違うのだ。
というのも、『ロッキー・ホラー…』のような映画というのはかつてのミュージカルの形式をあらかた出ていないわけで(って言うか『ロッキー・ホラー…』自体は完全なミュージカルだ)、これはちょうど、物語と曲がキャッチボールし合う関係に似ている。これに対して『狂い咲き…』の場合はあくまで曲と物語が〈同期〉し合っているのである。それも主従の見分けもつかない精度でお互いを補足し合うかのように…。
この意味では既存の『音楽映画』というよりは昨今の「MV」のようなもののほうに手触りが近いかもしれない。
つまり、映像が音楽との折り合いを計算するのではなく、そもそも音楽使用の発想が極めて映像的なのである。
また、「ミュージック・ビデオ」とは本来、〈楽曲〉と〈映像〉の掛け合いバトルのようなもので、お互いの持ち味を闘わせながら、結果、ある未曾有のグルーブへ誘おうとするものであるから、ある意味、音楽と映像の果たし合いと見ることもできる。この点『狂い咲き…』においてもこの緊張関係は作品の隅々に至るまで充満し、また、非常に豊かな邂逅を果たしている。
ところで、映画を構成する要素の中で、音で時を刻む〈音楽〉に直接対応し、かつ、最もコミットするものとしてはやはり〈視覚空間で時を刻む機能〉としての〈編集〉が担っているわけだが、そう言う意味から私はこの映画の〈編集〉と〈音楽〉を関連付けて語っている。
しかし、『狂い咲きサンダーロード』の映像の何と音楽的なことか…。同時にその音楽センスの何とイマジネーティブであったことか…。
大切なことはそうした点からも、この作品がその後の〝ある種の表現〟の発端であったかもしれない、ということなのだ。少なくともそれに自覚的であった一部の人たちにとっては…。
偉大なる邂逅!『泉谷しげる』×『パンタ&HAL』
さて、先を続けよう。この映画で使われている音楽の大半は既存のアルバムからの徴用である。
フィーチャーされているアーチストはこれまで度々言及してきた『泉谷しげる』それに『パンタ&HAL』と『THE MODS』である。
このうち『THE MODS』に関しては、当時、活動停止中であった森山達也が石井たちから楽曲提供を依頼され、急遽、スタジオメンバーを集めて録音したという、この映画唯一のオリジナル・トラックを使用している。が、しかしやはりこの映画のスピリットとも言うべき〝ロック魂〟を体現してやまないのは『泉谷しげる』と『パンタ&HAL』の既成楽曲の方であろう。もっとも当時、音楽使用の面でこの映画が最も衝撃を呼んだのは、この〝既成楽曲〟を使っているにも拘わらず、あたかもオリジナル・サウンドトラックに聞こえるほどの〈ハマり方〉にあったのだから当然と言えば当然である。
まずは『泉谷しげる』からだ。1970年代前半、フォーク・ブーム全盛の中、アルバム『泉谷しげる登場』でデビューし、ご存知『春夏秋冬』でブレイクした泉谷しげるはその後、俳優業にも進出しながら、音楽性としてはかなり早い段階からロック色を強めてゆく。そしてこの映画『狂い咲きサンダーロード』が制作される70年代後半頃には、まるでトム・ウエイツを連想させるようなハードでブルージーな独自のロックバラードを得意としていた。
『狂い咲き…』の使用楽曲としては何と言ってもオープニング・タイトル曲「電光石火に銀の靴」(アルバム『光石の巨人』に収録)。タイトル・バックの1、2、3、4とカウントされてから一気に雪崩れ込むあのグルーブのるつぼは、バイクの疾走がブレたままストップモーションするオープニング・クレジットとあいまって、私の中の「クールなもの」のひとつの尺度になってしまった。
また、石井監督をして「この曲は『狂い咲き…』の象徴」と言わしめたエンディング・タイトル曲「翼なき野郎ども」(アルバム『'80のバラッド』に収録) 。特にあの「とびきりの女に会いに行こう」というフレーズは私の中の侠気ナンバー史上、何をおいても〝永久欠番〟が決定しているのである。
この他にもアルバム『都会のランナー』から「俺の女」、「王の闇」、「ハーレム・バレンタインディ」、「揺らぐ街」、「君の心を眠らせないで」、アルバム『光石の巨人』から「テスト ドライバー」、「遥かなるセーヌの畔に」、アルバム『黄金狂時代』から「眠れない夜」、「火の鳥」、アルバム『光と影』から「国旗はためく下に」といった強力な楽曲の数々が、それこそ弾丸のように繰り出されるのがこの映画の真骨頂であった。
本題から少し離れるが、同時期に泉谷が関わった自主製作映画としては『戦争の犬たち』(公開時期が近いが、当然、フレデリック・フォーサイス原作の同名映画とは無関係)がある。この映画は石井組の対抗馬にして良き協力団体、『騒動社』が製作したものだが、ここで彼は出演と共にやはり楽曲を提供している。実はこの映画の音楽センスも誠に素晴らしく、「旅から帰る男たち」に始まり、エンディングは「褐色のセールスマン」、挿入曲に「綱引き」を起用するなど、(『狂い咲き…』では漏れてしまった)アルバム『都会のランナー』からの名曲2曲を全面に押し出した選曲には唸らされた。因みにこれもどうでもいいことだが、泉谷はこの頃『ガロ』にこの映画の小編〝ノベライズ・コミック〟を寄稿していて、こちらもかなりイイ味を出していた。
さて、『泉谷しげる』とは一味違った意味で、この映画にある種〈時代の空気〉を与えたアーチスト、それが『パンタ&HAL』である。
『パンタ&HAL』は『頭脳警察』のパンタ(中村治雄)がグループ解散後数年のソロ活動を経て結成した本格派の音楽ユニットである。80年前後の音楽シーンにあって、欠くことのできない潮流〈ニューウエーブ〉の胎動を『狂い咲きサンダーロード』に刻印した功績が大きい。
音楽的には密度のあるサウンドと完成されたアレンジ、また、パンタの『頭脳警察』時代とは打って変わった硬質にして奇妙にファンタスティックな歌詞など、魅力溢れる編成であった。ギターに今剛を起用したり、プロデュースに鈴木慶一を招いたりと、今から考えても非常に贅沢なユニットであった。
既に先述したが、この『狂い咲きサンダーロード』という映画には本質的に、非常に「リアル」な要素と「ファンタスティック」な要素が二律背反的に共存している、という件だが、音楽の面では泉谷しげるが「リアル」な面を、このパンタ&HALが「ファンタスティック」な面を、それぞれ体現しているように私には思えるのだ。
使用楽曲としてはアルバム『1980X』から「ルイーズ」、「トウ・シューズ」、「臨時ニュース」、「オートバイ」、「IDカード」、アルバム『マラッカ』から「つれなのふりや」。
最も印象的だったのは仁(ジン)が病院を退院する幻想的なシーンで使用された「つれなのふりや」だろう(未だに気になっているのだが、仁たちの背後で修羅場っている一人があの暗黒舞踏のギリヤーク尼崎氏であろうか?)。当時、私も自宅でこれを爆音でかけ、とんでもなく近所迷惑なことであった。
また、走れなくなった仁が想像の中でバイクを駆る、これも幻想的なシーンに流れる「オートバイ」や「街中の奴ら全員、ぶっ殺してやる」のタイミングで流れ出す「IDカード」などなど、印象的なシーンを彩った曲の数々であった。
因みに個人的には『狂い咲き…』使用曲以外にも「ブリキのガチョウ」、「裸にされた街」、「ネフードの風」、「極楽鳥」、「Audi80」、「トリックスター」、「キック・ザ・シティ」などパンタ&HALにはハードローテーションでお世話になった曲が数多く、もはや血肉になっていることは言うまでもない。
私はかつて、これらの挿入曲をせっせと買い集め、記憶だけを頼りに(当時はビデオも無い時代だったので映画館でしか劇中の曲順を確認しようがなかった)自力で『狂い咲きサンダーロード』のサウンドトラック(テープ)を作成したものである。
嗚呼、懐かしきかな、我が青春の〝自主制作〟サウンドトラック…。
ま、というわけで、この辺りで〈編集思想と音楽使用の相関性〉に関してもよしとしよう。
表現を巡る戦争ごっこ―〝現場ありき〟の〈自主製作映画〉
さて、拙文ながらここまで長々と語ってきた映画『狂い咲きサンダーロード』の本編解説というか作品論だけれども、最後にこの映画がこの映画たるためにとりわけ重要と思われるポイントを指摘し、ひとまずこの項の総括としたい。
結局のところ私がここで最も問いたかったことというのは、果たして『狂い咲きサンダーロード』という映画の何が、今なお、これ程までに異質な存在たらしめているのか、ということの一点であった。
純粋に映画の問題としてどんな構造がこの映画に備わっていて、またそのことが観客である我々をどんな地点に誘おうとするのか…。
あらためてこれを考えるには、かつて私がこの映画を初めて見た時感じたあの何とも言えない奇妙な感じ、これを思い返してみると案外的を得ているかもしれない。
この映画は果たして法律を守ってつくられた〈劇映画〉のようなものなんだろうか?
つまり、あの時、〈劇映画〉という「制度」では何か割り切れないものをこの映画に感じていたということになりはしないか?
では、本来的な〈劇映画〉の収束点とは何であろう?
それはとりもなおさず「虚構」というものを〈映画的形式〉の中で消化し、無論、純粋に観念上の産物でありながらも、その向こうに一点のリアリティに至る…。
つまり、こうしたものが本来の〈劇映画〉だと定義するならば、この『狂い咲きサンダーロード』という映画は少しばかり様相を異にしている。
少なくともこの映画の場合、〈映画的形式〉を通り抜けた上でリアリティーに通じているのではない。
〈映画的形式〉を積み重ねた上で観念上の本質論に至るのではなく、そのリアリティーは何の脈略も無く始めから存在しているのである。
そしてそれはほとんどドラマツルギーによる真実味ではなく、「現場」のリアリティーなのである。
「現場」とはつまり、物語のこちら側の物語ということであり、その〈臨場感〉ということだ。
端的に言うと、この作品は、創作された映画的虚構という構造の以前に、紛れもなくひとつの〈ドキュメンタリー〉として機能しているということである。
映画と時代と狂熱をめぐるある種の記録映像…。
それは『狂い咲きサンダーロード』という〈暴動〉の映画をつくるために現場に集まった〝規格外集団〟の熱くはかない妄想と疾走の記録であり、その寒く、痛く、埃っぽい現場の息づかいをこの作品は余りにリアルに刻印してしまったということだと思う。
確かに16ミリでオールロケで光量不足で…と、今となってはテクニカルな意味での〝ドキュメンタリーっぽさ〟を演出する要素は揃っている。しかしこの作品の生々しさは決してそんなことだけではない。
元助監督の緒方明氏が今回発売の『石井聰亙作品集 DVD-BOX 1…』の中で、当時、石井監督は、映画はライブだ、という発言を度々していたけれど、自分はこの考え方自体は好きではない、と告白しておられたが、(若干意味は違うかもしれないが)私は結果的にこの発言は『狂い咲き…』の強みを言い得ていると思う。
無論、定石で考えれば、こうした虚構を差し置いて湧き上がる現場的リアリティーなど早い話、下手と紙一重であり、まず成功するはずも無いものである。しかしだからこそ、それで映画史にアイデンティファイされている点、この映画の類いまれな素養が浮き上がっているとも言える。
結局、『狂い咲きサンダーロード』という映画は以前から述べているように、ことごとく奇妙な二重構造によって成立しているようである。
ファンタジーでありながら生々しいリアリズムの映画、虚構でありながらドキュメント的側面を併せ持つ映画。こうしたアンビバレントな要素が相互にフォーカスしあう仕組みがこの映画の最大の魅力なのではないだろうか。
また、繰り返しになるが、そんな多面的ファクターを併せ持つこの映画の中でも、殊に私は、この映画の〈現場〉のエキサイティングな息づかいを伝えている部分に着目したい。
何故ならそれこそが、あの時代に一瞬間、眩しく瞬いた「自主製作映画ブーム」の偽らざる本質を体現しているように思うからである。
そう、あの頃の「自主製作映画ブーム」とは果たして何であったか?例えばこの問に私なら一言で答えよう。
それは、〝表現を巡る〈戦争ごっこ〉〟であった、と。
この点がそれ以前の寺山修司や大林宣彦、その後の伊藤高志のようなファイン・アート志向(実験映画)のそれとは決定的に異なっている。ノリとしては「イメージフォーラム」ではなく「PFF」であり、彼等はあくまで劇映画をベースにしていた。そのため芸術性や技術の巧みさよりも生命感を重視し、下世話でポップな肉感性をもって最大の武器とした。
勿論〈戦争ごっこ〉であるならば〈現場〉にしか意味は無い。泥だらけになりながらエキサイトし、狂い咲くのがサバイバル・ゲームの常道だからである。
そういう意味で『戦争の犬たち』などを例に持ち出すのは図式化に過ぎるだろうか。
もっとも、必然的にも彼等の制作環境を考えた時、自主製作陣営とは常に〝この一本で玉砕する〟という覚悟で映画製作していたわけで、そもそも職人監督でさえ毎回、次はもう撮れないかもしれない、情況の中で張り込む大博打こそ実質、映画なわけだから、ましてや彼等に至っては、勢い、そのテンションたるや〈戦争〉となるのである。
ところで、言うまでもなく〈戦争ごっこ〉をこよなく愛するのは男の子のほうである。だから実際、当時の上映会の客層やつくり手側を見ても圧倒的に男ばかりであった。
『狂い咲き…』本編に至っては登場人物自体に女性はほんの端役程度で、しかも典子のように男を弱体化させる形骸化された存在としてのみ機能させている。きわめつけはヒーローに『うるせえんだ、このどブス!』などと言わせる始末である。
要するに〝男騒ぎの〟自主製作映画ブームであった。
もっとも、現実の中に架空の世界を想定し、その幻影の中に生き、走る行為、という意味に於いては全ての映画、または映画人の意匠とは〈戦争ごっこ〉に違いはないのだが。
つまり、元来、限られた撮影所システムの中だけに許されてきた映画製作という密かな遊戯が、やがて「自主製作」という表現的制約の無いかたちで解放された時、そこには創ることそのものの生の快楽がシンプルに浮かび上がってきたというわけである。
善し悪しは別として、この頃の自主製作映画の主導権は必然、つくり手の方にあったと思う。つくり手側のパワーがまさっていたというべきか。
「実際にはできないと思うけど、観客に作れる、作っちゃおうかな、という気にさせる. 歌手と同じで、俺でもできるんじゃないかなって気にさせるね. 誘ってくれる、とでも言うのかな. そういう気分にさせてくれることを求めて劇場で1500円払うこともあるから」(泉谷しげる) 『キネマ旬報』1980年9月上旬号
そう、このコメントにあるように、当時の自主製作映画には何か〝映画をつくる〟ということそのものの快感を観客に体感させるようなところがあった。
〝始めに〈映画〉在りき〟だったのである。
そして、このことが当時の私のような映画少年達に非常に大きな影響を与えた。
そう、かくしてクリエイティビティの芽は撒かれたのであった。
'80年代製石井映画の遺伝子
例えば私の個人的経験からこの辺りの影響を語らせてもらえるなら、当初、中学生であった私は、やはり『狂い咲き…』の影響などからモデルガンにはまったり、バイクの免許が取れる年齢になると真っ先に中型免許を取得し、自慢のGSXで〝ジンさん〟よろしく街を疾走したりしていた。
しかし、年齢を重ねるごとにますます映画への想いが高じた私は、ついに1本だけ、自分の映画を撮ってしまったのだった。
勿論、大学の卒制(!)である。
約50分のモノクロ、16ミリで、石井組と同じようにフイルムや機材はほとんど大学から支給されたが、二人だけ頼んだプロの役者(主役)のギャラや細々した経費はアルバイトでまかなった。
ただし、当時の私は既に少しばかりすれていて、ジム・ジャームッシュだのゴダールだのベルトルッチだの…、出来た映画はなんだかヌーベルバーグにかぶれたような、とぼけた観念劇みたいなものになってしまった。
しかし、本当のことを言えば、何よりかつての『狂い咲きサンダーロード』とその周辺の自主製作映画体験こそが私に、どうしても一度は映画を撮ってみたい、と思わせた最大の要因であったことを今なら正直に告白できる。
さて、私の個人史は別として、その手の主観レベルの話で言えば、石井聰亙の初期作品が後の、殊に自主製作映画に与えた影響というのは自覚的か否かは別として、私の印象の範囲では度々感じることがあった。
例えば塚本晋也の監督作『鉄男』を初めて見た時、私は石井聰亙が映像史において発明したエッセンスの凝縮を感じた。
はっきり言えばこの映画がこの当時、寡作であった石井本人の作でないことが信じられない程に…。
むしろそれゆえか否か、出来は素晴らしいものであった。しかし、結局、この映画は石井聰亙とサム・ライミのテイストをかけ合わせればこうなるという実験標本を見せられた気がした私は、実にこの秀作を愛しきれないわだかまりを感じたものだ(そういえば、塚本晋也が石井聰亙と同じ日芸出身ということに何か因果関係があるのかどうか私は知らない)。
その後、長い時を経て『ELECTRIC DRAGON 80000V』を観た時、作品としては、今やかつての『鉄男』などに比べると幾らか凡庸ながらも「これぞ本家!」との感慨を憶えたのは私だけだろうか…。
また、この他にも例えば福居ショウジン監督作『ピノキオ√964』を見た時は、あの救いの無いパンキッシュな人造人間ものの世界観に、どことなく『アジアの逆襲』(石井聰亙が『爆裂都市』の後に撮ったビデオ作品)を連想したし、はたまた園子温監督作『部屋 THE ROOM』を観た時は深く感銘を受けながらも、無性に『シャッフル』への想いが胸をよ切ったりした(今回、DVDボックスが発売されるまで、実質、この作品を観る手立てはなかっただけに、余計…である. 尺が30分そこそこながらこの『シャッフル』という作品は石井監督作ベスト1の呼び声も高いのだけれど、実は私も石井作品の、いや、ひょっとすると自主映画史の中の最高傑作かもしれないなどと考えていたりする. タランティーノ、これ、観ているのかなぁー)。
さて、そういうわけで、ここ迄、幾つかの角度から検証してきた私なりの『狂い咲きサンダーロード』論であるが、如何だったであろうか?
兎にも角にも私にとっては非常に重要な〈事件〉と言っていい作品だっただけに、どこまで客観化出来たかははなはだ疑問である。しかしある程度はこれまで自分にとっての懸案であった問題意識を整理できたのではないかと思っている。
それでは最後に幾つか捕捉的に考察して、ここは閉めるとしよう。
『狂い咲き…』における笑いのメカニズム
憶えている人は憶えていると思うが、当時、作品の中に右翼団体など現実の政治的構図を登場させたことに対する一部の批判があったと思う。
パワフルでアナーキーな純粋衝動を描いたこの映画に背伸びした政治もどきのエピソードはかえって水を差すというのである。
しかし私の考えでは、これは単に「若者は大人の状況などに捕われず若者らしくあれ」と言っているに過ぎず、この映画の実情からはかけ離れている。
実態は、一切の政治的構図〝に見えるもの〟はすべからく凍り付いた〈笑い〉に収れんされているからである。
岩見剛が「君が代」を口ずさみながら登場したり、藁人形に向かって突撃したり、彼等がホモセクシャルであったりと、これらはもはや我々の視線が「民族主義思想」などに向かうはずもなく、単に〈狂気の表象〉としてしか機能していない。同時にこの世界ではこうしたものは嘲笑のアイコンとして処理されるようである。
つまりこの議論は、当時の、あらかじめ政治や思想に期待する世代としない世代の認識の差異を表していたように思う。
第一、既に述べたように、この世界は私達の世界とは少し違う「5分後の世界」かもしれないのだ。
だとすれば仮に『スーパー右翼』なるものがどことなく現実の(任侠系)右翼に似ていたからといって、この虚構の中の歴史がどうして我々の知っている大日本帝国と同じものを擁していたと言い切れよう。
最もこの指摘、〝取って付けたような政治的メッセージ〟への疑問符は石井監督の次作、『爆裂都市』に於いては私もかなり頷ける。つまり私はこれと『狂い咲き…』は全くの似て否なるものと考えているのである。
なお、石井監督がATGで撮った『逆噴射家族』はこの凍りつく笑いのブラック・センスを自覚し、コントロールできるようになった一つの成果と考えられる。
〈フリークス〉〈不具者〉そして暴動!
今更言うまでもなくこの映画は〈暴動〉と〈反逆〉の物語である。
ところで、このどちらの要素もベクトルとしては低い方から高い方へ向かうものと決まっている。
初期、石井聰亙の描き出す世界は『狂い咲きサンダーロード』に限らず、社会をドロップアウトした人間達のるつぼ、アウトローどもでひしめいている。
しかし、この最下層の社会にあってさえ更に力の順列が決められ、また抑圧される者は凶気の牙をむく。
私はこの辺りの構図に石井聰亙の〝元祖サイバーパンク〟たる所以があると思う。
また同時にサイバーパンクとしての必須条件、〈異形のもの〉=フリークスに対する固執も、お馴染み石井映画のお家芸と言っていい。
挿入曲「トウ・シューズ」の中でパンタが唄っている。
「捨てられた うす汚れたトウ・シューズ
誰が捨てた ひき裂かれたトウ・シューズ
うらぶれた街角で猫にじゃれつかれてるトウ・シューズ」
私は『狂い咲きサンダーロード』とはすなわち、打ち捨てられた者達だけで構成されたアウトローの世界から更に打ち捨てられた主人公が、必然、その世界のもっと奥地、フリークスの世界にわけ入り、彼等の力を借りることで自ら〈異形のもの〉の王として復讐する物語だと考えている。
だから「風にならない都市よ なぜ俺に力をくれる」(『翼なき野郎ども』泉谷しげる)という問いの答えははっきりしている。
それは『仁』が襲撃によって右手、右足を切り落とされることで〈不具者〉という名の〈異形のもの〉へと変化したからである。
つまり『サンダーロード』という街は最も苦痛と恥辱と狂気をたずさえた者、すなわち〈フリークス〉にこそその暗黒の力を与えたのであった。
幻のダイナマイト・スラング映画
『狂い咲き…』における〈リアリティー〉の問題はこの映画を考える上で最も重要な要素として以前にも語っている。しかし、これに関してはもう一つだけ触れておかなければならない点がある。それはこの映画の言葉の使い方である。
表象的な部分で『狂い咲き…』に大きな真実味を与えている要素、それは一般的な劇映画では考えられない程、いわゆるスラングが多用されているという点だ。
当時の座談会で石井監督は「あれでも遠慮した」「もっとどんどん使いたかった」と語っているが、実際、この映画は過激できわどい口語表現が極まったかたちとしては日本映画史において比類がない。
また、こうした特異なダイアログが精製された過程については今回発売のDVD-BOXの中で、かなり山田辰夫のアドリブであったことが明かされていて興味深い。
シナリオ段階では仁の性格付けはもっと寡黙な人物だったそうである。
それと、もう一つ面白いのは、さすがに音感の良いこの映画だけあって、会話も一種の音として捉えている点だ。
ほぼ一貫して群集劇であるこの映画は会話の展開の中に野次りや雑音のような周りの声をかぶせることで、映画の宿命である説明的な観念性から逃げているのだ。
私の知る限り、少し似た音の試みを行っている映画に大林宣彦監督作品『北京的西瓜』がある。
しかし、これはどちらかというと実験的色彩が強く、本来『狂い咲き…』が目指す形式破壊の〝必要〟ではなく、それが〝目的〟化している点、かなり意味合いは違っている。
血戦!東映大泉撮影所
この映画のクライマックスと言えば何と言っても全身黒ずくめの特攻兵器として〝再生〟された仁が、たった一人で〝街の秩序〟という名の強権政治を相手に戦争を仕掛ける、あの大殺戮シーンのことである。
あの頃の一般劇映画としてはこれは正に辛酸を極め、その血と硝煙のにおいは、本来〈アクション〉というには余りに〈暴力〉であった。
仁の〈マシン〉を想わせるいでたち、殊にジェット・ヘルにモトクロス用ゴーグル・マスク、それに闘いの根拠と痛みを伝える右手のフック(映画『ローリング・サンダー』から着想し、助監の緒方明氏が大泉撮影所のゴミ捨て場から拝借し、再利用したという)等の小道具の使い方も最高にロックでありこの上なくクールなものであった( 因みにこのファッションに起因する件で一部から、この作品が、やはりこの当時公開の『マッドマックス』に酷似しているという言いがかりを受けたことがあった. しかしこれは石井監督自らによって繰り返し完全否定されている.その根拠として、単純に、撮影時期からいって盗用不可能であったということなのだが、しかし私などに言わせると、そうした言を待つまでもなく、そもそも『マッドマックス』のポスターで使われているあの問題のスタイルは復讐シーンでマックスが身に着けているわけではないし―あれはグースがバイクに乗るシーンでウエアとして身に着けているだけだ―、また〈暴走族映画〉というカテゴリーの相似にしても、オーストラリアと日本の社会的背景が余りに違い過ぎるため、厳密に言えば、あの映画の『アウトライダー』達をいわゆる〝暴走族〟と訳すこと自体、無理があるのだ. 強いて言えばあれは端から犯罪を目的としたギャングスターに近いものだと思う)。
さて、少し話をもとに戻すと、このシーンは東映大泉撮影所の取り壊しが決まったセットを使って行われたことは有名だが、実はこれを巡って当時、〝辛い〟評価が幾らか挙がっていたことをご存知だろうか?
例えば、先にも引用させて頂いた『キネマ旬報』誌上での山根貞夫氏の評や、あの長谷川和彦監督なども当時、この点については苦言を呈しておられたようだ。
ではそれらがどのような批判であったか、要約すると、作品のパワー溢れる前半部に比べて決戦に至る後半は、形骸化された日本映画(例えば東映ヤクザもの)のパターンに集約するかのようなチープさが目につく。つまりこの作品の出自が自主映画ということも含めて、本来、既成の映画スタイルに〈反逆〉すべきもののはずが、ああした陳腐なセットの使用によって、自らの闘争を安いつくりものの世界に押し込めてしまった、というような趣旨であった。
実は私もこの意見は少なからず的を得ていると思う。
というのも、私自身、当初からこの作品を何度か見るうち、全編通しての〝反映画的〟とも言える先鋭的でアナーキー(孤高)な印象に対し、確かにこの後半部分の純映画的、図式的展開については、実際、微妙な違和感を憶えなくもなかった。
指摘のように〈本物らしさ〉が売りのこの映画にどことなく既成映画の〝つくりもの臭さ〟が漂うのはこのシーンが唯一である。
純粋に映画評論的立場としてはこれはなるほど正論であった。
しかし同時に、それでも私はこのシーンを生理的に嫌うことができないばかりか『狂い咲きサンダーロード』と言えばやはりこのシーンがエンブレムのように連想されることを否定もできない。
第一、あの『サンダーロード』の代替えとしてどんな『サンダーロード』があり得たのであろうか?
例えば私は本公開以後、幾度となく場末の名画座で『狂い咲き…』を見たけれど、その度に必ずと言っていい程、観客のどよめく笑いを聞いた。それは〝過剰なもの〟に対する笑いであった。「バっカだなぁ~」の笑いであり、「目茶苦茶だよ」の笑いであった。
無茶を無茶とも思わず画として具現化してしまうエネルギー。拙さや不完全さや泥臭い記憶までも飛び去る風景として横目に認めながら疾走してゆくパワー。私はこれがあの血戦の場面だと思う。
仮にあのシーンを大泉撮影所の取り壊し寸前のあのチープなセットを使わず前半部のような廃工場などのロケで行っていたとする(勿論、仁と茂のあのマカロニ・ウエスタンを思わせる一騎打ちも存在しなかったことになる)。しかしそれでは余りにスマートであり、本気でクールに過ぎるから、その結果、『スーパー右翼』のくだり等が妙にバカ気て見えて(政治性を持ち込むなんて不遜だ!などと言ったりして)、やっぱりこれらも削ることになったとする。するとその必然、観客の〝過剰なものに対する笑い〟は起こらなくなり、すなわち、これはもう私の知っている『狂い咲きサンダーロード』ではないのである。
それはもしかすると、案外、洗練されたドキュメンタリー調のハードボイルド映画であり、当然〈戦争ごっこ〉の〝キング〟などでもないから、『騒動社』の〈宿敵〉ですらないかもしれない。
確かにこれはこれでATG的〝過激な青春譚〟として悪くないのかもしれない。しかし、私はことこの作品において、このパラレルな『狂い咲きサンダーロード』を選ぶ気にはなれないのである。
勿論、こういうのは映画論的態度ではないし、この文の冒頭に記したような私の個人的刷り込みの影響を多分に含んだ見方なのかもしれない。
しかしそうであっても、例えば長谷川和彦監督の『太陽を盗んだ男』において、あれ程の時代的リアリティーとシリアス極まるテーマを持ちながら、これと裏腹なデテール ― いきなり原発に潜入してプルトニウムを強奪したり、ロープ一本でターザンよろしく奪還したり、はたまた数十メートルの高度のヘリコプターから飛び降りたり、やたら銃撃されても死ななかったり― こうした一見、人を食ったような劇画的展開、奇想天涯な二律背反こそこの作品を底知れぬ眩惑(硬質のリアリティーが次第に主人公の心象風景に変容してゆき、やがて観客は全ての実存的手がかりさえ失ってゆく)に誘っているとは言えないだろうか?
だとすればこの〈リアル〉と〈ファンタジー〉の変転の不可解さ、面白さ、あるいは自由度というものにかけて、この作品もまた『狂い咲き…』と相似形を成すものと考えられるのだ。
こうした意味で、とは言わないが、やはり私にとって『狂い咲き…』の決戦の場とは『東映大泉撮影所』と決まっているのかもしれない。
連想 ―『特撮ヒーローもの』から『鴨川つばめ』まで
ところで、このクライマックスの決闘シーンを徒然なるままに思い巡らせている私はふと、あのバトル・サイボーグを思わせる仁のいでたちに、東映は東映でも〈東映特撮ヒーローもの〉のにおいを連想してしまうのだが、これはそもそも私とこの作品との邂逅が13歳の頃だったことに拠るのかもしれない。
あのつくりもの臭い人口的なセットを背景に、悪の手によって〝改造〟を施され、復讐の鬼として立ち上がった男の闘いは〝正義のため〟ならぬ〝ロックンロール・スピリットのため〟に繰り広げられるあたり、当時の私の自我の萌芽に見事ハマっていたとも考えられる。
壮絶な死闘の後、鈍く黒光りする傷んだ筐体を晒して、バイクで走り去るあの後姿の残像に、きっと私はリアル『仮面ライダー』を見ていたのかもしれない。
それと、こういう連想で言えば、私はあの頃、どこか『狂い咲き…』とダブらせて読んでいた大好きな漫画があった。
それは『ドラネコ・ロック』という作品で、あの鴨川つばめが『マカロニほうれん荘』を『週刊少年チャンピオン』誌上で連載していたのと同時期に、月刊の方で描いていた〝暴走族もの〟のギャグ漫画である。
これは一口に言うと、鴨川つばめ版『天才バカボン』とも言えるもので、なぜ私が『狂い咲き…』とこの漫画を関連付けて愛読していたのかというと、まず、主人公が「ワイルドキャット」という暴走族グループの〝副番長〟で「泉屋しげる」(!)という名であったこと(『天才バカボン』のバカボンパパに相当するキャラが「泉屋おやじ」という)、また主人公達と付かず離れずの関係を演じるファンキーな警官コンビ(シュトコのマッポ)「ウルフとジョー」が、権力との取引によって「エルボー連合」をまとめ、めでたく交通警官となった「久米と氏岡」のチンピラ警官コンビを彷彿とさせること、などであった。
鴨川つばめは『マカロニほうれん荘』にしてもそうだが、当時のハードロックそのもののスピードとビートの感性を漫画に取り込んだ唯一の作家であったが、考えてみれば、これはそっくり映画界における石井聰亙の立ち位置をも示しているわけで、こうしたことがどことなくこの二つの孤高の作品をオーバーラップして見せていたのかもしれない。
1980年をめぐるアート・シアターの潮流
思えば、『狂い咲きサンダーロード』が公開された1980年当時というのは日本映画界に於いて非常にドラスティックに新しい感性が胎動し始めた端境期であった。
具体的に言えば、あの頃、アート・シアター・シーンにおいて少なくとも4つの潮流が存在し、後に開花する潜在的な才能を数多く温存していた。
その一つめは『ATG(日本アート・シアター・ギルド)』が、1960年代から牽引役を果たしてきた〝独立系プロ〟 ( 大島渚の『創造社』や今村昌平の『今村プロ』に代表される) 主導の映画製作に替わって、独自の製作・配給体制を確立していったという流れだ。
そして二つめは『 日活ロマンポルノ』やその他の〝 ピンク映画〟と呼ばれる土壌であり、そこでは常に、ゲリラ的に〝活動屋魂〟がふつふつとくすぶり続けていた。
また、三つめは、70年代中盤から台頭してきたいわゆる『角川映画』。出版と映画をタイアップさせる〝メディア・ミックス商法〟を武器に、キャスティングとしては大作主義的なスターシステムを敷きながらも、徐々に新しい監督達の起用で、作品としての評価も納めていった。
こうした中、更に旧来の固定観念に染まらぬ新たな創造の萌芽と呼ぶべき〝第四の流れ〟があった。そう、それこそが今回取りあげた石井聰亙や『狂映舎』を取りまく〈自主製作映画〉という名のフィールドであった。
もっともこれら各々の流れは決して相互に没交渉であったわけではなく、監督を始めとするこの時代の映画作家たちは自らの出自に関わりなく、それぞれ入り乱れ、越境し、交流しながら、やがてはいわゆるアート・シアター系、メジャー系などというような垣根すらも曖昧化させてゆくのだった。
かくいう、私もこうした80年代初頭の日本映画シーンの空気を思いきり吸って育った世代である。
例えばあの時代、相米慎二が『翔んだカップル』で鮮烈にデビューした。大森一樹が『ヒポクラテスたち』で青春群像劇に新たな風を吹き込んだ。また、森田芳光が『家族ゲーム』でメロドラマを解体してみせ、高橋伴明は『TATTOO[刺青]あり』で等身大かつ最も普遍的な破滅劇を描きだした。
無論、この他にも『ねらわれた学園』の大林宣彦がいた、『遠雷』の根岸吉太郎がいた、『ガキ帝国』の井筒和幸がいた、『人魚伝説』の池田敏春がいた。更に後の影響から言えば、『日活ロマンポルノ』においてこの頃、石井隆が『天使のはらわた』シリーズを盛んに〝執筆〟していた。
また、こうした、当時黎明期の〝若手〟陣営に加えて、あの衝撃の〝清順歌舞伎〟『ツィゴイネルワイゼン』と共に大復活を遂げた鈴木清順や、岡本喜八、それに実相寺昭雄や若松孝ニ、神代辰巳、寺山修司などなど、あの一癖も二癖もあるようないぶし銀の名匠達がこの頃まだ現役の牙を研いでいたのである。
あの頃の日本映画の〝熱〟に思いを馳せるにつけ、やはり私は今日の〝映画環境〟を幾らか比較せずにはいられない気持ちになる。
しかしだからと言って私が特に今日の状況を悲観しているというわけではないし、第一、あの当時と今を単純に比べることなど余りに難しい。とにかくその後、余りにも色々なことが起こり過ぎたのである。
まあ、それはともかく、実はあの当時も日本映画界全体の斜陽化は、かなり決定的なところまで進行していた。
にも拘らず、あの作家層の分厚さ、そして何より、それを〝映画と呼ぶ以外の何ものでもない表現〟が今日よりずっと普通に存在し得た時代。それはやはり映画界に於いて少なからず〈至福の時〉と言い得たであろう。
因みに、私の感慨としてはこの辺の〝熱〟が一段落ついた感があったのは、ATGの終焉は勿論であるが、なんといってもあの『ディレクターズ・カンパニー』の倒産劇が決定的であった気がするのだが如何だろうか…。
〈自主製作映画〉借景 ―回想の『上板東映ファイナル』
さて、いよいよこの項をもって本『狂い咲きサンダーロード』論もお仕舞いとなるわけだが、ここまでなんやかやと書き記してきた最後に私は、ある牧歌的情景の中でこの小論の幕を閉じたいと思う。
それはしごく個人的で小さな記憶だけれども、私にとっては忘れ難い思い出の風景である。
1983年12月、年の瀬も押し迫ったある日、当時、高校一年生だった私は、なんというか、幾分疲れた佇まいを見せる「上板橋」の街並みをひとり歩いていた。
その日、『上板東映』という場末の名画座で催される「さよなら特集上映会」というものを観るためだった。
〝さよなら〟と冠されているのは、実はこの旧弊の映画館がこの特集上映会を最後に閉館してしまうことを意味していた。
しかも私は『上板東映』の〝実物〟をその時、初めて見た。
当時の私がその名を聴くだけでも、殆ど聖地のように感じていた自主製作映画の〝殿堂〟は、私の想像を遥かに超えるような〝場末風味〟の外観を湛えていた。
『上板東映』…その読んで字の如く、東映系列の一上映館でしかないその名前が私の記憶にしっかりインプットされたのは他でもなく、『狂い咲きサンダーロード』のエンド・クレジットにその奇妙な名を見つけた時からだった。
果たして、上板橋を〝カミイタ〟と中途半端に略しているこの変な映画館とウルトラ・バイオレンス・ロックンロール・ムービー(何でもいいが…)との間にどんな関係が?という私の素朴な疑問は程なくしてあっさり晴れることになる。
実は『上板東映』は資金面で『狂い咲き…』の製作をバックアップしていたのである。
つまり、自主製作映画に対して単独で支援を買ってでる映画館!ボスは小林紘支配人という。
兎にも角にもあの『狂い咲きサンダーロード』をつくった映画館と氏の名前は、当時わけのわからぬ映画少年の私にとって、それだけで最高にRock!であった。
ところで、こうやってもっともらしく書き始めたけれど、この時、一体どうやって私は『上板東映』の最終興行を知ったのか?また、ニ週間程の特別興行のうち、一日だけ詣でたのか、何度か通ったのか?実際、どんな作品をフィーチャーしたプログラムを観たのか?など、細かいことは殆ど憶えていない。ただ何となく憶測できるのは、確かこの時、松井良彦監督の『錆びた缶空』(石井聰亙が撮影を担当した自主映画)だったか、土方鉄人監督の『特攻任侠自衛隊』だったかを観た気がする、ということぐらいだ。
つまり、私がここで書きたいのは、そうした上映内容云々のことではなく、実はこの時、ようやく生身の〝神様〟たちに出会えた!という思い出なのだ。
但し、これは不思議なことだが、現在、私の手元に残る、当時のプログラム代わりのリーフレットの何処にも〝神様〟たちが降臨(来館)する旨は記されていない。
シチュエーション的にはオールナイト上映だったような気もするから、もしかすると飛び入りのサプライズだったのかもしれない。
しかしともかく間違いなく、この時、私は〝最オーラ期〟の神様たちに出会った。
あれはこれから映画が上映される幕間であったと思う。
確か初めに小林紘支配人がスクリーン前の舞台に上がった。とうとう上板東映もこれが最後の上映になった、というような短い挨拶の後、順番に、土方鉄人監督、石井聰亙監督、そしてなんと『狂い咲きサンダーロード』主演の山田辰夫さん(特に仕事以外で人前に出ることは稀であるということだった)が登場されたのだ。
この時の土方鉄人監督の挨拶は今でもよく憶えている。かつて石井監督所属するところの『狂映舎』と土方監督の『騒動社』とで人気投票形式の〝バトルロイヤル〟をやったのが一番の思い出である、という趣旨の内容であった(これは今でも一部の事情通の間では語り草になっている逸話だが、私はこの挨拶で初めて、以前、そういうことがあったのを知ったのだった)。
さて、次に、この小論のテーマ的にも最重要問題の石井監督の挨拶であるが…、実は監督は当時、とても照れておられて、あまり挨拶らしい挨拶はされなかったのだった。
また、これは山田辰夫さんも同様で、何か一言二言しか話されなかったと記憶している。ただし、あの何とも言えずはにかんでおられる姿はかえってスクリーンで見ていた氏のイメージそのものであり、私には強烈な印象として今でも残っている。
それと、この挨拶と共に、何と言ってもこの時の楽しい思い出として忘れられないのは、ファン・サービスの一貫として、石井監督の当時の新作『アジアの逆襲』のサウンド・トラックを購入された方に石井監督からサインのプレゼントがある、というものであった(『アジアの逆襲』というのはビデオ作品で、このサントラを、石井監督自らヴォーカルをとる期間限定ニューウエーブ・ユニット『バチラス・アーミー・プロジェクト』が制作していた. そういえばこの時、確か『アジアの逆襲』本編の上映もあったと記憶しているのだが、やはりこれもプログラムには記されていない. するとこれもやっぱりアドリブ的なサービスであったのだろうか?)。
勿論、私はこのささやかなサイン会に参加した。
〝神様〟を前にしてガチに緊張する私に「名前は?」と聞いた石井監督は「えっ?」と二回聴き直し、「たかし君へ」と書きかけた後、三回目にようやく「か」と「し」の間に「は」を入れて「たかはし君へ」としてくれたのだった。
そういう訳で私の『アジアの逆襲』サウンド・トラックLPには「上板東映の星 聰亙 たかはし君へ 1983.12.20」と刻印されることになったのである。
それともう一つ、この時の貴重な戦利品としては、騒動社製作『戦争の犬たち』の業務用非売品ポスターというのがあった。
これは劇場の売店で「『戦争の犬たち』のポスターって買うことできませんか?」と尋ねる映画小僧の私におじさんが「そう?欲しいの?それは鉄人(テムジン)さん喜ぶなぁ~」と言って、その辺のポスターを無造作に剥ぐと、売り物じゃないけどもう使わないから、と譲ってくれたものである。
つまりこのように、この『上板東映ファイナル』というイベントは少し寂しいながらも端々にとても暖かいファンへの感謝に満ちた催しであった。
考えてみれば、上板東映が関わってきた多くの映画、無論『狂い咲きサンダーロード』にしても『戦争の犬たち』にしても、それ自体はとても凶暴で攻撃的なものの筈である。にも関わらず、この時私が触れた、そこに関わっている人々の感触とは、どこか素朴で気さくな優しさを秘めた男たち、という印象であった。
当時、小僧の私ははっきりとは解らないながらも、何かものをつくるということは例えその主張がどういうものであれ、基本的にポジティブで、本質的に明るいことなのかもしれない、などと感じていた。
全ての映画が終了して、やがて席を立とうとする頃、劇場側から、これから「養老の滝」のほうで石井監督など作り手の方を交えて席を設け、楽しく歓談などしたいと思います。ついてはできるだけ多くの方にご参加頂きたいので、もしも持ち合わせが…という方は当方で考えさせて頂きます。お気軽にご参加ください、というアナウンスが入った。
これから閉館してゆく映画館に金銭的余裕などあろう筈もないことぐらい、子供の私にもわかった。
つまりそういうところが『上板東映』の生き方だったのかもしれない。
ところで、私はどうにも、石井監督以下〝神様〟たちの語る映画談義を間近で聞いてみたかったが、「養老の滝」というのは酒を飲むところか、持ち合わせも無いし、まさか未成年者が借りるわけにも…と、まさしく後ろ髪引かれる思いで劇場を後にした。
帰途路の、見知らぬ上板橋の街並は何故か少しほろ苦く、心細いような心持ちであった。
さて、一本の映画なり作品の魅力について様々な言葉を労することは可能である。
今回もこの『狂い咲きサンダーロード』という映画について自分なりに様々な角度から、また、できるだけ記憶の糸をたぐるように考察してみた。
だが、にも関わらず、必ずしも私はこの映画の魅力の本質に肉迫できたとは思わない。
私の記憶の中の『狂い咲きサンダーロード』はまるで〝幻の楼閣〟のようである。
そもそもこの映画は長い間、その本質について語ることが非常に難しかったように思う。最も言葉にし難い一種の〝生命力〟のようなものが魅力の本質と考えられていたせいかもしれない。
何れにしろ、一個の作品についてその本質を見極めようとすることとは、とりもなおさず〝一種異様な執念を持ってそれを見続けること〟、これに尽きると思うのだ。
結局、この熱く醒めた視線の中にしか、表現の表現たり得べき出自の謎を解き明かす手だては無いのである。
(一部敬称略とさせて頂きました)
さて、何とかこれで私なりの〝積年の落とし前〟、あの『狂い咲きサンダーロード』という映画への総括を終えたところでめでたく次回へ…。
此れにて一件落着!