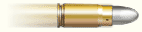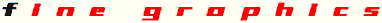Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
ロングテールズFILE;vol.32
死狂ひ錦絵、見参!月岡芳年VS
日本近代絵画のパイオニア!川村清雄
僕が小学校5年生くらいの頃、家の近所のおばさんが趣味で油絵を描いていて、そのおばさんが絵を教わっている先生のところへ、僕も少しの間、習いに行っていたことがある。
習うと言っても、結局、僕はスケッチブックに漫画ばかり描いていて、まともに絵らしい絵など描くことはなかった(僕と同じに習いに行ってた同級生は、生真面目に水彩画なんか描いてたな)。
この画家先生はもの静かな、非常に人当たりのいいお爺さんで、僕が鉛筆で漫画しか描かなかろうと何をしようと、いっこう気にせず、あれこれ指図するようなことも全くなかった。
ただ、子供のやりたいようにやらせ、自分はその横で、せっせとパイプを吸いながら、いつもこじんまりしたサイズのキャンバスに、何だか抽象的な油彩画を描いているのであった。
今思えば、あの先生の画家としての素姓は全くわからないけれど、しかし、あの強烈なテレピン油の匂いと、常にラジカセからローテーションしていた越路吹雪のシャンソンだけは、今でも強く印象にとどめている。
★
さて、僕だって、美術教科書でお馴染みの高橋由一や黒田清輝や横山大観の絵なんかを観ると、それはそれは美しいものとは思うけれど、しかし、常々、素朴に思うのは、「洋画壇」とか「日本画壇」なんて言い方はどうも気持ちが悪いし、例えば、「具象」とか「抽象」なんてカテゴライズも、実際、無意味だし、変に派閥めいていて、どこか官僚的だと思う。
考えてみれば、1960年代くらいまでの日本の〝画壇″の葛藤なんか端からわかっちゃいない、初めからもう無国籍同然の人種が僕らなのだ。
加えて、僕に言わせれば、そんな、日本人とも呼べない日本人の、ほぼ外人並みの客観視点で見た場合、ダントツ面白く、圧倒的にカッコいい、日本固有の絵画とは、大陸由来の狩野派以上に、何と言っても浮世絵だと思うのだ。
ジャポニズムというキャッチフレーズでよく知られるように、ゴッホやモネが浮世絵に惹きつけられ、蒐集したり、盛んに模写したりしたのは有名である。
これが何故かというと、元々、西洋古典絵画というのは、即ち写実表現オンリーであったが、写真の発明、進化に伴い、次第に絵画から、視覚領域の客観的再現性、いわば〝記録媒体″としての重大な意義が薄れていった。ちょうどこれに呼応する形で、「印象派」のような、それまでの写実表現に留まらない、新たな表現形式が模索され始めたのである。
単に写実性に寄らない、全く新たなものの見方、感性を探求していた当時のゴッホやモネが、よりによって〝形式化″の世界的極北としての日本の浮世絵に出会ったら、それはひっくり返る程の衝撃を受けても無理からぬことだ。
〝リアリズムの精度″を競っていた時代から、〝様式の独自性″に価値を転換しつつあった彼らが、たまたま独特の歴史環境に培われた、究極とも呼べるオリジナル表現に出会った、というのがことの核心である(大体、世界美術史において最初に浮世絵を〝発見″したのは当の日本人ではない。クルトという、ドイツの美術史家が東洲斎写楽を、レンブラント、ベラスケスと並んで「世界三大肖像画家」と賞賛したあたりが発端であったと言われている)。
ただ、こうした西洋側の事情から見た歴史的前提をよそに、無論、日本サイドではこれと180度正反対の〝葛藤″が日本美術界に巻き起こったわけで、黒船・開国以来、西洋美術によるビジュアル・ショックが常に、我が国のメイン・カルチャーを席巻し続けたのであった。
また、これを起点として、前述の画壇の〝派閥問題″が幕を開けたわけでもある。
そういう意味では、(とても卑近な例だが)僕あたりの浮世絵との出会いも、この混乱をなぞるかのように、少しばかり紆余曲折があった。
どういうことかというと、思い返す限り、僕が最初に浮世絵というものに強い魅力を感じたのは(もう20年以上も前)、実は小林清親 (1847/弘化4年ー1915/大正4年)という絵師の作品を知った時だった。
小林清親というのは明治期に名を馳せた、中でも特異な手法で知られる浮世絵師である。
当時、「光線画」などと形容された、非常に叙情味のある陰影表現を多用した人で、彼の作品は、それまでの浮世絵には殆ど見られなかった、革命的な手法を取り入れたものだった。
どう革命的なのかといえば、要は、何のことはなく、文明開化によって解禁された西洋の陰影表現や、リアルな遠近法をいち早く、また、見事な洗練度で、既存の浮世絵のフォーマットに落とし込んだ、というものであった。
小林清親の作品は美しいといえばこの上なく美しいし、また、現代的な僕らの感性に寸分無理無くフィットしてくるあたり、殆ど驚嘆に値するわけだが、ただし一方で、これは何処まで行ってもやはり、浮世絵の魅力の本筋ではないことも事実であった。
つまり、僕にとっての浮世絵の入り口とは、何ともはや(邪道とは言わぬまでも)、件の、洋の東西の潮(うしお)の合流点にのみ存在した、全くの特異点であった。
言ってみれば当時の僕は、浮世絵のような最も日本固有の文化らしい文化にすら、西洋美術のフィルターをかけたかたちでしか感情移入できなかったことになる!
実はこんなことにも、我が国の歴史の一筋縄ではいかない事情の一端を、多少なりとも垣間見る気がするのである。
ところで、ウィキペディアを見ていたら、開国後、日本美術界の再編纂に多大な影響を与えた美術史家のフェノロサは、日本の絵画の特徴を次のようなものだと語ったという。
・写真のような写実を追わない。
・陰影が無い。
・鉤勒(こうろく、輪郭線)がある。
・色調が濃厚でない。
・表現が簡潔である。
ちなみに、村上隆が2000年に企画した展覧会のタイトルは、『スーパーフラット』展という。
これも日本の絵画表現の伝統的属性(西洋絵画のような〝厚み″を持たないこと)に着目し、「平板」というキーワードによって、我が国の国民性を端的にアイデンティファイさせた造語なのである。
さて、僕が小林清親という変則的な入り口を経て、いよいよ本家「スーパーフラット」な浮世絵の魅力に目覚めたのは、それから数年後、ちょうど、篠田正浩監督の映画『写楽』が公開されたり、写楽 = 斎藤十郎兵衛説が定説と言われ始めた頃であった。
実はたまたまその当時、父親の実家を家捜ししていたら、初代歌麿、勝川春章、歌川国芳、歌川国周などの浮世絵が出て来て、町田市立国際版画美術館に持参したことがきっかけであった(もっともこの時、発見した浮世絵は、研究素材としてはそれなりに面白いものもあったらしいが、ただ、摺りが甘く、保存状態も今いちだったことから、価値としては大したことはなかった。知っている人には常識だが、絵師にもよるが、浮世絵というのは、版木が鋭利な試し刷りの100枚程度が最も高価なのである)。
思い返せば、この頃以降、僕は始めて真剣に浮世絵というものを考えるようになり、その結果、実はこれこそが唯一、世界中に類似するものの無い、完全無欠のメイドイン・ジャパンなのではないか?と思うようになった。
小林清親の親しみ易い叙情味もいいが、実は写楽大首絵の、荒々しく削ぎ落とされた簡潔さの中にこそ真に恐るべきものがあることを知った。
ある時は〝進歩″のための模倣が非常に重要であることは言うまでもないが、しかし、決して万能でなくとも、孤りのびのび、切磋琢磨することの内に、既にして王道があることを痛感させられた。
一見、いびつに見える過剰な形式としての浮世絵は、思想も方法も、あらかじめ閉ざされ、欠落した中からこそ突出した独創が生まれた好例である。
実はこうした出自のものに、ある種開かれた模索を続けたヨーロッパの人々が、逆に驚嘆させられた事実には、やはり皮肉なものを感じずにはいられない。
最近、僕は、二つの展覧会を観た。
浮世絵太田記念美術館で開催された『没後120年記念 月岡芳年』展と、江戸東京博物館で開かれた『維新の洋画家 川村清雄』展である。
まず、月岡芳年(1839/天保10年ー1892/明治25年)というのは、僕も大好きな江戸後期の天才絵師、歌川国芳の弟子にあたる人で、先述の小林清親と並んで、明治期を代表する浮世絵師の一人である。
芳年がことに有名なのは、西南戦争などの合戦図や、新聞に依頼されて描いた、事件報道(挿絵)などの、常軌を逸した血みどろさ具合いだ。
彼は他にも、師匠、国芳譲りのダイナミックな歴史画や武者絵、美人画なども見事にものにしているが、しかし芳年独特の境地、といえば、やはりあの残酷絵の世界だと思うし、また、歴史背景を考えた場合、それは報道のリアリズムという意味合いで、当時、情報革命時代の要請でもあった。
さて、芳年の作品が一堂に会する希少な機会である『没後120年記念 月岡芳年』展は、3分の2も観れば既にお腹いっぱいになるくらいの凄まじい情報量であった。
明治頃の浮世絵を通称「赤絵」というが、毒々しいまでの原色の色彩と、毛筆タッチの描線の洪水!!
観客を力でねじ伏せるような密度とバイオレンスの幻想世界がどこまでも広がっていた。
観ていてヘトヘトになるようでもあるが、ただ、それでも最後まで観ずにはいられない、底知れぬ磁場を発しているかのようであった。
例えば、浮世絵あたりが「漫画」の元祖、なんていうけれど、芳年に至っては日本の漫画というより、カラーリングといい、ダイナミックな構図といい、ほとんどマーベル・コミックなんかのアメコミに近いと思う。
殊に国芳や芳年の作品には、僕は、何か他とは違う、暴力的なまでの〝エッジ″を感じる。
それまでの錦絵が持つ牧歌性を極端に排し、そこには現代に通じる極彩色の刺激と、何よりスピード感がある。
そういう意味では芳年の作品には、師匠の国芳より、何か達者というのと違う、突出した過剰なもの、異形性を感じて、よりマニアックである。
バランスとしてはもはや崩れているわけだが、逆にそういう辺りこそ、むしろ現代の僕らからみれば滅茶苦茶かっこよく、カッティング・エッジ!なのであった。
何しろそれはあの、カルト・マンガを思わせる、神経症すれすれの、独特の描線を観れば感じる筈だ(実際に芳年は、晩年、神経症で病没している)。
ちなみに、僕は浮世絵師が描く肉筆画も大好きだけれど、やはり何と言っても、版木職人の超絶技巧によって下図をトレースし直されることで生まれる、全く独特の風合いにこそ、絵画表現としての、唯一無二のアドバンテージがあると思っている。
浮世絵という表現形式とは、独立した個性というのではなく、実は技の三位一体なのであった。
蛇足になるが、世の中にはたまに、この浮世絵の作風をそのまま踏襲したような〝タッチ″が存在する。
イラストや、時には美術の世界においてすら、そんなものを見かけることもある。が、しかし、どうも僕は、〝パロディ″というのは好きになれない。
先達のスピリットをどのように今日的に消化するか、と模索することには共感できるけれど、しかし、過去のフォーマット(方法論)をそのまま持ってきて、単に現代的なテーマに当て嵌めてみました、みたいなスタイルには正直、閉口する。
そういうのは単なる技術論であって、表現姿勢としては、どうも不遜に思われるからだ。
時代の形式というのは、その時、息づかざるを得なかった痛ましさ、そこにこそ意味があり、魂がある。
後になって、それらを俯瞰したつもりで、ちゃっかり形式だけ戴く、というのは、意義どころか、一種の敗北主義すら感じて、嫌なのである。
さて、この辺りで、もう一方の展覧会『維新の洋画家 川村清雄』展の方にも触れておこう。
実はこちらの方も非常に意義深く、開国の歴史を垣間見る意味でも、存分に愉しめる内容であった。
川村清雄 (1852/嘉永5年ー1934/昭和9年)は幕末、旗本の家系に生まれ、武士として徳川家に仕えたが、大政奉還後、パリ、ヴェネツィアに渡って油彩画を学び、本格的な西洋絵画を日本に伝えた、当時、最も先駆的な画家の一人であった。
西洋絵画といってもこの人が面白いのは、決して西洋かぶれの発想ではなく、方法論としては伝統的な油彩の技法を駆使しながらも、テーマの中に、最も日本的なものの源流を追求した、全く希代の画家である。
川村清雄の場合、特筆すべきは、この時代にして圧巻の筆力、そして一方で、パトロンがあの勝海舟であったり、篤姫の遺影や福沢諭吉の肖像を描いていたりと、動乱の表舞台を照らす陰画のような活動の部分も興味深い。
余談になるが、実は小林清親も、もともと幕臣で、大政奉還後、一時、徳川家と共に静岡に下っていたことがあり、これは川村清雄と共通している。
考えてみれば小林清親は、浮世絵という日本の伝統技法を使って、あたかも西洋絵画のような見たての江戸風景を描いたのに対し、川村清雄は、技法としては西洋式のフォーマットだが、画題はあくまで純日本的なものを追求したわけで、これは何と、正対照を成す同時代人であったことになる。
やはりこの辺りが、この時代の混乱というか、問題の本質を語っているようで面白い。
それにしても今回、初めて拝む、川村作品の、職人的描画技巧の冴えは圧巻だった。
これは、パリ、ヴェネツィアにおける武者修行時代の研鑽ぷりが思い遣られる。
筆が走りまくって非常に気持ち良く、油絵本来の、理屈を超えた〝筆跡の快楽″を堪能できた。
中でも僕は何点か、決定的に魅了される作品にも出会えた。
ところで、実はこの川村清雄という画家が今注目されている(と思われる)一番の肝の部分は、実はこれまで日本美術史の中で、ほとんど忘れ去られてきた、ということがある。
実際、彼は、活動当時、既に「旧派」などと呼ばれ、その先見性、問題意識、斬新さは不当な評価に甘んじてきたという。
だが、今日観返す彼の作品とは、実に意外な程、新鮮なものであった。
一口に言えば、非常にソフィスティケートされているというか、大体、根底にあるものがモダンである。
「旧派」などという皮肉な呼称に反し、印象派あたりの猿真似絵画なんかよりずっと、古臭さ、野暮ったさが無く、誠実に伝わってくるものがある。
しかも、現代っ子の僕から観れば、和洋折衷の実験的な意匠や、一見、支離滅裂に見えるモチーフの変遷すら、何か、美術というより〝芸術″寄りのクールな謎かけに見えて格好いい。
まあ、そういう意味では、先の月岡芳年も川村清雄も、通底するのは、本格的な研究や再評価が待たれる、もしくは始まりかけた、同時代の作家だ、ということだ。
また、たまたまこの二人の大規模なレトロスペクティブが同時期に、都内で行われたということが、僕には少なからず、意義深いことに思われ、さっそく足を運んだのであった。
つまりその意義というのは、この二人の絵描きこそは、かつて日本人の自我が分裂し始める、全くその起点において、同じように葛藤し、それぞれ道を尋ね始めた最初の世代であり、したがってそこには、何か、日本人の最も原初的なアイデンティティをめぐる問いと指針が在りはしないか、という、ほのかな期待からであった。
★
さて、なんにしても僕らが突き当たるのは、いつも日本文化のアイデンティティの問題である。
元を正せば、我が国は、なまじ長いこと鎖国をしていたお陰で、明治維新によって極端に落差を伴う転換を経験してしまった。
その後、不可思議な、神話と合理主義をミックスしたような文化を形成し、更に今度は敗戦によって全てがぶった切られてしまった。
おまけに、その間、幾度となく災害や戦争で首都が焼失している。
要は我々とは、文化の地続き感に非常に乏しい、稀な民族なのである。
こうなるともう、何が日本人の本来の場所で、どこにアイデンティティを求めるべきなのか、さっぱりわからないのが本音であった。
ついでに言えば、今日の日本国民ほど、一般に歴史観念の希薄な民族は(少なくとも先進国中には)存在しないのではないだろうか?
それは、忘れなければやってこられなかったのか?失われたから忘れざるを得なかったのか?卵が先か鶏が先かは判然としないものの、ただ、結果的に今日、日本人が〝忘却の民族″になり果てていることだけは確かなように思う。