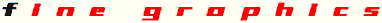Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
ロングテールズFILE;vol.24
ミヒャエル・ハネケ『白いリボン』で『堕落論』坂口安吾
最近、以前から観たい観たいと思っていた映画をようやく観た。
当代屈指の鬼才、ミヒャエル・ハネケ監督の最新作『白いリボン』である。
この作品は、第一次大戦前夜、ドイツの片田舎を舞台に、静謐で美しい歴史写真そのものの風景の裏で、秩序と美徳に押し込められた人間性の、実は陰湿で独善的な本性を淡々と浮き彫りにするものである。
全てのカットが息を呑むほど美しく、役者の風貌、身のこなし、画の構図など、およそこの上は考えられないほど、映画の最重要命題としての〝喪われた時の再生〟を完遂させている。
一方、この作品の場合い、こうした究極美の対比としてこそのハネケ・ワールドなのである。
この作品をありきたりの〝謎解きゲーム〟と取り違えて来た鑑賞者には、例によって、手酷いもやもやした後味悪さを残したかもしれない。
つまり、誰がどの件の犯人であるか、などは、何れ筋立てて考察してみれば推理できるだろう。しかし、そもそも、なぜ貴方は〝誰が〟を特定することが、即ちこの問題の解決だと考えるのか?という、それ自体、ハネケ流の痛烈な問い掛けに晒されるわけである。
結局、問題の核心は、人間社会の本質的、普遍的、歴史的な因果なのであって、決して〝解決〟という名の、都合の良いカタルシスを許さないのが、ミヒャエル・ハネケという作家の一貫した姿勢である。
もっとも、逆の言い方をすれば、遥か昔のドイツの村社会に巻き起こった小さな事件の連鎖(実際には殺人すら成立していない)について、犯人当てさせる意図の映画などあろう筈もない。
では、この映画でハネケ(オーストリアの映画監督)が見据えようとした真のテーマとは、一体、何だったのだろうか?
結論から言えばそれは、この作品とは、あの世界大戦の歴史、地獄の時代を産み落とした精神的風土へのシンプルな疑問、即ち、人々は何故、ナチスになったのか?または、最も初歩的人格形成の視点で、ナチズムとは一体、何処から来たのか?という、(ある種の表現的仮説に基づいた)社会歴史的人間考察なのである。
この作品は〝事の以前〟を観客に淡々と目撃させながら、今日に於いても普遍的な人間社会の秩序、道徳、そしてその裏の脆弱性や欺瞞との危うい関係をありのままに考えさせる。更にその先には、(戦争さえ連動するかに見える)負に向かう集合的無意識の不気味を炙り出すのである。
映画は第一次世界大戦が勃発するところで幕を閉じるが、大戦の前年、物語りの舞台となった1913年のドイツというのは、奇しくもミュールハウゼン村というところで、世界犯罪史に名を残す「ワグナー事件」(日本の都井睦雄事件との類型が指摘される)が発生した年であり、また、デュッセルドルフではペーター・キュルテンが最初の殺人を行った年でもある。
同じ頃、オーストリアではアドルフ・ヒトラーが放蕩暮らしの末、いよいよ、従軍志願し、今正に、未曾有の悪夢が姿を現そうとしているのである。
ところで、何故、人々は、かつて戦争やファシズムへの道に邁進したのだろうか?という疑問でいけば、無論、我が国も、ナチス・ドイツと同盟し、共闘した間柄である。これは他人事ではない。
それどころか、我々日本人とは、この映画の最も切実な観衆でなければならないと僕は思う。
『白いリボン』に倣えば、何故、日本人は望んで戦争し、自ら壊滅したのだろうか?
無論、歴史学的には、その原因というのは諸説諸々あるとされる。
例えば、日清・日露戦争に於いて大勝したことで軍部が奢り高まり、また、一般国民の間にも外国人に対する優越感と差別感情が生まれたから、とか、大日本帝国憲法では「皇軍」は天皇直属の軍隊とされていた。このため、中国大陸において陸軍(関東軍)が政府の指示を軽んじ、暴走したことがそもそもの始まりだ、とか、いやいや、大陸侵攻に伴う西欧列強の外圧(輸出停止などの制裁措置)に遭ったことのみが全てだ、とか、はたまた、陸軍省、海軍省の確執や官僚体質も一因といえる、とか、元々、マスコミが一般国民に戦勝気分を煽り過ぎたせいじゃないのか?とか、少々、聞き囓っただけでも、これはもう様々である。
このように、具体的要因としては諸々あるけれど、何が本当か?といえば、個人的には、どれも本当であろうと思う。
しかし、この際、『白いリボン』に寄せて考えるなら、もっと潜在的なメンタリティの綾(あや)の部分、つまり、かつての日本民族にまつわる美徳や道徳(宗教、武士道、謙譲の精神)というものと、その背後にある生身の欲望や欺瞞がどのように相互作用することであれだけの破壊を産むに至ったのか?その辺の人間考察についても、もっと思いを馳せる必要がありそうだ。
事実、僕らは当時の人々の心の内に起こったこと、その内面の真相について、余りに何も知らないのである。
さて、そうした意味では、当時の日本人というものの本音の部分を浮き彫りにする貴重な告白文学がある。
坂口安吾の『堕落論』である。
ハネケの『白いリボン』が第一次大戦前年のドイツを舞台にした虚構であるのに対し、この作品は、第二次大戦終結の翌年、日本で綴られた実際の戦争論、あるいは民族論である。
ドイツと日本、二つの大戦の前後両端を、虚構的推論と実体験によって立体的に眺めて見ることで、何か見出せるものがあるのではないか?
そういう思い付きから、以降、坂口安吾の『堕落論』を全文掲載してみようと思う。
そして、これらを通して我々が考えなければならないこと、それは、〝何故、人々は罰せられなければならなかったのか?〟ということである。
堕落論
坂口安吾
半年のうちに世相は変った。
昔、四十七士の助命を排して処刑を断行した理由の一つは、彼等が生きながらえて生き恥をさらし
この戦争中、文士は未亡人の恋愛を書くことを禁じられていた。戦争未亡人を挑発堕落させてはいけないという軍人政治家の魂胆で彼女達に使徒の余生を送らせようと欲していたのであろう。軍人達の悪徳に対する理解力は敏感であって、彼等は女心の変り易さを知らなかったわけではなく、知りすぎていたので、こういう禁止項目を案出に及んだまでであった。
いったいが日本の武人は古来婦女子の心情を知らないと言われているが、
武士は仇討のために草の根を分け乞食となっても足跡を追いまくらねばならないというのであるが、真に復讐の情熱をもって仇敵の足跡を追いつめた忠臣孝子があったであろうか。彼等の知っていたのは仇討の法則と法則に規定された名誉だけで、元来日本人は最も憎悪心の少い又永続しない国民であり、昨日の敵は今日の友という楽天性が実際の偽らぬ心情であろう。昨日の敵と妥協否
小林秀雄は政治家のタイプを、独創をもたずただ管理し支配する人種と称しているが、必ずしもそうではないようだ。政治家の大多数は常にそうであるけれども、少数の天才は管理や支配の方法に独創をもち、それが
私は天皇制に就ても、極めて日本的な(従って或いは独創的な)政治的作品を見るのである。天皇制は天皇によって生みだされたものではない。天皇は時に自ら陰謀を起したこともあるけれども、概して何もしておらず、その陰謀は常に成功のためしがなく、島流しとなったり、山奥へ逃げたり、そして結局常に政治的理由によってその存立を認められてきた。社会的に忘れた時にすら政治的に
すくなくとも日本の政治家達(貴族や武士)は自己の永遠の隆盛(それは永遠ではなかったが、彼等は永遠を夢みたであろう)を約束する手段として絶対君主の必要を嗅ぎつけていた。平安時代の藤原氏は天皇の擁立を自分勝手にやりながら、自分が天皇の下位であるのを疑りもしなかったし、迷惑にも思っていなかった。天皇の存在によって御家騒動の処理をやり、弟は兄をやりこめ、兄は父をやっつける。彼等は本能的な実質主義者であり、自分の一生が
我々にとっては実際馬鹿げたことだ。我々は靖国神社の下を電車が曲るたびに頭を下げさせられる馬鹿らしさには閉口したが、或種の人々にとっては、そうすることによってしか自分を感じることが出来ないので、我々は靖国神社に就てはその馬鹿らしさを笑うけれども、外の事柄に就て、同じような馬鹿げたことを自分自身でやっている。そして自分の馬鹿らしさには気づかないだけのことだ。宮本武蔵は一乗寺下り松の果し場へ急ぐ途中、八幡様の前を通りかかって思わず拝みかけて思いとどまったというが、吾神仏をたのまずという彼の教訓は、この自らの性癖に発し、又向けられた悔恨深い言葉であり、我々は自発的にはずいぶん馬鹿げたものを拝み、ただそれを意識しないというだけのことだ。道学先生は教壇で先ず書物をおしいただくが、彼はそのことに自分の威厳と自分自身の存在すらも感じているのであろう。そして我々も何かにつけて似たことをやっている。
日本人の如く権謀術数を事とする国民には権謀術数のためにも大義名分のためにも天皇が必要で、個々の政治家は必ずしもその必要を感じていなくとも、歴史的な嗅覚に於て彼等はその必要を感じるよりも自らの居る現実を疑ることがなかったのだ。秀吉は
要するに天皇制というものも武士道と同種のもので、女心は変り易いから「節婦は二夫に
まったく美しいものを美しいままで終らせたいなどと
死んでしまえば身も
私は血を見ることが非常に嫌いで、いつか私の眼前で自動車が衝突したとき、私はクルリと振向いて逃げだしていた。けれども、私は偉大な破壊が好きであった。私は爆弾や
私は疎開をすすめ又すすんで田舎の住宅を提供しようと申出てくれた数人の親切をしりぞけて東京にふみとどまっていた。大井広介の焼跡の防空壕を、最後の拠点にするつもりで、そして九州へ疎開する大井広介と別れたときは東京からあらゆる友達を失った時でもあったが、やがて米軍が上陸し四辺に重砲弾の
けれども私は偉大な破壊を愛していた。運命に従順な人間の姿は奇妙に美しいものである。
あの偉大な破壊の下では、運命はあったが、堕落はなかった。無心であったが、充満していた。猛火をくぐって逃げのびてきた人達は、燃えかけている家のそばに群がって寒さの煖をとっており、同じ火に必死に消火につとめている人々から一尺離れているだけで全然別の世界にいるのであった。偉大な破壊、その驚くべき愛情。偉大な運命、その驚くべき愛情。それに比べれば、敗戦の表情はただの堕落にすぎない。
だが、堕落ということの驚くべき平凡さや平凡な当然さに比べると、あのすさまじい偉大な破壊の愛情や運命に従順な人間達の美しさも、
徳川幕府の思想は四十七士を殺すことによって永遠の義士たらしめようとしたのだが、四十七名の堕落のみは防ぎ得たにしたところで、人間自体が常に義士から凡俗へ又地獄へ転落しつづけていることを防ぎうるよしもない。節婦は二夫に見えず、忠臣は二君に仕えず、と規約を制定してみても人間の転落は防ぎ得ず、よしんば処女を刺し殺してその純潔を保たしめることに成功しても、堕落の平凡な
特攻隊の勇士はただ幻影であるにすぎず、人間の歴史は闇屋となるところから始まるのではないのか。未亡人が使徒たることも幻影にすぎず、新たな面影を宿すところから人間の歴史が始まるのではないのか。そして或は天皇もただ幻影であるにすぎず、ただの人間になるところから真実の天皇の歴史が始まるのかも知れない。
歴史という生き物の巨大さと同様に人間自体も驚くほど巨大だ。生きるという事は実に唯一の不思議である。六十七十の将軍達が切腹もせず
私は
終戦後、我々はあらゆる自由を許されたが、人はあらゆる自由を許されたとき、自らの不可解な限定とその不自由さに気づくであろう。人間は永遠に自由では有り得ない。なぜなら人間は生きており、又死なねばならず、そして人間は考えるからだ。政治上の改革は一日にして行われるが、人間の変化はそうは行かない。遠くギリシャに発見され確立の一歩を踏みだした人性が、今日、どれほどの変化を示しているであろうか。
人間。戦争がどんなすさまじい破壊と運命をもって向うにしても人間自体をどう為しうるものでもない。戦争は終った。特攻隊の勇士はすでに闇屋となり、未亡人はすでに新たな面影によって胸をふくらませているではないか。人間は変りはしない。ただ人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。人間は生き、人間は堕ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。
戦争に負けたから堕ちるのではないのだ。人間だから堕ちるのであり、生きているから堕ちるだけだ。だが人間は永遠に堕ちぬくことはできないだろう。なぜなら人間の心は苦難に対して鋼鉄の如くでは有り得ない。人間は可憐であり
底本:「坂口安吾全集14」ちくま文庫、筑摩書房
1990(平成2)年6月26日第1刷発行
底本の親本:「堕落論」銀座出版社
1947(昭和22)年6月25日発行
初出:「新潮 第四十三巻第四号」
1946(昭和21)年4月1日発行
入力:砂場清隆
校正:高柳典子
2006年1月11日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。