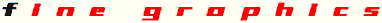Longtail`s Cafe BACK NUMBERS
ロングテールズFILE;vol.22
シーンで綴る、〝反権力〟シネマテーク
本年、2011年1月28日、三重県志摩の海上で、約一ヶ月前に発見された遺体が、映画監督、池田敏春さんのものであることが発表された(三重県警発表)。
死因は不明。ただ、昨年末24日に知人宅を出たまま足取りが解らなくなっていたという。
★
例によって少しばかり古い話しになるが、1984年公開の日本映画『人魚伝説』、それは掛け値なしに壮絶な〝後味〟を残す一縷(る)の爪痕のような作品であった。
主演は艶かしい刃と化す白都真理。
プロデュースは、ある一時期、間違いなく日本映画シーンの台風の目であったディレクターズ・カンパニー。
しかもこれはその第一弾として公開された記念碑的作品でもあった。
僕は近頃、ふと、この映画のことが頭をよぎった。
というのも、今年に入って、この作品の監督、池田敏春が穏やかならざる状況で急逝したこと、その後に襲ったあの大津波、それに原発の暴発といったことが頭の中で一点の像を結び、銀幕の記憶を蘇らせたのだ。
凶刃としての海。原発利権の深い闇。そして折り重なる屍の群れ。
奇しくも、池田敏春監督はこれに先立つように海に還っている。
「一体、何人殺したら終わるんやろう」
映画の終盤、権力に挑む修羅と化したファム・ファタール(運命の女)、「みぎわ」による無差別殺戮と、一転、幻想的な海中(静かな死の暗喩)に誘う〝人魚〟のシルエット。
映画『人魚伝説』とは自然と権力(男性性)と情念(女性性)をめぐる暗黒のファンタジーなのであった。
デジャヴュ。上手くは言えないが、何かこの映画の持つ〝悪夢の澱(おり)〟のようなものが、昨今、現実のキーワードと相まって、泡沫(うたかた)の蜃気楼のように、僕の胸に蘇って来るのだった。
★
さて、何故か唐突に『人魚伝説』など思い出している僕だが、ところで、この映画が公開された1984年当時というのは、実は早くも日本映画の凋落が叫ばれて久しい頃である。
観客動員数も、一部の大作を除いて全般的に下降の一途を辿っていたと思う。
しかしながらその中身、つまり映画表現としての質や情熱は、およそ今日からは考えられないくらいとんがっていた。
殊に、若い日本映画特有の、あのギラついた生命感。
そこでは、あたかも過剰なまでの凶暴性を孕んで、それこそ競って時代を挑発するのが流儀であった。
言わずもがな、いつもその核にあったもの、それは〝反権力〟の眼差しである。
もっともそれは、僕の説では、あくまで〝反権力〟であって、あながち〝反体制〟という意味ではない。
つまり、特定のイデオロギーや、その時々の体制批判などに留まることなく、人間存在の本性に至る衝動、苛立ち、怒り、絶望、即ちすべての欺瞞を取っ払った生身の欲望を、これでもかとストレートにえぐり出すスタイル。
そしてその末に、あらゆる権威・権力を逆照射し、批判し、嘲笑し、狙い撃つ。
そういう気骨みなぎる〝反権力〟な風景が、かつて日本映画に渦巻いていたわけである。
反権力な風景。それは、ワンシーンで語り尽くす、時代の殺気。反骨の萌芽。凶暴な夢。
ところで、僕は常日頃から映画を〝シーン〟で考えることを習慣としている。
何故なら、優れた映画とは、必ずワンシーン・ワンカットのみで事の核心を語り尽くすイメージ喚起力を持つものだ、という自論があるからだ。
あらゆる問題提起はすべからく〝情景〟の中にシンボライズされるべきである。
また、本来、脈略ある構造体としての映画を、単なる意味の文脈から離れ、純粋に詩的イメージの羅列と捉えてみたらどうだろう?あるいは自分だけのスクラップ・ブックに独自の映画史が現出するかもしれない。
★
さて、日本映画における反権力な風景を思い出してみよう。― まあ、お題目の通り、これは別に脈略があるというものではない。単に思いつくまま気の向くまま、掬い上げてみるまでである。
反権力、つまり〝反骨の情景〟として僕が先ず筆頭に思い浮かべるのは(少々ベタではあるけれど)何と言っても『八月の濡れた砂』(藤田敏八監督作品)のラストシーンである。
ご存知、石川セリのヒットナンバー(タイトル曲)をバックに、あてどなく海に乗り出すヨットの俯瞰。
あたしの海を まっ赤に染めて
夕日が血潮を 流しているの
あの夏の光と影は どこへ行ってしまったの
悲しみさえも 焼きつくされた
あたしの夏は あしたもつづく
(主題歌『八月の濡れた砂』より)
1971年公開『八月の濡れた砂』という作品の背景には、二つの時代の終焉が交錯している。
一つは、政治の季節の終焉。
もう一つは当時の映画状況の、いわゆる撮影所システムの終焉。
政治の季節の終焉、というのは、この頃の社会背景として、鬱屈した若者の心情の根底に学生運動の挫折があったことを意味する。
この作品の全編を通した虚無感や刹那的快楽主義には、当時揶揄された「しらけ世代」と呼ばれる〝遅れて来た若者達〟の、行き場のない苛立ちが吐露されているわけだ。
また、撮影所システムの終焉というのは、丁度この作品あたりを最後に、日活は一般映画製作を断念し、以後、ロマンポルノの製作に移行してゆくことになる(大映は倒産)。
つまり、かつては隆盛を極めた日本映画界も、この頃を境に、本格的に斜陽化が進むのである。
学生運動の絡みで言うと、この映画が封切られた翌年の1972年2月(ちょうど半年後)には、例のあさま山荘事件が発生する。
連合赤軍の凶行が明るみに出るに至って、世間の共産化運動へのシンパシーも完全にご破算となった。
ところで僕は、どうもこの『八月の濡れた砂』のラストシーンには、わずか後の連合赤軍事件を予見しているようなイメージがあって仕方がないのだ。
そうして考えてみると、あの石川セリの唄った歌詞も、妙に酸鼻なリアリティーを持ってくるようである。
あたしの海を まっ赤に染めて
夕日が血潮を 流しているの
あの夏の光と影は どこへ行ってしまったの
悲しみさえも 焼きつくされた
あたしの夏は あしたもつづく
「あたしの夏は あしたもつづく」というくだりに、決して免責されることのない革命兵士の十字架を連想するのはいささかうがち過ぎだろうか?
もっとも、「あたしの海を まっ赤に染めて 夕日が血潮を 流しているの」という歌詞や、劇中の、赤い船倉に発砲し、朱に照り返されながら涙を流すカットとは、もともと〝赤い思想〟の挫折を普遍的にシンボライズさせたものなのかもしれない。が、しかし、何れにせよ、あの大海に閉ざされた孤立無援の閉塞感、内に篭る凶暴性、そして引き裂かれそうな敗北のイメージとは、すべての〝末路〟を含めて『八月の濡れた砂』があらかじめ時代の核心を語ってしまっていたからには違いないのである。
時代に敗北し、どこにも行くあてのないまま、それでも海に漕ぎ出すヨット。彼らは怒りと慟哭と苛立ちをとも連れに、夢の終わりを背負っていたのであった。
★
そう言えば、ちょうどこの頃の「しらけ世代」の典型を、ある種ヒロイックに造形した作品と言えば、長谷川和彦監督の傑作『青春の殺人者』と『太陽を盗んだ男』があった。
長谷川和彦監督はご存知の様に、先述の『人魚伝説』を製作したディレクターズ・カンパニーの代表だったわけだが、僕が学生の頃、この長谷川監督が連合赤軍事件を映画化するらしいという噂に何度となく湧いていたのを憶えている。
というのは、その当時はまだ、共産ゲリラの武装闘争が幾らかリアルな時代で、連合赤軍ものというのが今では考えられないくらいタブー視されていたからである。
しかし結局、長谷川監督は夢やぶれたようで、後に、やや連赤ネタとして『鬼畜大宴会』(1997年公開 熊切和嘉監督)が、またその後しばらくして、ようやく長谷川監督の盟友、高橋伴明監督が、立松和平の原作をベースに実際の連合赤軍に迫った『光の雨』(2001年公開)を発表した。
しかし、結局、究極の解答としての〝連赤映画〟と言い切れる作品は、2007年まで待たなければならなかった(この間、警察側の視点であさま山荘事件を捉えた『突入せよ! あさま山荘事件』(2002年 原田眞人監督)があるが、これを連赤映画と呼んではいけない)。
では、その究極作とは何かというと、言うまでもなく、若松孝二監督の『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(みち)』である。
何故これが、大勢が認める決定版と言えるかといえば、一つには、そもそも若松監督は実際の事件当時、赤軍とコンタクトを取っていて、重信房子(後の赤軍リーダー)などとも関係があった。そして何より、山岳ベースで粛清された、あの遠山美枝子とさえ知人であったことが挙げられる。
そしてもう一つには、元々、若松監督の映画的資質が、余りに〝連合赤軍的〟なものだったからだ。
映画的資質が〝連合赤軍的〟なんていうと、いくらなんでも物騒に聞こえるかもしれないが、しかし実際、若松監督の作品とは紛れもなく〝物騒〟なのである。
さて、本題の〝反権力な風景〟に戻ろう。
例えば、若松監督の二本の作品、『ゆけゆけ二度目の処女』(1969年公開)と『水のないプール』(1982年公開)。
言わずもがな、これらをピックアップした理由とは、僕の言う〝反権力〟という意味において、若松孝二に触れないなどということは考えられないからだ。
まずは、『ゆけゆけ二度目の処女』のワンシーンから。
〝密猟者〟が去った最初の朝、屋上(彼らの砦)から、少年と少女が、シラけた真昼の街を見下ろしている。
「あたし、輪姦されたのこれで二度目なの」
「昨日〝あの時〟、夢見てたんだろ?」
「夢なんか見なかった。とっても疲れただけ」
〈街〉。今や彼らにとって無縁とも思われる、その白く高慢な地獄を見つめながら、ふと、少年、少女は苦笑いにも似た愛想笑いを交わしあった。
この作品、『ゆけゆけ二度目の処女』という変なタイトルの映画は、若松孝二監督の、最も過激な初期ピンク映画の系譜に連なる一本である。
特に僕がこの作品を好みな理由の一つは、1969年という時代背景にして、敢えてあからさまな〝政治性〟が言及されることなく、しかも、強烈にイマジネーティブなヌーベルバーグの手法を採用している点である。
若かりし日の秋山道男(当時、秋山未痴汚名義)氏の存在感、そして何といっても、あの、山下洋輔トリオの超クールなフリージャズが、通り一遍の主張や些末な〝意味〟を超越し、一服の血塗られた詩篇へと昇華している(そもそも「ゆけゆけ二度目の処女」というのは、劇中で自殺願望の少女が唱える詩の一説である)。
また、この作品の実に注目すべき点として、その後の、つまり、今日の若者の内向する〝凶気〟を、不気味なまでの正確さで予見している点が挙げられる。
他人と自らの生を無自覚に、軽々と越境するあの浮遊感は、決して、当時の政治闘争の脈略と地続きのものではなく、むしろ今日の我々が問いかけられる問題、即ち、あの、生命(いのち)の闇なのである。
もう一度、宵が明けたら、子供達はトラウマの繭を食い破り、手摺の外側へ飛翔するだろう。
「ママ ぼく でかける」。
因みに、この作品の脚本は、後に『ルパン三世』でも誉れ高い大和屋竺(『ゆけゆけ…』では出口出名義)だが、実は彼は前出の『八月の濡れた砂』の共同脚本家でもある。いやはや流石(さすが)!個人的に、若松孝二監督と並んで〝反権力大王〟の称号を進呈したい程である。
★
ところで、水を湛えないプールとは、単なる巨大な石棺だろうか?
いや、違う。何故ならそれは、〝水〟という快楽の〝記憶〟を確かに留めているからだ。
つまり、厳密に言えばそれは、記憶や願望で満たされた〝単なる石棺〟なのである。
そして、何れにせよ「水のないプール」は実益のない、無用の長物なのだ。
さて、今度はもう一方の若松作品『水のないプール』から一場面。
不覚にも自ら仕掛けたクロロホルムの罠に落ち、〝夢犯〟の男が目覚めた時にはゲーム・オーバーであった。
欲望と現実が無惨な対面を果たし、時は変質した。「水のないプール」というゲームの本質が姿を現す。
女が見つめ、男が不適に笑う。男は、苛立たしい現実を矮小化させ、プールを願望で満たすゲームに勝った、と思った。
やがて、パトカーのサイレンが二人の捻れた夢想を引き剥がす。
この『水のないプール』という作品は、当時、実際に起こった三面記事的とんでも事件をベースにしている。
この犯罪の性格は、勿論、相当に歪んだ、不可解なものだが、しかしだからといって、決定的に大それたものでもない(若松作品にしては)。ある意味、『屋根裏の散歩者』の性犯罪版とでも言おうか。
「「恋の三角関係」どころではありません。五角、六角と、複雑した関係が、手に取るように見えるばかりか、競争者たちのだれも知らない本人の真意が、局外者の「屋根裏の散歩者」にだけ、ハッキリとわかるではありませんか。おとぎ話に隠れみのというものがありますが、天井裏の三郎は、いわばその隠れみのを着ているも同然なのです。」(江戸川乱歩『屋根裏の散歩者』)
但し、この作品には僕の言う〝反権力〟の眼差しが濃厚である。
事実、この映画は、いわゆる、内田裕也ものの決定版の一つ、『コミック雑誌なんかいらない!』のラスト・カットで吐かれる、あの「I can't speak fucking Japanese ! (糞いまいましい日本語なんか喋れるか!)」という痛烈なスピリットの原点であり、かつ、映画的に緻密な細部の積み重ねを経て、犯罪ものとしてのリアリティーも併せ持つ、紛れもない良作なのだ。
またそれと同時に、これ程〝孤独〟を鮮やかに浮き彫りにする作品も稀だと思う。
しかもそれは、余りに我々の現実と相似形の孤独である。
安易なフィクション、つまり、気休めの希望や救済を非情なまでに告発する、という意味でも、これは誠に危険な映画であった。
それにしても、この物語の最大のポイントとは、男が〝夢姦〟つまり、意識下で女を犯すだけに飽き足りず、現実に侵犯しようとしたことの誤算、つまり、女のために朝食を用意するなどして、〝夢の痕跡〟を残し始めたことに尽きると思う。
万が一、完璧にやり遂げれば、それは、永久に〝実体化〟することのない、純粋本能のまぐわりであり続けたかもしれないのである。
空っぽのプールに〝願望〟でなく〝本物の〟水を注ごうとして自滅する男。最終的にこの映画は、果たしてそれは男の〝誤算〟だったのか?それとも…、と観客に問いかけるのであった。
★
時に、ここまではまた、えらく反権力らしい反権力な映画を取り挙げてきたようだが、しかし、本来、反骨の眼差しとは、決して暴力と対のものではない。と、いうより、本質的には、元々、この両者に、何の関連性も無いのである。
それはただ、ある時、ある時代、反骨表現の〝効率〟として暴力が描かれた(そしてそうした作品は比較的多く存在する)と言うに過ぎない。
そういう意味では、それらとは一見、対局にある作品でありながら、一方で強烈な気骨を備えた一品として、忘れられない映画がある。
それとは、根岸吉太郎監督の『遠雷』(1981年公開)である。
「あんたの友達、死刑になるの?」
「自首したから10年ぐらいだって警察で言ってたぜや. 三十三になりゃあ、出てくるべ」
宅地化が進む地方のマンモス団地。
その一角にしがみつくように根を張るトマト畑の前で、若い夫婦が干し草を燃やしている。すると、何処の都市部から来たとも知れない土地買収の人間達が慇懃に菓子折りを差し出してくる。
若い亭主は〝アブラ虫〟を追い払う様に手荒く一蹴した。
「顔、真っ黒だぞ」
「変?変なら洗ってくるけど」
「いいさ、おしろい塗って、百姓やる奴なかんべ」
雲行きのわからない空の彼方で遠雷が鳴った。
新婚夫婦は眩しそうに稲光を見上げている。
『遠雷』は、前掲の『人魚伝説』を撮った池田敏春監督と日活時代、同期入社の根岸吉太郎監督が、ロマンポルノを経て、始めてATG(日本アートシアターギルド)で撮った一般映画である(因みに、根岸監督は、かつて、ディレクターズ・カンパニーに所属し、当の『人魚伝説』のプロデューサーも務めている)。
原作は、これも少し触れた『光の雨』の原作者、立松和平。
ところで、僕はこの『遠雷』という(主題通りに)素晴らしく外連味の無い作品を、何か無性に愛おしいものに感じている。
この作品の、生きることへの〝気概〟がどうにも凛々しく思われて好きなのである。
それと同時に、この作品が警鐘を鳴らす日本の将来とは、行き着くところ、今、我々が直面している〝最悪のシナリオ〟のように感じられて仕方がないのだ。
そのことは、まず、前述の『水のないプール』(1982年)と、この『遠雷』(1981年)を対比させて眺めてみると、明白化する。
両作品とも、製作時期はほぼ一緒。舞台となるのは都会と地方都市(『水のないプール』が東京を舞台とするのに対し、『遠雷』は栃木の宇都宮近郊が舞台である)。
『遠雷』に於いても『水のないプール』に於いても、重要なテーマとなるのは「性」の問題であった。
しかし、この両者の性の捉え方は余りに対照的である。
『水のないプール』に於いて、あれほど捻れた孤独のはけ口であった性欲が、『遠雷』では、至っておおらかな、明け透けなまでの衝動として描かれている。
(無論、古典的な日本古来の土着習俗を踏まえて)ここでは、良くも悪くも多くの問題が「性」、即ち、根源的な生本能の上に立ち上がるのに対し、『水のないプール』の都会では、あらかじめ全方位が閉ざされ、その一つの突破口として性欲だけを突出させた無惨が展開されている(しかも、それは、内向する、願望としてだけの性である)。
言うまでもなく、この肉感性は、人間関係のあらゆる端々に至るまで対照的だ。
有り体に言えば、1981年当時、『遠雷』の主人公が抗っていた、得体の知れない世界とは(あのマンモス団地が象徴し、『水のないプール』が体現するような)、物質的隔絶社会なのである。
役割りと目的だけが存在する〝科学的で合理的〟な社会。
それは、『水のないプール』のあの、切符切りの男を廃人にした、個々人の根源的な生命力を吸い上げ、膨張するだけの世界像だ。
そしてその先、そのまた先にどんなことが起こるのか…、残念ながら、我々は知っている。
結局のところ、この映画『遠雷』は、この主人公の若者をひとつのヒーローだ、と言っているのである。
更に彼ら夫婦を、この国の希望だ、と。
だとするならば、僕は、この国にはまだまだ、真の意味のヒーローは沢山存在すると思う。
大切なのは、彼らが折れないで済む社会を考えてゆくことである。
そして、よしんば、ヒーローになれなくとも、我々皆が、満夫とあや子のように、のびのび、逞しく、泥臭いまでの気概を持って歩み出すこと、これを映画『遠雷』は提案しているのであった。
★
さて、先にも述べたが、映画表現というものは、(『遠雷』のように)必ずしもあからさまな暴力描写だけが、内に秘めた反骨の眼差しを保証するものではない。
そういう意味ではまた、極端に抑制された表現の中に、決して媚びない、無垢の魂を活写することもあり得るわけだ。
この意味で僕が忘れ難いのは、北野武監督の『あの夏、いちばん静かな海。』である。
特筆すべきは、この映画では(本来、十八番であるところの)暴力描写を、敢て一切排除することで、逆に、北野映画の根底に流れる、映画そのものの〝殺気〟がストイックに際立っている点だ。
極めてシンプルなラブストーリーでありながら、全編、ある種の禍々しさにも似た緊張感に満ち、それはもう、『ソナチネ』と比べても遜色ない程である。
こうした特異な映画空間が、果たして何によって生成されているかというと、特にこの映画の場合い、その画作りによるところが大きい。
極端に削ぎ落とされたカメラワーク、僅かな移動を省いて、殆ど、固定のショットのみで繋ぎとめられたシークエンス。
斜めの構図を意図的に排し、対象を正面で捉えているから自ずと画に奥行きが失われる。つまり、この作品は、厚みというものを拒否しているのである。
また、これに加えて、この映画は、一口に言って、〝風景〟の映画であった。
あたかも、実景ありきの画角の中に人物を当て込んだかのような、劇と背景の位相がどこか転倒している点にこそ注目である。
かつて、北野監督の発言の中に、全てのカットがどこから取っても、絵画のように一枚画として成立していることが理想だ、というのがあったけど、この映画『あの夏、いちばん静かな海。』では、まるで、ジョージ・シーガルの彫刻や、エドワード・ホッパーの絵画を見るような、〝景色の中に孤立する人物の肖像〟とでも呼ぶべき本質論、つまり、人間存在の〝孤独〟が、言下に語られてしまっているのであった。
また、付け加えるなら、こうした画づくりの冒険は、無論、〝音〟にも連動していて、つまり、聾唖(ろうあ)のカップルが主人公のこの映画は、あらかじめ主体としての音(声)が失われている。加えて、(会話も含めて)殆どの劇中音が、まるで潮騒と同等の環境音、つまり〝風景〟の役割りに留められているのだ。
このことによって映画は、いよいよ矮小な意味や作為の呪縛を逃れ、人間も含めたある種の自然観、ひいては、無常のものの象徴としての〝海〟自体にクローズアップしてゆくのであった。
ところで、この映画には唯一、ワンカットだけ、聾唖の主人公が見た主観ショット、つまり、〝あの夏、いちばん静かな海〟が登場する。
それは、映画のファースト・ショットである。
暴力的に切り取られた、どんよりアスファルトのような無音の海面に白い旗が立っている。
主人公の青年がゴミ収集車の中から見詰めている設定だ。
一見、この映画は、清楚なラブ・ロマンスを装うかに見える。
しかし、かつて僕は、このカットほど険のある海を見た気がしない。
それは、甘事では済まされない、〝牙〟を持った視点であり、実にこれが、唯一、観客が追体験できる、あの夏、いちばん静かな海、だというのである。
どだい、こんなカットから導入する映画が並の恋愛ものである筈もないのであった。
★
ところで、北野武監督といえば、もうひとつ、かつて僕の心に引っ掛かった初期の傑作、『3-4x10月』(1990年公開)というのがあったが、これと図らずも奇妙な共通項を持つ、もう一本の日本映画があった。石井隆監督の『GONIN』(1995年公開)である。
では、この二本の〝共通項〟とは何かというと…、
まず、プロデュースが奥山和由(当時、松竹)であること。
また、どちらも、俳優・ビートたけしが、凶暴で、身内からも煙たがられるヤクザ者を演じていること(物語では同じ様に後半、登場する)。
双方ともに、大筋で群像劇だが、軸となるのは主人公を含めた、男二人組であること(『3-4…』では柳ユーレイとダンカンが、『GONIN』では佐藤浩市と本木雅弘がそれぞれ演じている)。
作品の根源的テーマが『GONIN』の売り文句にあるような〝キレたら止まらない〟、つまりは、〝殺気立つ街〟というようなものであること。
主要人物が全て男であること(『GONIN』の中でやや重要な「ナミィー」という役があるが、メインの役割りではない)。
そもそもストーリー自体が同じ様に、一般人が本職のヤクザと抗争を繰り広げる話であること。
更には、重要な起点となるシーンに、何故か〝野球〟というものが据えられていること…などである。
もし逆に、あの二作品が、上記のような示し合わせの縛りの元、競作されたものだったら、などと連想してみると、これは非常に興味深く、また、個性が際立っている。
ところで、上に挙げた共通項の中でも、特に僕が気になるのは〝野球にまつわるエピソード〟についてである。
「振らなきゃ始まんないよ」
『3-4x10月』という作品の中で、そもそも、タイトルの由緒(いわれ)ともなる重要な要素が、例の、草野球のシーンだ。
映画の冒頭、暗闇の中に薄っすら顔が浮かび上がり、カットが変わると主人公が仮設トイレから出てきて草野球に合流する。
ここからカメラは、何故か延々と草野球試合の経過をスケッチしてゆくわけだが、注目すべきは、何か非常に殺伐とした空虚感と共に、そこかしこに沸々と殺気立ってゆく空気である。
まるで、初期、大友克洋の漫画の一場面を彷彿とさせるような、開放的だが、からからに乾いた群衆シーン。
ここではまだ、久石譲によるリリカルなメロディーは登場せず、それどころか、この映画には一切、音楽というものが使用されていない。
一見、のどかに見える、こんな俗な街の情景の奥底にさえ、実は、不気味な闘争本能がくすぶっていて、やがて火種は小さなきっかけを得て焔(ほのお)となり、焔は、凄まじい暴力となって狂気に転換することを、この映画は語っている。
つまり、『3-4x10月』という作品の魅力とは、こうした、一見、泥臭く、俗っぽい等身大の表象を持ちながら、しかし一転して集合的無意識とも言うべきソリッドな狂気に転換する鮮やかさであった。
そしてまた、僕はこの草野球のシーンこそ、北野映画の一つの原点であり、また、最も象徴的な風景の一つであったと今でも思っている。
一方、こうした『3-4…』の文脈に呼応する、石井隆作品『GONIN』の中のイメージと言えば、何と言っても、あの、バッティングセンターのシーンであろう。
新宿歌舞伎町。スーツ姿のまま、酔った、やさぐれサラリーマン達が遮二無二バットを振っている。
ここでも、鬱屈した、凶暴な闘争本能を剥き出しにした男たちは、無闇矢鱈にカキン、カキンとバットを振り回すのであった。
隣の打席では数人が揉み合い「手目ェ、イラつくんだよっ!」と殺気立っている。
物語りはこの場所に、集うべくして集った男たちの因縁によって動き出す点でも『3-4…』と通底している。
『GONIN』では、タイトル通り、5人の崖っぷちの男たちが、乗るかそるか、〝バッター・ボックス〟に入ることになる。
無論、〝振らなきゃ始まんない〟からである。
しかも、彼ら〝闘争本能〟の向かうベクトルとは、いみじくも、強大な〝権力〟(ここでは暴力団)であった。話し合って解る相手なら(言葉になるが)画にならないということなのであろう。
結論から言えば、『3-4…』に於いても『GONIN』に於いても、そこに何ら大義らしい大義は無く、いわば、切羽詰った犬同士が喰らい合い、成り行き、自滅してゆく構図であった。
しかし、この両作品とも、そもそも、男という性が本能的に背負っている〝渇き〟の正体、つまり、〝闘争本能〟というものをシンプルに浮かび上がらせる意図としては、日本映画史に於いても無類であった。
ところで、僕は、これら二作品に於ける、〝バット〟や〝バッター・ボックス〟つまり、〝闘争心〟〝勝負〟転じて〝暴力的衝動〟を表す比喩が、そもそも〝野球〟であることに注目したい。
何故なら、この場合い、サッカーでは絶対、駄目なのである。
というのも、「野球」が持つ大衆性、俗っぽさ、どこか洗練されない野暮ったさ、というものが、北野武、石井隆という作家性の一面を語る上で、どうしても外せない、共通のファクターだと思うからだ。
既に述べたように、〝一見、泥臭く、俗っぽい等身大の表象を持ちながら、しかし一転して集合的無意識とも言うべきソリッドな狂気に転換する〟ドラマツルギーに於いて、常に日常のリアリティーを担保することこそ生命線であり、そういう意味で、ここでは、「野球」というキーワードもまた、日々の形骸を浮き彫りにする重要な映画言語たり得たのであった。